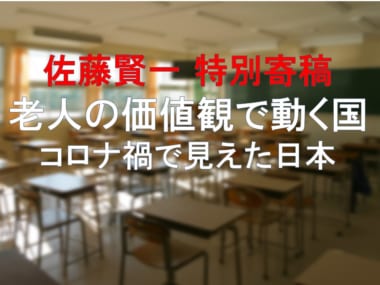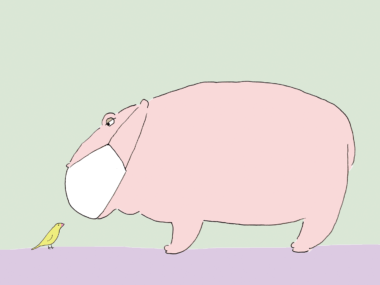2020.7.6
第7回 カレーのきた道

2001年の夏、私は虎屋の羊羹を抱えて横須賀へ向かっていた。謝罪をするためだ。
出版社に入って初めて担当した特集号で、横須賀にあるカレー屋を取材した。
謝罪の原因となったのは、誤植だった。当時は原稿を電話口で読み上げ、お店のひとに聞いてもらって確認作業をしていた。その店ではじゃがいもを使っていない──しかもそれがレシピの肝だ──にもかかわらず、私は誌面に書き入れてしまったのだ。電話口でどんな行き違いがあったのか、今となっては記憶も定かでない。
料理と真摯に向き合ったことのない新人編集者の無知。当然じゃがいもが入っているという思い込みがあったのかもしれない。
それ以来カレーを前にするたびに具が気になって仕方ない性分になった。それがこうして料理の仕事に生かされていると思うと、不思議な道行きである。
横須賀といえば、海上自衛隊のお膝元。1908年に発行された『海軍割烹術参考書』を再現したカレーでまちおこしをはじめたのは、1999年のことだ。
海上自衛隊では、長い航海生活で曜日感覚を失わないよう、毎週金曜はカレーの日と決まっている。
ステイホームが叫ばれる2020年、誰が呼びかけたか「金曜カレー」がSNSに登場したとは、なんの因果だろう。外出を制限され、曜日感覚を失いがちなのは家の中とて同じ。単調な生活に句読点を打つのは、いつの時代もカレーなのだ。
金曜だけでなく、毎日カレーを作り続けるひとたちがいる。
ドキュメンタリー映画『聖者たちの食卓』(2011年/原題『Himself He Cooks』)で描かれるのは、インド北西部にあるシク教総本山ハリマンディル・サーヒブの公衆食堂だ。
毎日10万食のカレーが、500年もの長きにわたり、巡礼者にも旅行者にも等しく無償で提供されてきた。にんにくの皮をむくひと、チャパティをこねるひと、皿を洗うひと──調理に関わるひとの数は300人。もちろん無償の労働だ。
街が眠っているうちからはじまるカレー作りは、野菜も豆も、火も水も、なんだって信じられないくらい大量に投入される。
やがて門がひらき、一杯の豆カレーを求める人々が回廊を牛歩で進む。耳鳴りのような喧騒。一帯を覆い尽くす火とスパイスの圧倒的な匂い。うんざりするほどのひと、ひと、ひと!
カレーはありがたく、しかし泰然と受け取られ、満たされたひとは去る。皿は洗われ、床は掃除され、長い一日が粛々と仕舞われてゆく。
作るひとと食べるひとが、大きなうねりとなってただそこにいる。資本主義や社会保障という言葉で語れば矛盾だらけの伝統が、“分かち合う”──この一点の教義のために続いてきたのだ。
シク教には、奉仕を意味し「世話」の語源でもあるセーヴァーという教義もある。私ができるだけおいしいものを作りたいと思う心も、まさにセーヴァーだ。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)