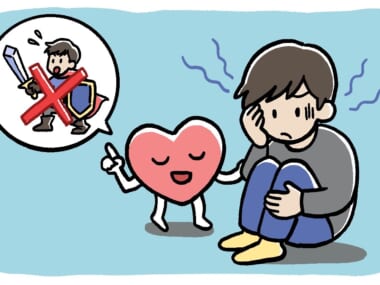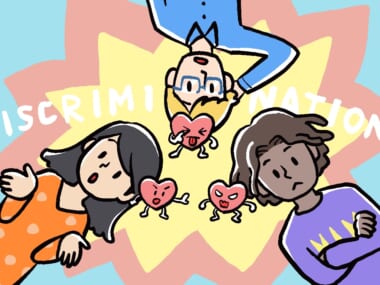2023.7.13
動物の世界にも「児童虐待」が存在する?! 子殺しの進化心理学
オスの繁殖戦略としての子殺し
動物は同種同士の殺し合いはしないという当時の常識が見直しを迫られたのは、サルの群れにおいて子殺しが確認されたことによります。京都大学の大学院生であった杉山幸丸が1962年にハヌマンラングールというオナガザルの一種で子殺しが一般的に行われている事実を発見したのです(注4)。これにより、ハヌマンラングールは子殺しを行なうサルとして一躍有名になります。
ハヌマンラングールの群れは単雄群の場合が多くあります。単雄群とは、複数のメスと子供と1匹の成体オス(アルファオス)からなる群れのことです。このアルファオスは他の群れから移動してきた個体です。杉山が観察していた群れにおいて、1962年にアルファオスの交代が起こりました。群れの外のオス達がアルファオスを攻撃して群れから追い出し、群れを乗っ取ったオス達の中で最高順位のオスが新たなアルファオスとなりました。この新しいアルファオスによる子殺しが観察されたのです。
さらに、この子殺しの発生に引き続いて注目すべき出来事が観察されました。子どもを殺されたメス達が発情を再開したのです。これにより、新アルファオスはメス達と交尾できるようになり、自分の子孫を残すことが可能になります。メス達は自分の子どもを殺したアルファオスとの交尾を受け入れたわけです。
ハヌマンラングールのこうした子殺しは、アルファオスが自分の子孫を残すための適応的な行動と考えられます。メスは基本的には一生涯同じ群れにとどまりますが、オスは成長すると生まれた群れから離れます。オスが子孫を残すためには、他の群れを乗っ取って自分がアルファオスになる必要があります。そのため、成長したオスは、アルファオスを攻撃して、群れの乗っ取りを図るわけです。
オスがアルファオスとして群れを支配できるのは平均して2年程度という短期間であるため、アルファオスは他のオスに負けて群れが乗っ取られる前に、できるだけ多くの子どもを残す必要があります。しかし、目の前のメスは前のオスの子どもを育てています。メスは育児期間中には発情しません。新アルファオスにとって、これは望ましい状況ではありません。こうした状況を一変させる手段が子殺しです。群れの乗っ取りに成功した後すぐに子どもを殺してしまうことで、メスは発情を再開します。これにより、アルファオスは自分の子どもを作るまでの期間を大きく短縮できます。このように考えることで、新たなアルファオスによる子殺しは、自分の子孫をより多く残すための適応的な行動であることが理解できます。
オスによる子殺しは、ハヌマンラングール以外にも多くの霊長類の種で生じることが確認されています(注5)。ライオンでもオスによる群れの乗っ取りのさいに、子殺しが起こります。この現象も基本的には霊長類と同じ要因によるものと考えられます。このように、今日では多くの動物で、子殺しはオスの繁殖戦略として進化してきた一般的な行動であると考えられています。
記事が続きます
霊長類の集団形成:子殺し回避の可能性
子殺しに関する興味深いトピックとして、霊長類が集団を形成する理由が食物資源の防衛、捕食者回避に加えて、子殺しの回避であるという研究があります(注6)。
ニホンザルの群れは通常、複数のオスと複数のメスとその子どもたちで構成されています。群れの大きさは10~150頭です。メスは基本的には生まれた群れに留まりますが、オスは成体になるになると別の群れに移ります。ある群れに注目したとき、その群れに常駐しているオスを「群れオス」、常駐していないオスを「群れ外オス」と呼びます。ニホンザルの群れには通常複数の群れオスがおり、群れ外オスの攻撃から子を守っているため、子殺しが発生することはまれです。しかし、群れオスが何らかの理由により常駐していない場合、群れ外オスによる子殺しが発生しうることが報告されています(注7)。
前述のハヌマンラングールでも同様の報告があります。ハヌマンラングールには、成体オスが複数いる複雄群と成体オスが1頭しかいない単雄群がありますが、単雄群よりも複雄群のほうが、子殺しの発生リスクが低いことが確認されています(注8)。子殺しが一般にオスの繁殖戦略として進化してきたことについてはすでに述べました。霊長類のメスは、それに対する対抗戦略として、オスを「群れオス」として自分の群れの仲間に取り込むことで、子どもを群れ外オスによる子殺しから守ってもらっている可能性が考えられます(注5)。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)