2020.3.27
脇役的な存在のワークキャップにも、興味深いうんちくがあるのだ
当記事は公開終了しました。
2020.3.27
当記事は公開終了しました。

グリズリー世代のバック・トゥ・ザ・ストリート

グリズリー世代のバック・トゥ・ザ・ストリート

スポーツ界イケてる顔面図鑑

クラスメイトの女子、全員好きでした

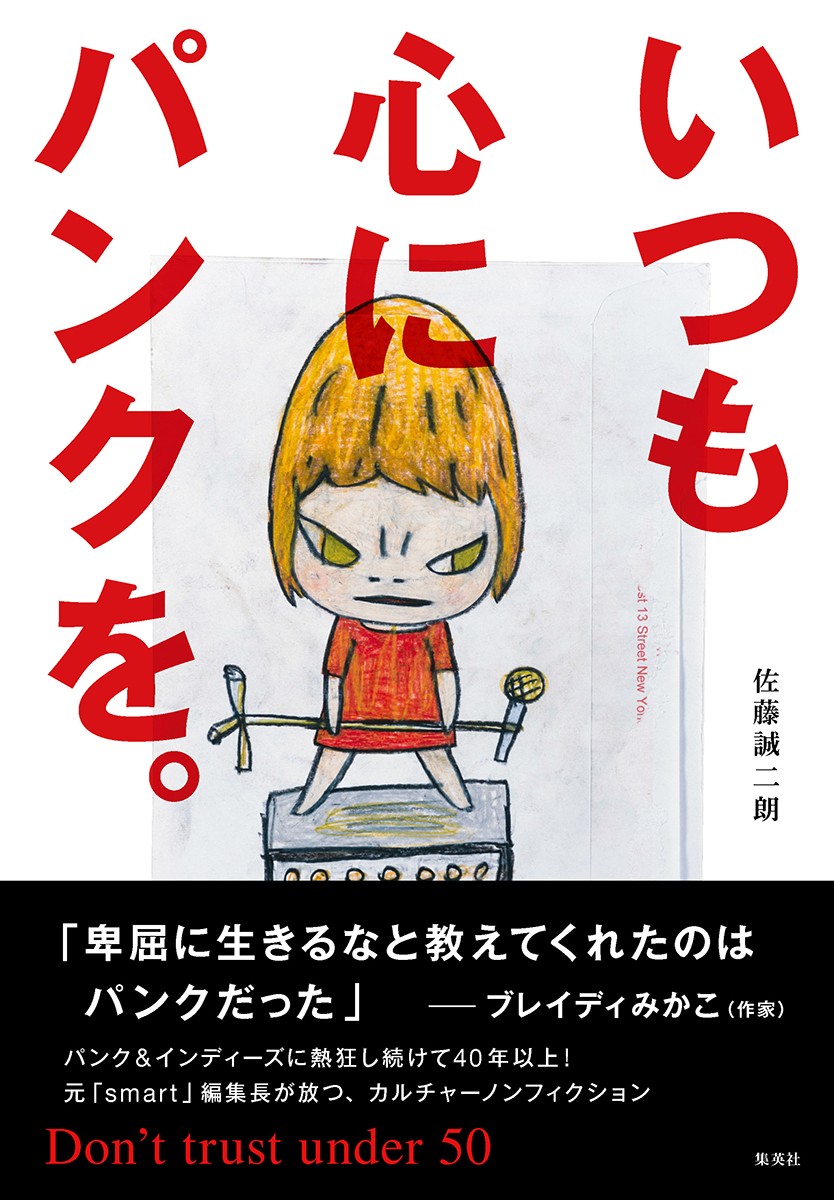
2025/8/26
NEW
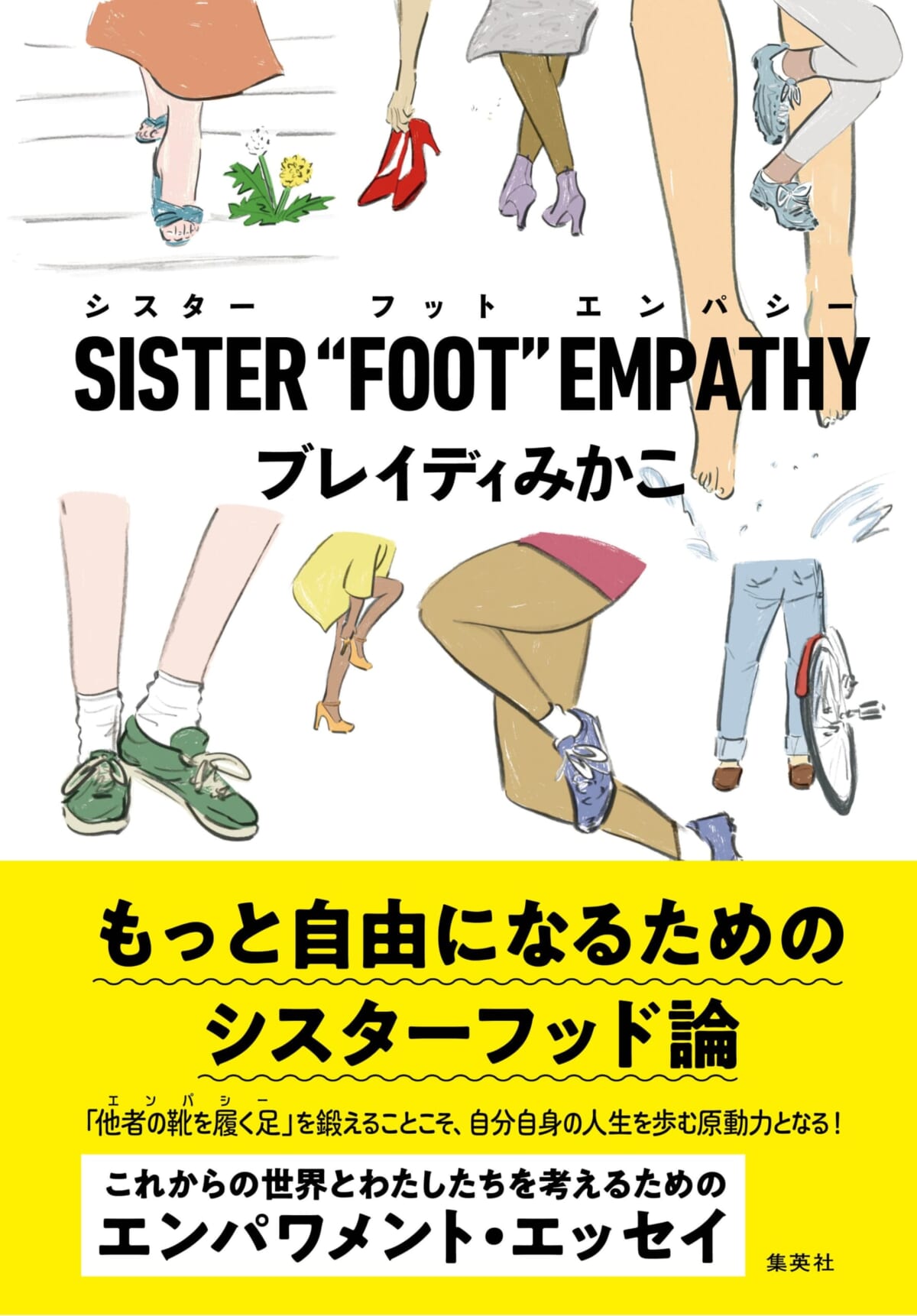
2025/6/26
NEW
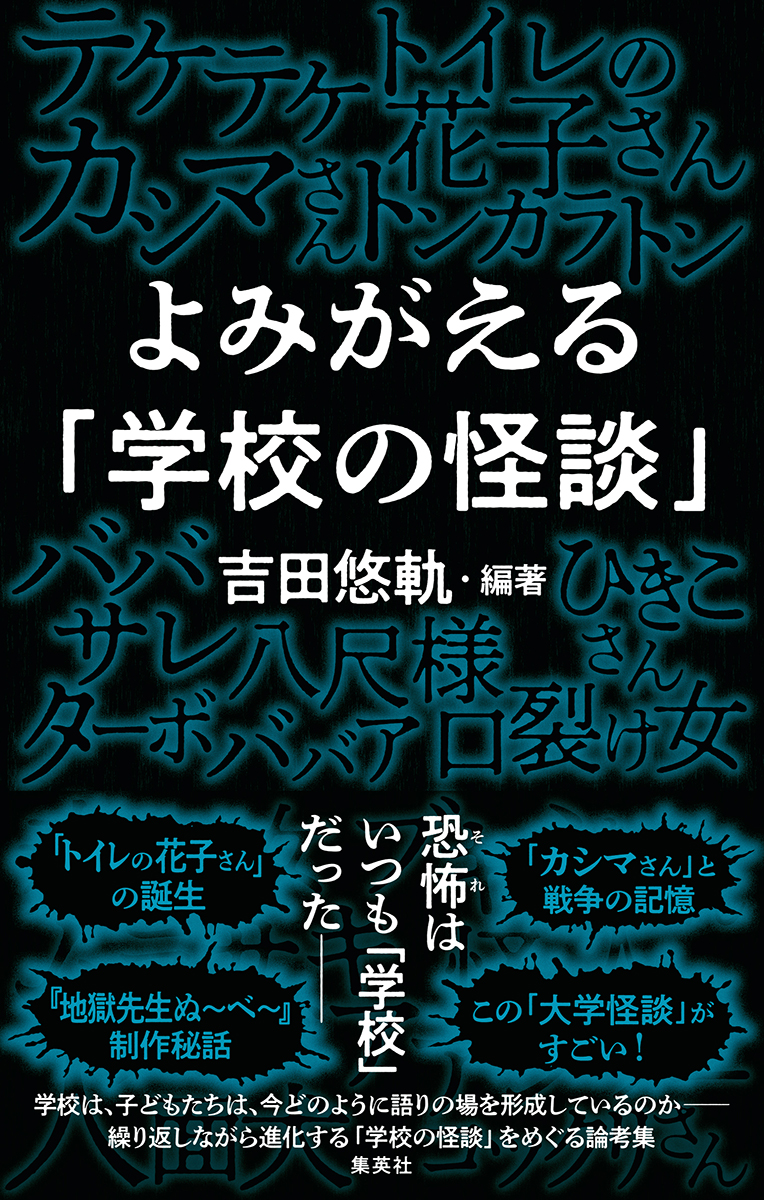
2025/7/4
NEW

2025/5/26

白兎先生は働かない

ケアとアートのダンス ~アクセシビリティのためのプロジェクト・レポート~

もう一度、君の声が聞けたなら

私たちは癒されたい 女風に行ってもいいですか?