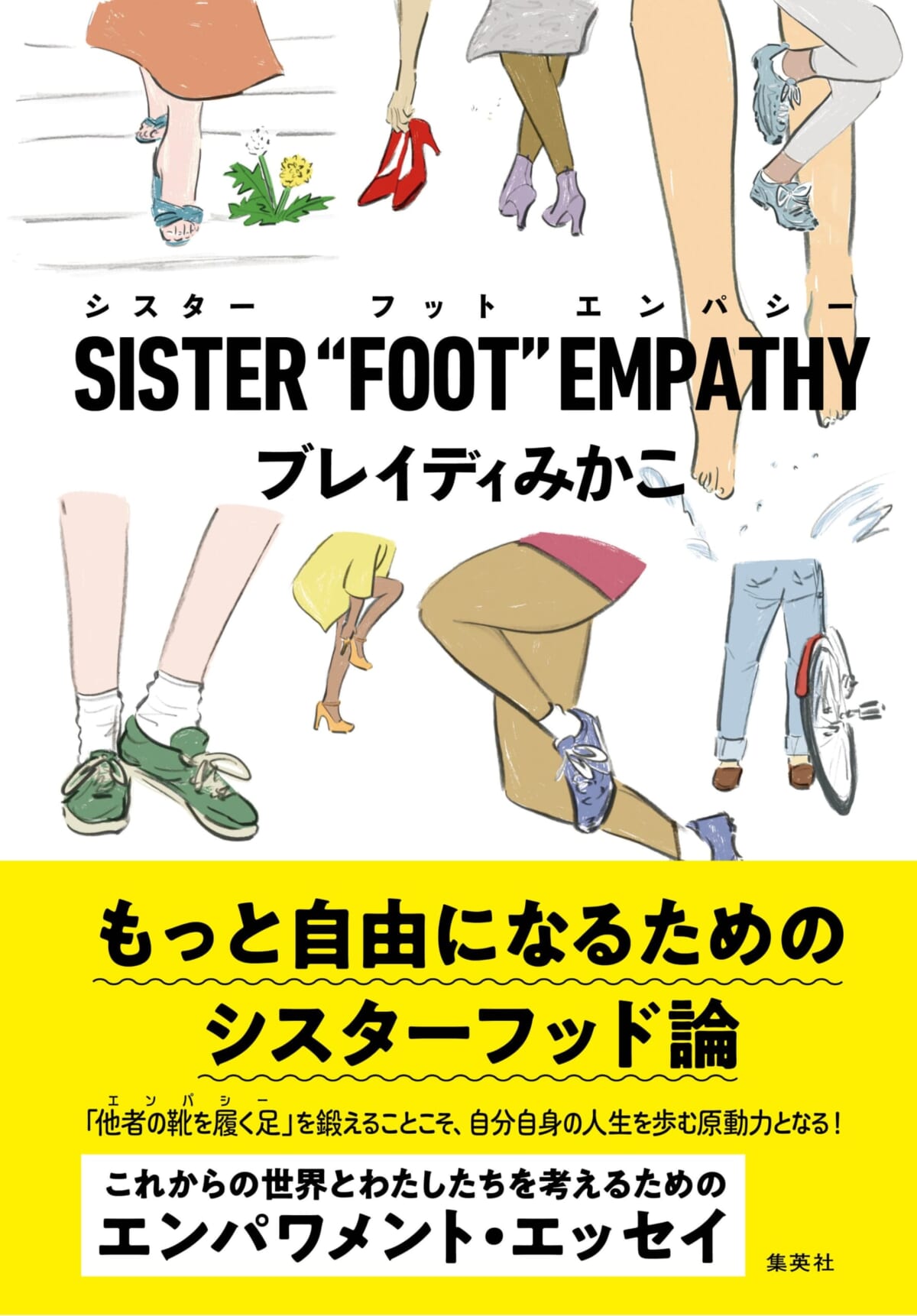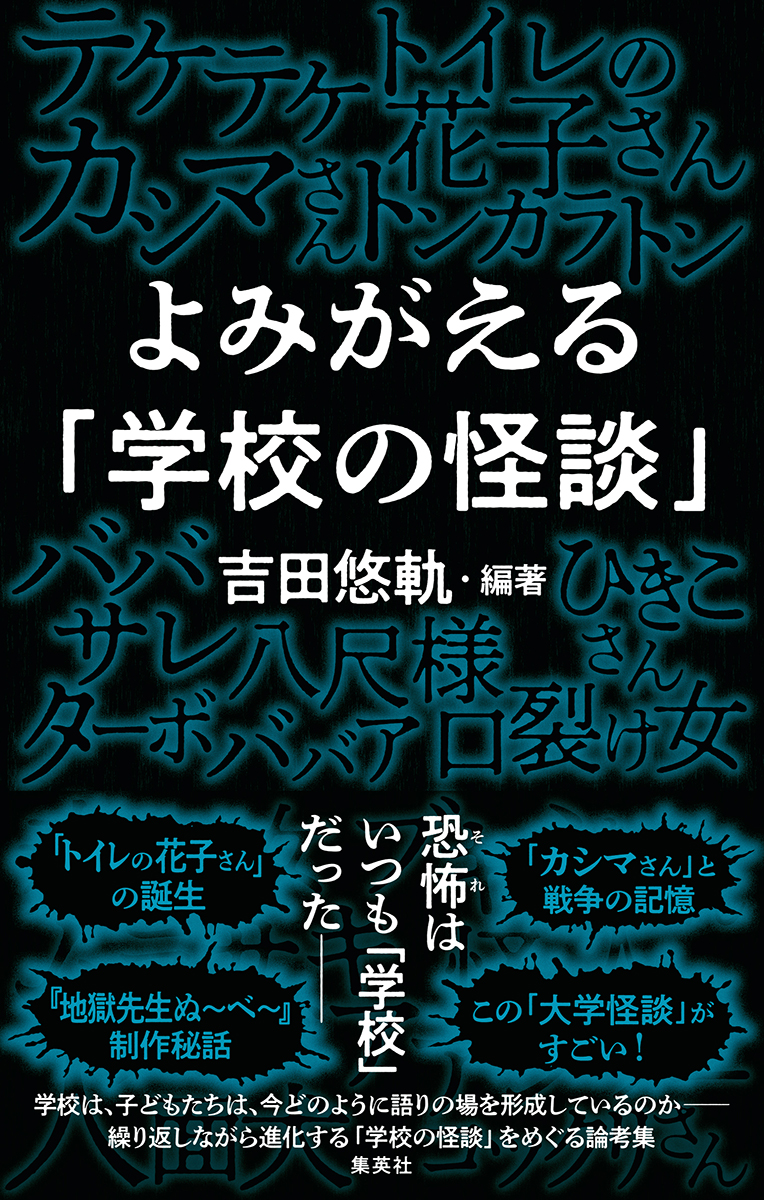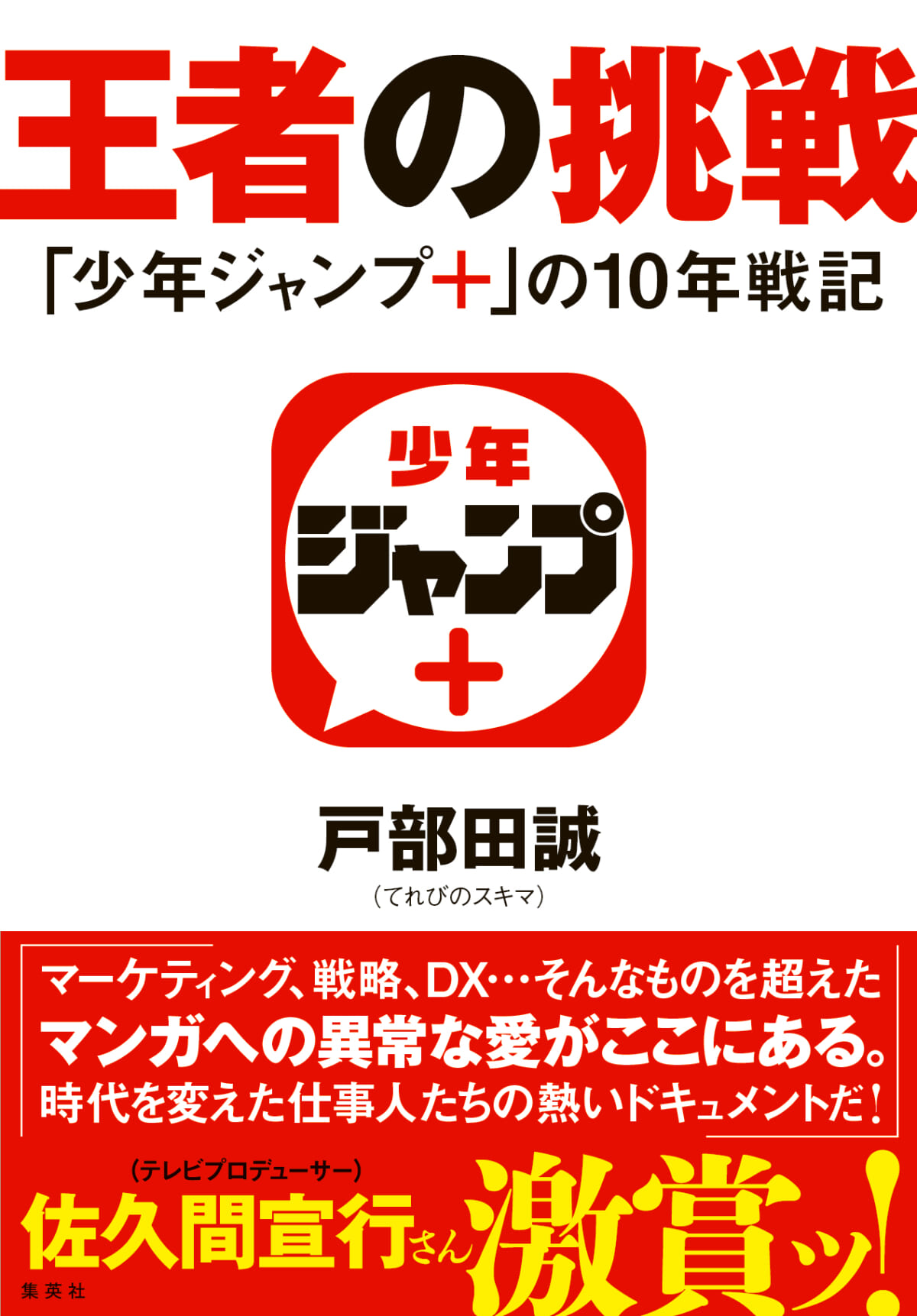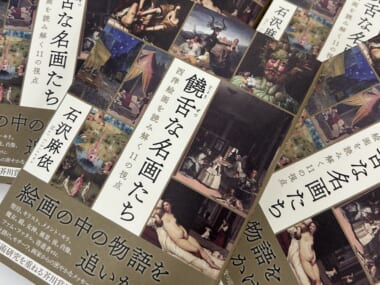2020.3.13
役員まで勤め上げた俺なのに……定年退職後の居場所は酒しかなかった男性

●70代男性・Bさんのケース
仕事一筋で生きてきた70代の男性・Bさんは、大手企業で順調に昇進し、役員まで勤め上げました。
しかし65歳で第二の人生のスタートと考え退職してみると、家に居場所はありませんでした。妻は友人らとの旅行や観劇などでしょっちゅう家を空け、Bさんと顔を合わせているときも、不機嫌な様子を隠そうともしません。それまでは役職で呼ばれ、職場で必要とされてきたのに、退職後は、社会的な地位や役割を失うだけでなく、家でも必要とされていない「ただのおじいさん」になってしまいました。
40年間仕事だけが生きがいだったBさんは、趣味を持とうと退職後に読書や語学の勉強などを始めてみましたが、どれも長続きせず、結局やることがなくなってしまい、気がつくと朝から飲酒するようになっていました。
もともと晩酌が好きだったBさんは、サラリーマン時代も時々飲みすぎることはありましたが、暴れたりすることもなく、お酒でこれといって大きな問題を起こしたことはありませんでした。
ところが、毎日のように出かけていく妻が楽しそうなのに比べると、Bさんは仕事の付き合い以外で親しい友人もなく、近所に知り合いもいません。駅前の居酒屋で一人テレビを観ながら、ビールや日本酒をあおるばかりでした。
ある日の深夜、就寝中の妻に救急病院から電話がかかってきました。Bさんが泥酔して路上で転倒し寝込んでいたところ、頭部にケガをしていたため、救急車で搬送されたというのです。驚いた妻が慌てて病院に駆けつけると、Bさんは額にできた5㎝ほどの傷からひどく出血しており、一晩入院することになりました。

翌朝、医師と話した妻は、Bさんにアルコール依存症の疑いがあると告げられました。医師は妻に、専門機関へ相談することを勧めました。それまで、Bさんのことを単なる酒好きだとばかり思っていた妻は「依存症」という言葉を聞いて、想像以上に深刻であることに初めて気づきました。妻に治療を強く勧められたBさんは、アルコール専門病院を受診することを決めました。
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)