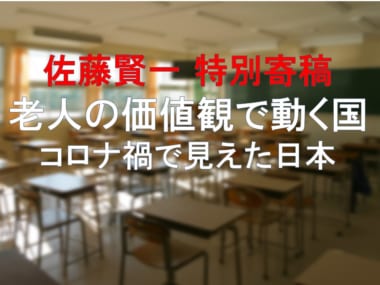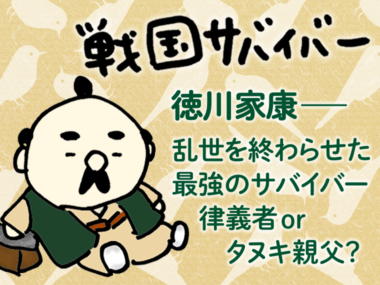2020.5.18
第4回 豆のうた
子どものころ学校から帰ると、奥のほうから秘密めいてくぐもった声が聞こえてきた。
ランドセルを置いて駆けてみれば、母や叔母たちが台所に新聞紙を敷き、うずたかく積まれた枝を囲んで豆をはずしていた。毛を生やした豆の濃密な匂いと、そこに時折まじる含み笑い。私には近寄れない空気が、確かにあった。
「なってなって、かなわん」(富山弁でたくさんできすぎて困る、の意味)
母はよくこう言ったが、それとは裏腹に、茹でたての豆は密かな楽しみだったに違いない。
そう思ったのは、自分の小さな城で、はふはふと豆をほおばる特権を私も知ったからだ。ひんやりとした床で、女たちが膝をつき合わせて豆をむしるはしゃいだ指先を、今ではうらやましく思い出す。
枝豆の嵐が去った秋、豆の世界はふたつめのクライマックスを迎える。
大豆の出番だ。
秋祭りの獅子舞がトンチキ、トンチキ、トンチキ、トンの四拍子にあわせて練り歩く背後には、黄金に乾いた十月の田畑が広がり、干された大豆の群れがあった。
ガサガサと音を立て、枯れきったように見えるその姿の中に、タンパク源としての偉大な力が蓄えられていることは、日本に暮らすひとなら誰もが知っているだろう。私の家にも、母から送られてくる大豆で仕込んだ味噌が眠り、日々の食卓をつないでいる。
大豆の枝にはそのうち雪が降りかかり、季節は閉じて深まっていく。
雪解けとともにやってくる遅い春、そして階段を駆けあがるような実りの季節と、のちに迎える成熟と発酵の冬を、豆は見事に生きる。四季を通底する豆のうたを、私はあぜ道を歩きながら五感で覚えた。
消費し尽くしたかと思える豆のうたには、まだ続きがある。
大豆のやり場に困りに困り、高温で炒って割れたものに砂糖をまぶしつけた名もなき菓子を、母が毎年送ってくれる。また豆かとボヤきたくなるが、あの疎ましいほどの豆の洪水を知らぬ子どもたちは、これが大好物なのだ。
郷里の土に実ったタンパク質を吸収し、子どもたちはどんどん大きくなっていく。まばたきをしている間に、さやから飛び出し、いずれ思いもよらぬ早さで巣立っていくだろう。私自身がそうであったように。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)