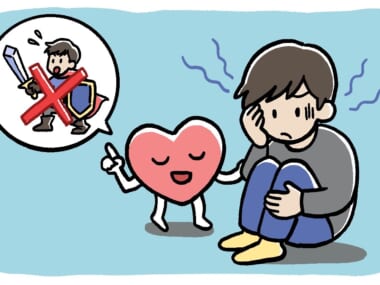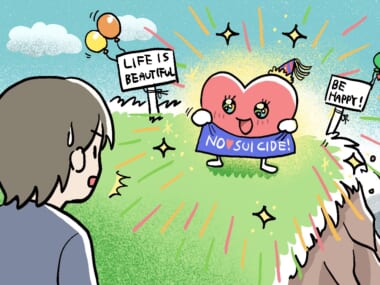2023.9.14
どのように人間は〈戦争〉をする生き物になったのか──戦争の進化心理学
マルチレベル選択による利他性の進化
記事が続きます
ヒトは高度な利他性を示すことで知られています。チンパンジーも相手を助ける行動をしますが、そうした行動は相手からの要求があって初めて生じることが実験により示されています。しかし、ヒトの利他行動はかなり自発的なもので、この点でチンパンジーとは異なります(注7)。相手から要求された場合だけではなく、特に要求がなくても相手を助けることがヒトでは普通です。ヒトが進化の過程でこのような高度な利他性を獲得した理由が戦争と関係しているという説があるので、紹介します。
哲学者のエリオット・ソーバーと進化生物学者のデイヴィッド・ウィルソンは1998年出版の共著『Unto Others』のなかで、マルチレベル選択によって利他性が進化しうるというアイデア(マルチレベル選択説)を提唱しました(注8)。自然選択は、従来考えられてきたように個体レベルで働くだけではなく、状況によっては集団レベルでも働くことがあり、そうした集団レベルの自然選択によってヒトの利他性が進化したというのです(注9)。
集団レベルの自然選択が働きうる状況とはどのようなものなのでしょう? ソーバーとウィルソンは以下のような例を挙げています。複数の小規模な集団が存在し、かつ、集団内の交流は活発で集団内の個体同士は性質がよく似ていると仮定します。そのうえで、集団は互いに隔離されていることから集団間の違いは大きくなるとします。こうした状況において利他行動に寄与する遺伝子の数の推移を考えてみましょう。集団の内部では自然選択の働きにより、利他行動に寄与する遺伝子は減少する可能性があります。なぜなら、利他行動に寄与する遺伝子は、その遺伝子をもつ個体の負担(コスト)が利他行動のため増大し、生存や繁殖に不利となりうるからです。
その一方で、集団間の比較においては、利他的な個体が多い集団は個体同士が協力することで生存率が高くなるため、利他的な個体が少ない集団よりも生き残りやすく、結果として利他的な個体が多い集団の割合が高まっていくと考えられます。こうして、複数の集団全体をトータルで考えると、利他行動に寄与する遺伝子は存続できるという予想が導かれます。ソーバーとウィルソンはこうした現象を「マルチレベル選択」と呼びました。
自民族中心主義や内集団バイアスが強まると、自分の所属集団(内集団)のメンバーには好意的であるものの、自分が所属していない集団(外集団)のメンバーには敵対心をもつという状況になり得ます。経済学者のギンタスとボウルズは、この状況を「偏狭な利他主義」と呼びました(注10)。うえで述べたように、マルチレベル選択が働くには、各集団の内部では互いに似ている一方で、集団間の違いは大きくなっている必要があります。ギンタスとボウルズは、食物分配や一夫一妻制などの社会制度が生まれることで集団内のメンバー間の格差が小さくなり、それにより集団内の団結が促進され、そこにマルチレベル選択が働くことで、食物分配や一夫一妻制などの社会制度を有する集団がそうでない集団よりも多く生き残り、複数の集団全体でみると、それらの社会制度がより強化される、という説を提唱しました(注11)。
こうしたマルチレベル選択に必要となる集団間の大きな違いを生み出す一つの原因が、集団間の対立すなわち戦争と考えられます。利他性によって団結している集団が利己主義者の集団に戦争で勝てば、マルチレベル選択の働きは強まります。こうして、利他性によって集団内で団結しながらも外集団のメンバーには敵対心をもつという偏狭な利他主義が、戦争を通じることで集団の生き残りにとって有利となり、マルチレベル選択で増加する、という可能性が生じます。ヒトの祖先社会においては実際に頻繁に戦争が発生していて、それが偏狭な利他主義を生みだしたとギンタスとボウルズは述べています。
ギンタスとボウルズの仮説の妥当性について、データに基づいた確実な結論を得ることは難しいでしょう。しかし、人類の祖先は過去に過酷な状況下における戦争の激化を経験しており、それによりヒトの偏狭な利他主義が進化したという説(注12)があるので紹介します。その説では、人類の祖先は10数万年前の地球規模の寒冷化の影響で当時個体数を大きく減少させたとして、過酷な状況においては貝類などの海洋沿岸資源が限られた食料として特に重要になり、それらの資源の確保を巡るテリトリー防衛のために集団間対立(戦争)が激化し、戦争に有利となる偏狭な利他主義が進化したと主張しています。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)