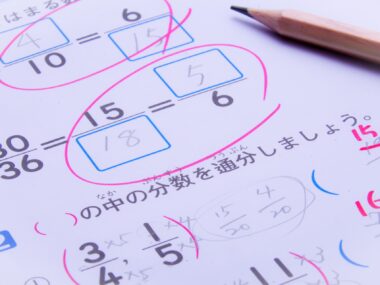2024.5.20
加害と依存【逃げる技術!第15回】ギャンブル依存症と似ている?
記事が続きます
被害を思い出し、自分に落ち度があったのか?と反芻するうちに
この1年ほど、ずっと自分の身に起こったモラハラについて反芻してきました。最初は、自分がされたこと、子ども達がされたことを言語化するのに精いっぱいでした。わたしに落ち度があったのではないか、と常に思いましたし、いまも無心に皿を洗っているときや自転車に乗っているときなどは、ずっと考えてしまいます。わたしが間違えたのではないか、夫の加虐性を引き出してモンスターにしてしまったのは自分なのでは、と。
その一方で、気持ちが整理されていくうちに、夫の心理のメカニズムにも想像がおよぶようになりました。毎日子どもの前でわたしの悪口をいい、室内でわざと転ばせ、「一生かけて恩返ししてもらうからな」とニヤニヤと宣言していた理由を考えれば考えるほど、「あれは楽しかったのではないか? 夫にとっては遊びの一種だったのではないか?」とも思い至るようになりました。残念なことですが、稀に、ペットをいじめて遊んでいるつもりの人が いますよね。それと似たようなことのような気がします。
そしていまは、DV・モラハラはする側にとっては「加害行為への依存や嗜癖」なのかもしれない、と思い始めています。夫はもはや「加害の形」でしか親密なコミュニケーションが取れなくなってしまっていたように思うのです。
夫はわたしにも子どもにも意地悪をすると、上機嫌になりました。にわかに血色がよくなり、目がキラキラと輝き、アッハッハと笑い、上から見下ろします。イキイキしてとても楽しそうでした。あれはアドレナリンが分泌されていたのではないかと思います。目に光が宿るのは、瞳孔が開くためでしょう。アドレナリンレベルが上昇すると、頰の毛細血管が拡張し、顔を紅潮させることが知られています。
記事が続きます

記事が続きます
DV・モラハラは依存や嗜癖なのではないだろうか?
そう思って検索すると、加害を依存や嗜癖ととらえるアプローチ手法があるようでした。いくつか例示します。
例えば鳥取県依存症支援拠点機関 渡辺病院のウェブサイトには「依存症(アディクション)とは、人生に飢えや渇き(満たされなさ、空虚感)を感じる人がそれを埋めようとする行為」とあり、依存の対象を大別して「1、物質依存」「2、プロセス(行動)依存」「3、関係依存」としています。「3、関係依存 」にはアルコール依存症やDVにおける「共依存」が含まれます。
また亀有メンタルクリニックではDVや学校でのいじめのことを「関係嗜癖」と呼んでいます 。
国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センターは「薬物やアルコールへの依存、配偶者等への日常化した暴力(DV)や幼児・児童・高齢者等への虐待、ストーカーや痴漢等の性問題行動、病的なギャンブリング、クレプトマニア(窃盗癖)や摂食障害、インターネットや携帯電話への依存といったアディクション(嗜癖・嗜虐行動)の背景には、”孤立”があります」と書いています。
いじめやDVを「関係依存」「関係嗜癖」などのカテゴリーに入れている臨床機関もあります。
ギャンブル依存症患者とDV加害者の類似点に驚く
2024年3月、メジャーリーグの大谷翔平選手の専属通訳だった水原一平さんが、ギャンブルのために大谷選手から巨額の資金を横領していたというニュースが流れました。これをきっかけに「ギャンブル依存症」という言葉がニュースで流れ、それに詳しい医師や当事者家族の話を見聞きして、わたしは驚きました。あれっ、これはDV加害者とよく似ているな、と。
以下は、独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターが挙げるギャンブル依存症の特徴の一部です。
・ギャンブルを減らそう、やめようとしてもうまくいかない
・ギャンブルをしないと落ち着かない
この「ギャンブル」というワードを「いじめ」や「モラハラ」に入れ替えると、夫の行動によくあてはまっていたと感じます。加害の程度や頻度が次第にエスカレートし、ストップできず、毎日のように加害行為(ぶつかる、文句をいう、行動や金銭の使用を厳しく管理する、命令する、叱責する、お前は無価値だというなど)をしていないと落ち着かないように彼は見えました。
DV加害者の「家族は自分の命令に従うべき」という信念
「DVも依存の一種」だとすれば、被害者が自分ひとりで事態を打開しようとしても難しいのも納得がいきます。アルコール依存もギャンブル依存も専門の医師がいて回復のための施設もあるのですから。
家の中でDVの加害者と被害者が一緒にいること自体が、どうしてもDVを生んでしまいます。アルコール依存症の患者の前にはお酒を置かないのと同じで、まず対象物である被害者と加害者を物理的に離す必要があるでしょう。
DVやモラハラの加害者は誤った信念を持っています。「家族には、自分の命令に従わせないといけない/家族は自分の命令に従うべき」という価値観です。また、それでいて「自分はDVなどしていない。自分は家族に当然のことを教えているだけ」「DVをする人間はとんでもないやつだ」くらいに考えています。まず自分が加害者であるという事実を本人が認められるようにならないと、行動も修正できないのですが、これをとても困難なことだと感じています。
加害者は「被害者は自分に従うべき」という誤った信念を抱いています。
また、おそらく加害の根本には、恐怖や劣等感、自信の欠落、愛情への飢餓感などがあるように感じます。でも、被害者がひとりでそれをケアしようとしても、穴の空いた桶に水を汲み入れるようなもので、つぎこんでも、つぎこんでも漏れていってしまうのです。そのうちに被害者のほうはエネルギーが枯渇してしまいます(わたしは結婚生活中につねに何かしらの身体症状が出ており、いくつもの病気をしました)。
身内だけでなんとかしようとしても、加害者はすでに「家族への嫌がらせ、意地悪、暴力、命令」を常にしていないと気がおさまらなくなっていますから、一緒にいればいるほど、被害者も家族(わたしの場合は子ども達)も、絶えず傷つけられる事態になってしまいます。そしてどんどん力が奪われていってしまうのです。
加害者からまず離れることの大切さ
ですからやはり加害を止めるには、加害者から離れることが第一ステップだと思います。ターゲットがいなくなれば、物理的に加害はできなくなるからです。
それでもしつこくメールを送ってきたり、通学路で待ち伏せしたりといった相手からの接近はありますが、それらは弁護士から連絡してもらう、警察から注意してもらうといった対処によって、ひとつずつ解決していくほかありません。
加害行為を止めるためにも、被害者が加害者から離れることが重要。
加害者が家を出るか? それとも被害者が出るか?
では、どうやって加害者から距離をとればよいのでしょうか。
もちろん、話し合いで加害者がまず家を出ていってくれれば、そちらのほうがベターです。なぜなら、加害者が自ら出ていくというのは、過去の自分の行動をいくらかでも自覚し、認めているということだからです。少なくとも「自分と被害者との人間関係が壊れてしまっていることは理解できている」といえます。
まだ数は少ないのですが、DV加害者更生支援団体というものがあります。「更生」ではなく「教育」と呼ぶ組織もあります。DV加害者が集まって、講座を受けたり、互いに自己開示しあったりして、自分の過去の言動を見つめ直し、DVを行なってしまう価値観を修正していくための場です。
ある支援団体の代表の方に相談したことがあるのですが、「自分のした行為を認められるかどうか」、ここが加害者の更生のスタート地点になるのだそうです。そしてわたしの夫については「彼はまだスタート地点に立てていませんね」といわれました。それから1年以上が経ちましたが、夫はいまも変わっていないようにわたしは感じています。
いま、日本にある加害者更生の講座やセッションは、カリフォルニア発のメソッドをベースにした自助会形式のものが多いようです。まだまだ 効果検証も十分とはいえないと聞きます。並行して、他にもさまざまなアプローチが増えていくことを願います。
DV加害者が自分のしたことを認められるかどうか。そこが更生のスタート地点。
実は、わたしが最初に家を出たときには「子ども達とわたしが家に残りたい。子どもを育てるにはある程度の広さも必要だし、子ども達もこの家に住み続けたいといっている。だから、あなたに家を出ていってほしい。ただ、あなたが父親であることは変わらない。子どもとは週末に外で遊んだりしましょう。これからは夫婦ではなく、子どもを一緒に育てる新しい関係に移りたい」と弁護士を通じて書面で提案しているのです。
しかし、残念ながら夫は過去のDVを認めることはできず、反対に「もし俺に出ていってほしいのであれば、こうしろ、ああしろ」と、次々ととても呑めないような条件をどんどん出すのでした。
やむなくワンルームマンションに母子3人で引っ越し
第13回でご紹介したように、警察を呼ぶような事態もあり、危険を感じていたので、しかたなくわたしと子ども達は最低限の荷物を持って小さなワンルームマンションに引っ越しました。夫はいまもずっとひとりで、ファミリー向けの広さのあるマンションに住んでいます。
ワンルームマンションは狭く、子ども達の学ぶ環境、遊ぶ環境はとても悪化しました。テレビを観るにもどうしても近くから。キッチンの調理スペースも幅が20cmあるかないかで、まな板も置けません。冷蔵庫も単身者向けのものしか置けないので、容量が小さく、子ども達は食べざかりですが食材のストックも困難です。
狭いので、誰かが風邪をひいても隔離もできず、かならず全員にうつってしまいます。2023年の冬は、アデノウイルス、溶連菌、インフルエンザ、ウイルス性胃腸炎と、毎月何かしらに全員でかかっていました。呼べる助けもなく、その度につらい思いをしました。
子どもも状況を理解し、心情が変わっていく
家出当初は「お父さんとは一緒には住めないけれど、外で遊んだり、ボードゲームをするのならいいよ」と話していた子どもたちですが、「どうしてわたしたちは悪いことをしていないのに元のおうちに住めないの?」と疑問なようで、すっかり父親のことが嫌になってしまったようです(今後の夫の変化によっては変わるかもしれませんし、そうあってほしいものですが)。
いまはなんとか無理に説得して面会交流に連れていっても、相手の顔を見ただけでキャーと走って逃げるような状態になってしまいました。
わたしは子ども達を連れて家を出るまで、何度も「子どもから父親を奪うことになるのでは」と逡巡しました。ですが、夫の言動がエスカレートしていった最後の数年間を何度も反芻して、やはり家を出るしかなかった、といまは考えています。もちろん、児童相談所や自治体、子どもの学校の校長先生などから強く別居を勧められたという外的要因も大きかったです。
あれ以上、夫がわたしと子どもを傷つけつづけていたら、きっと誰かが潰れていただろうと思うのです。
参考文献:信田さよ子『暴力とアディクション』(青土社)
当連載は毎月第1、第3月曜更新です。次回は6月3日(月)公開予定です。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)