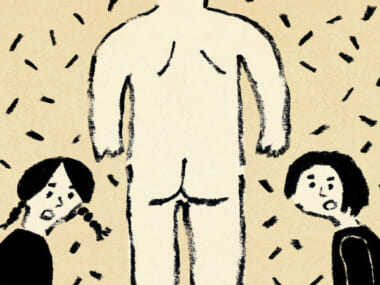2022.9.29
注文したのは私……「俗」が聖なる場面に放たれるとき 第1回 絵画空間に置かれた「自分」—寄進者の肖像
「見る」「見られる」の関係性
聖なる空間への立会いを表した興味深い作品に、ハンス・メムリンクの〈マールテン・ファン・ニーウェンホーフェの二連画〉(一四八七年)がある。二つのパネルから成るこの形式は、聖なる場面と寄進者という宗教画から、夫婦肖像画まで広く用いられていた。メムリンクの二連画の場合、左パネルに正面を向いた聖母子が、右パネルに寄進者である後のブリュージュ市長マールテン・ファン・ニーウェンホーフェが四分の三正面観で描かれている。当時、正面からの姿はキリストや聖母など聖なる人物にのみ採用され、王侯貴族や市民の肖像は斜め前方を向いた姿で表すのが一般的であった。また、聖母と幼児キリストの間で手渡される果実は、絵画伝統的にキリストの物語と結びつくものとなっている。ここに描かれる林檎は、アダムとエヴァによる原罪を象徴するだけではなく、やがて磔刑という形でこれを贖わなくてはならない救い主の運命をも示唆するものだった。
一見するとこの二連画もまた、〈宰相ロランの聖母〉のように聖人の仲介がないものと映るが、両パネルのステンドグラスに聖人像が取り込まれている。聖母子の背後、右側の窓には竜退治する聖ゲオルギウスと幼子キリストを担いで川を渡る聖クリストフォロスが、ファン・ニーウェンホーフェの右側に位置するステンドグラスには、聖マルティヌスの姿が見られる。身体の不自由な貧者に、切り取ったマントを施すその騎士は、マールテンという名が示すように寄進者の守護聖人でもあるのだ。
〈メロードの祭壇画〉と同じく、メムリンクの作品でも二枚のパネルが聖と俗を隔てているようだが、聖母の背後の凸面鏡という仕掛けが、鑑賞者側からは見えない絵画空間の様子を物語っている。そこに映る聖母の後ろ姿と、祈りを捧げる寄進者の横向きの姿。この小さな鏡像によって、聖母子と寄進者は同じ空間と時間の流れの中にあることが明らかとなる。さらに、鏡に映るという客観的な事実から、聖なる存在はファン・ニーウェンホーフェの幻視ではなく、彼の生きる現実に顕在しているとも考えられるのではないだろうか。人物の位置や空間配置など見えないものを明らかにする凸面鏡は、ヤン・ファン・エイクの〈アルノルフィーニ夫妻の肖像〉(一四三四年)から影響を受けたモチーフだと考えられる。
![ハンス・メムリンク<マールティン・ファン・ニーウェンホーフェの二連祭壇画>1487年 フランス、パリ [ルーヴル美術館]](https://yomitai.jp/wp-content/uploads/2022/09/01-ishizawa-03.png)
![ヤン・ファン・エイク<アルノルフィーニ夫妻の肖像>1434年 イギリス、ロンドン [ナショナルギャラリー]](https://yomitai.jp/wp-content/uploads/2022/09/8408270bc25009554a4ae7090a24fadc-scaled-e1663232315294.jpg)
このように、聖と俗の空間性を巧みに表してきた初期ネーデルラント絵画に対し、寄進者など現世の人物の肖像性が強調される形式もまた生まれてくる。そこでは、画家の生きた時代の人物が、聖なる場面に溶け込むように描かれているのだ。例えば、ニュルンベルクで活躍したアルブレヒト・デューラーの手になる一五〇六年作〈ロザリオの祝祭〉がその一例だろう。この作品は、二度目のヴェネツィア滞在中(一五〇五—〇七年)、ドイツ人商人たちによって聖ドミニコ会と結びつきのあるロザリオ同信会のために制作を依頼され、サン・バルトロメオ大聖堂に奉納された。豊かな自然を背景とした絵画世界は、鮮やかな色彩が祝祭的な雰囲気を強めている。中央の玉座に腰を下ろす聖母子、その左隣に佇む聖ドミニコ、そして宙を舞う四人の天使たちが、跪く人々に薔薇の冠を祝福するように授けている。聖母が冠を被せている右側の人物は、ハプスブルク家の神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン一世である。彼は芸術の保護者としても名高く、デューラーのパトロンでもあった。その反対側で、幼児キリストが薔薇冠を与えようとしているのが、時の教皇ユリウス二世である。玉座をはさんで跪く聖俗の権力者の背後には、注文主にして寄進者でもある同時代のドイツ人が並び、集団肖像画としても機能していた。
この作品の興味深い点は、画家自身の自画像も紛れ込んでいることである。画面の右後方、ニュルンベルクの著名な人文主義者ヴィリバルト・ピルクハイマーが黒い外衣に帽子姿で佇むその隣に、画家デューラーの姿が見られる。その手が掲げるのは、この作品の制作者であることを記した紙片だった。寄進者や著名な人物の肖像が聖なる場面に立ち会うのに対し、画面の外に眼差しを向ける画家は、絵画世界と鑑賞者のいる現実の仲介者でもあるのだ。同様の構成の作品として、イタリア・ルネサンスの画家サンドロ・ボッティチェリの〈ラーマ家の東方三博士の礼拝〉(一四七五年頃)が挙げられる。フィレンツェの両替商組合の仲買人グァスパッレ・ラーマが依頼したこの作品は、キリストの誕生を祝いに訪れた東方三博士という聖書主題を扱いつつも、メディチ家を中心とするフィレンツェの著名人の集団肖像画という性質も帯びていた。特にコジモ・デ・メディチとその息子のピエロとジョヴァンニは、、聖書内人物である三博士に擬せられており、聖書の世界に浸透している。ボッティチェリ自身もまた、パトロンであるメディチ家との関係を示すかのように立ち会っているが、その顔は聖なる場面ではなく、画面の外の鑑賞者のいる方へと向けられているのだ。つまり、聖なる物語と世俗の断片が入り交じるこの絵画は、当時の権力者を描いた公的な肖像画でもあった。
![アルブレヒト・デューラー<ロザリオの祝祭>1506年 チェコ、プラハ [国立美術館]](https://yomitai.jp/wp-content/uploads/2022/09/20e94c08a5cc0c77d93f26f3b11a0a91.jpg)

![ボッティチェリ<ラーマ家の東方三博士の礼拝>1475年 イタリア、フェレンツェ [ウフィッツイ美術館]](https://yomitai.jp/wp-content/uploads/2022/09/01-ishizawa-05.png)
聖書場面や聖なる人物を描いた宗教画は、主題のために一見すると隔たりがあるようだが、常に鑑賞者のいる現実へと眼差しが投げかけてもいる。観る者もまた、自分のいる場所や時代との繋がりを見出すことで、絵画内に「現実感」が紡ぎ出されてゆくのだ。その「見る」と「見られる」という関係を生み出すことに、描かれた聖と俗もまた大きな役割を担っていたのだろう。断絶ではなく、延長としての聖なる世界。しかし、その均衡は画家のみならず、注文主によっても異なってくる。日常の顔をした聖の姿もあれば、聖が世俗という現実の鏡像ともなり、その移ろう在り方こそが二つの空間を捉えた肖像となるのだろう。
※1 人物名、絵画タイトルは『西洋美術の歴史 4ルネサンスⅠ』(中央公論新社/二〇一六年)『西洋美術の歴史 5ルネサンスⅡ』(中央公論新社/二〇一七年)を参考にしています。
※2 初期ネーデルランド絵画と初期フランドル絵画は、十五‐十六世紀のフランドル地方の画家たちによって制作された作品を表し、同じものを指しますが、文中では「初期ネーデルランド絵画」で統一しています。
編集協力/中嶋美保
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)