
2022.9.2
バブル世代「会社の妖精さん」の行く末は 第3回 五十代からの「楢山」探し
当記事は公開終了しました。

2022.9.2
当記事は公開終了しました。
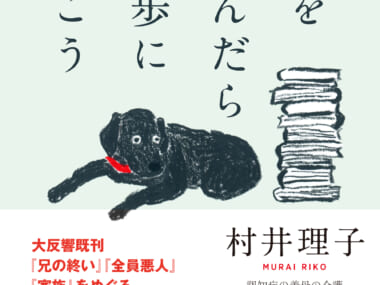

六十路通過道中
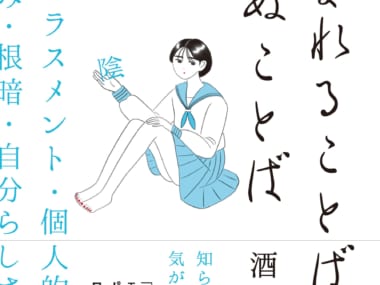

おもいっきり東京ライフ

実母と義母
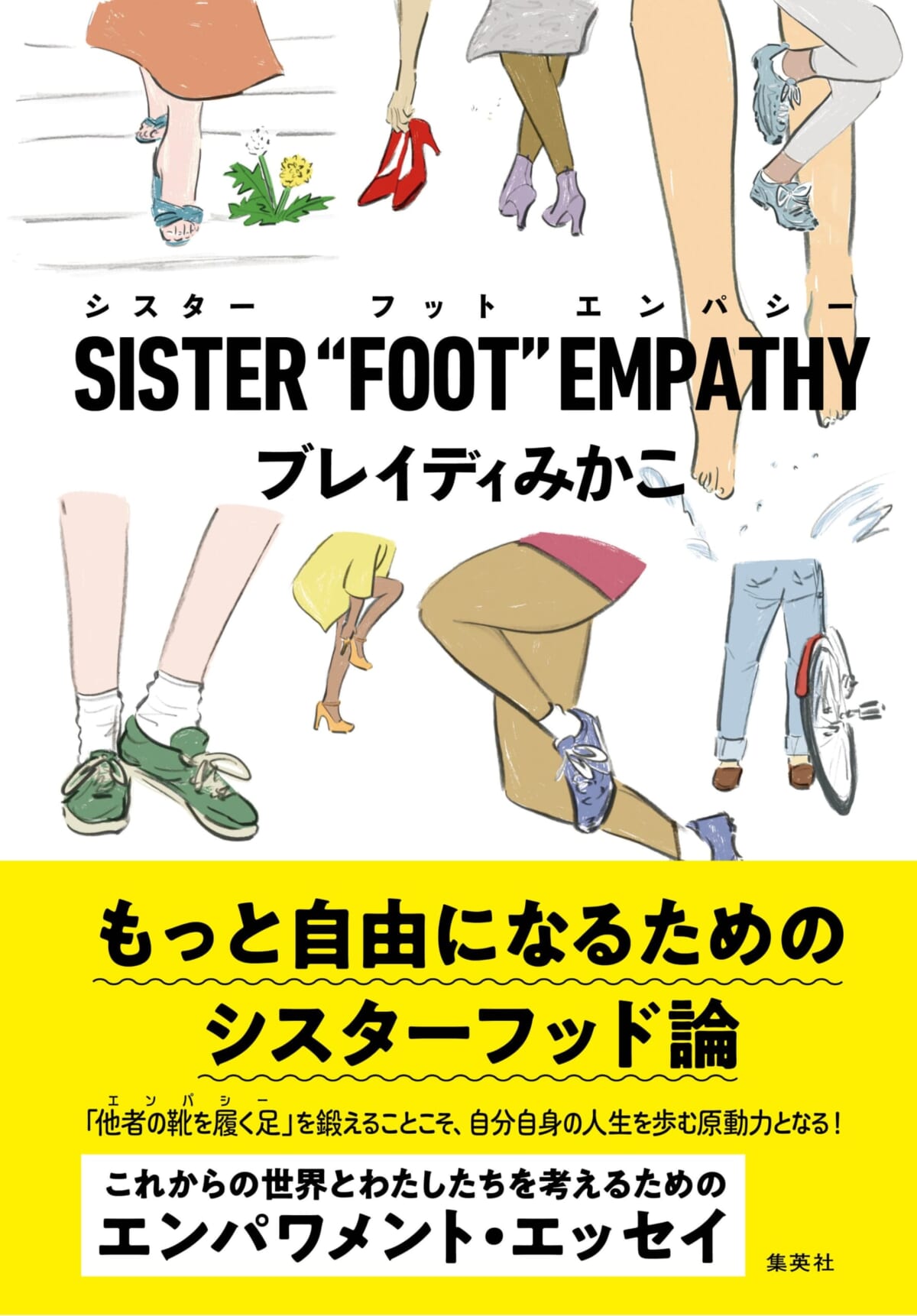
2025/6/26
NEW
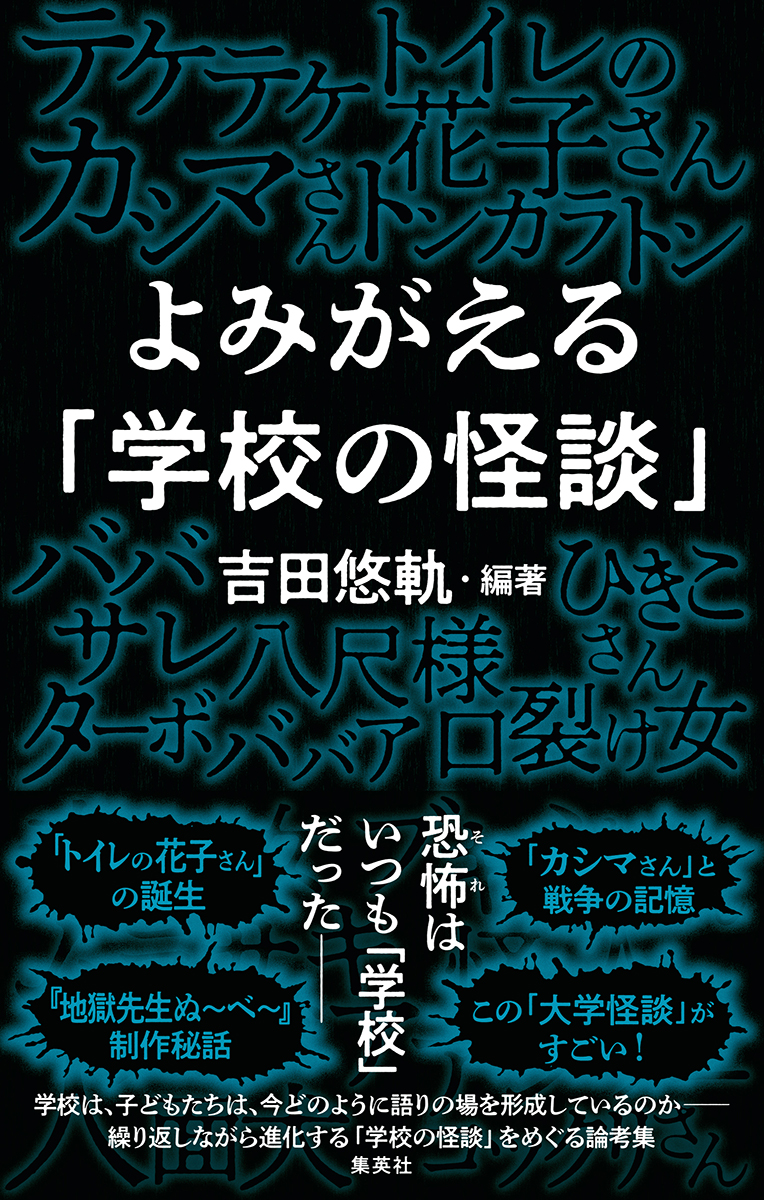
2025/7/4
NEW

2025/5/26
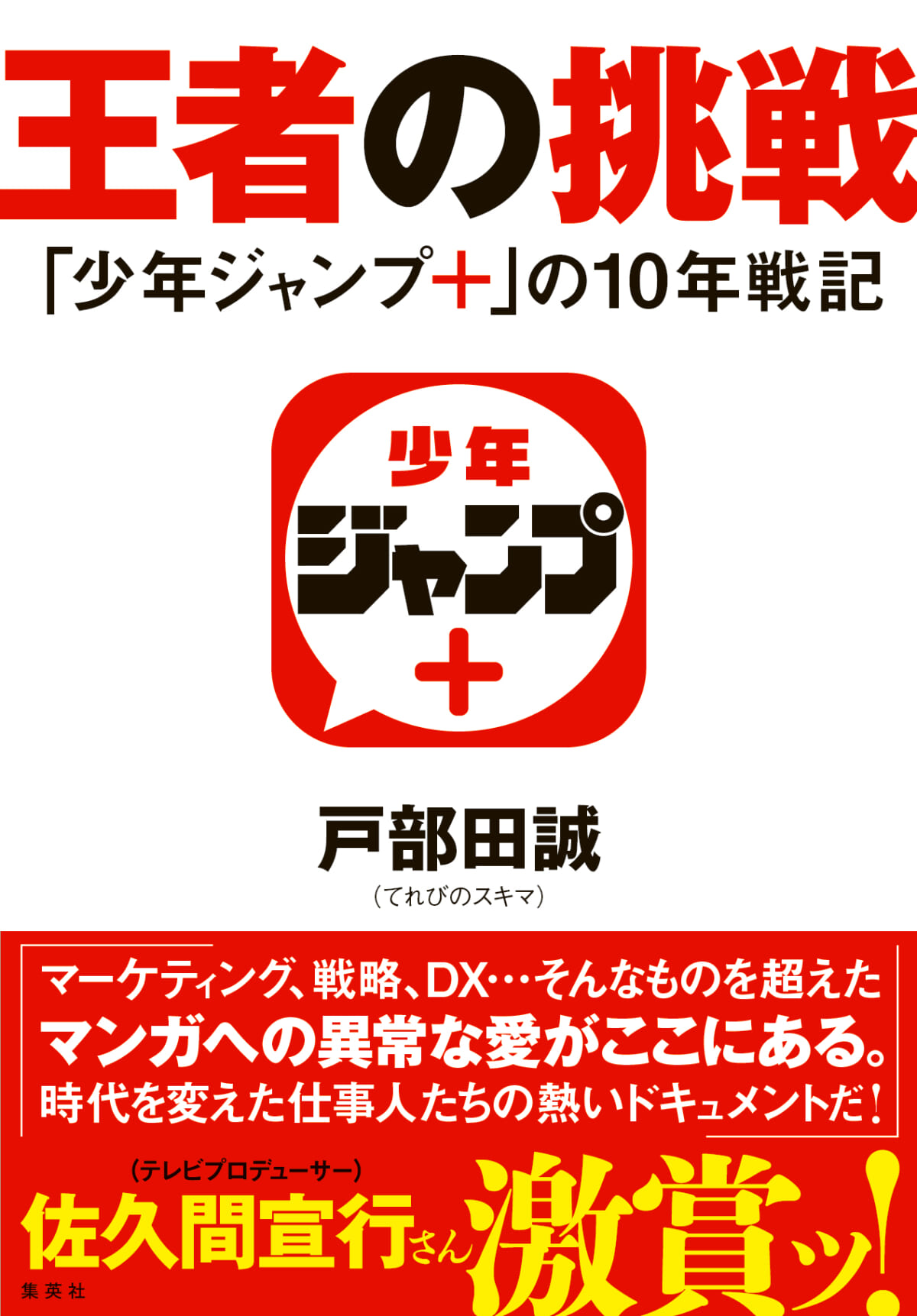
2025/5/9

もう一度、君の声が聞けたなら

私たちは癒されたい 女風に行ってもいいですか?

白兎先生は働かない
