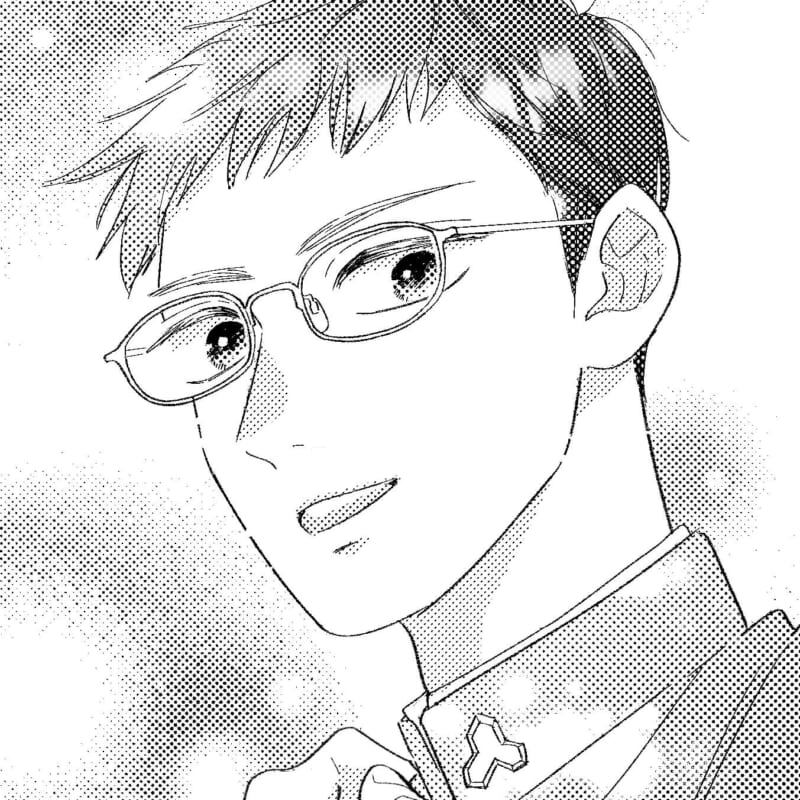2023.6.15
「田舎の神童」の作り方【学歴狂の詩 無料公開中!】
京大卒エリートから転落した奇才が放つ、笑いと狂気の学歴ノンフィクション。
朝日新聞やCREAで取り上げられ話題沸騰中の『学歴狂の詩』の冒頭を、刊行記念として無料公開いたします!
この機会にぜひお読みください。
☆連載をまとめた書籍の詳細はこちらから。

学歴に取り憑かれてしまった経緯
「佐川恭一」という名前を聞いてピンとくる方はよほどの物好きだろうから、簡単に自己紹介しておくと、私は京都大学を出ている。滋賀出身で、小説を書くこともある。とりあえずそれだけ知っておいてもらえれば十分である。初回は今後の連載を楽しんでいただく下準備として、私が学歴に取り憑かれてしまった経緯について紹介しておきたい。
さて、京大を卒業している私だが、そもそもは京大などというワードすら出てこない世界(滋賀の田舎町)でハナタレ小僧をやっていただけだった。父は高卒、母は短大卒。父はかなり貧しい母子家庭で育っており、その流れでうちも貧乏だったのだが、父が会社の仕事でメキメキ頭角を現してだんだんマシになっていった。父は大卒をブチ抜いて出世していたからか「大学なんて出てても社会では役に立たん」みたいなことをよく言っていた。一方で母は、父が大卒を攻撃するのはコンプレックスの裏返しだと考えていたようで、私に何とか大学は出てほしいと思っていたらしい。父の実際の心理はわからないが、この母の漠然とした思いのおかげで、私と妹は大学に行くことができた。私の一族で、少なくとも冠婚葬祭で集まる近しい範囲で大学を出ているのは、私と妹だけである。
家がその程度の感覚なので、小学生の時は学研の「学習と科学」を取ってやっていたのと、あとはそろばん塾に通っていたぐらいで、中学受験なんて考えもしなかった。家族の誰にもそんな発想はなかったし、私の小学校から私立中学に進んだ人間は一人もいなかったと思う。小学校のテストの点数は良かったが、テストのレベル自体が低いので周りも高得点を取っていた。事態が変わり始めたのは小六になる直前、友達に誘われる形で地元のそこそこ大きな学習塾に入り、算数と国語のテストを初めて受けた時のことだった。そのテストの成績が小四からずっと塾に通っている生徒たちよりも良かったとかで、先生が「この子はものすごい逸材です」みたいなことを母に言ったらしいのである。
私の住んでいた滋賀の田舎町で「ものすごい逸材」と言えば、公立の「彦根東高校」に行くものと相場が決まっていた。滋賀の公立ナンバーワンと言えば「膳所高校」なのだが、私の時代にはまだ学区制があり、私のエリアから膳所の普通科を受けることはできなかった。私はまず彦根東高校を目指すという目標を立てられ、真面目に塾に通った。とは言え、小学校時代にはドラクエやFFやダビスタをやりまくっていたし、彦根東の価値もよくわかっていなかった。なんかまあ、塾行ってこのままやってりゃ入れそうやな、という感じだった。
滋賀の田舎町には、私を超える人間が見当たらなかった
そのまま公立の中学に入ると、定期テストや実力テストというものが始まる。私はそこで五教科480〜495点ぐらいを取りまくり、それが結構ヤバイということになった。私は「天才」ということになり、私も「僕は天才なのでは…?」と思うようになった。一方、塾の方でも小学校時代より大規模な全国テスト(といってもせいぜい近畿地方が塾の勢力圏なのだが)が行われ、そこで1〜4位ぐらいをコンスタントに取り、やっぱり天才ということになった。天才ということになると、やる気が出る。私は誰に言われるでもなく異常に勉強するようになった。そこで塾は私に、某R高校や東大寺学園高校、ラ・サール高校を目標にやっていこうと言った(ちなみに、灘は某R高校と受験日が一緒なので受けられないと言われたが、そもそもその塾で全国一位を取っても灘の合格率は二十~四十パーセントだった。塾自体が灘に対応していなかったのだ)。いや、近くの彦根東でいいです、とはもはや思わなかった。私はより高い目標を目指して自分に過剰な負荷をかけることに、そしてそれが成果として現れる現実に、快感さえ覚えるようになっていった。
塾の同じ教室には私以外にも二人ほど全国ベスト30に入るぐらい優秀な生徒がおり、塾は「田舎に奇跡的に集ったこの三人の宝を育てなければならない」みたいになって、なんと私のいたいわゆる特進クラスが特進A、特進Bに分割された。わざわざ塾が私たちのために編成を変えたのである(これは記憶違いの可能性もあるのだが、私の通っていた教室には最高レベルのクラスが設置されておらず、多分それを勝手に作ることもできなかったので、上から二番目のクラスを二つに割り、片方を疑似最高クラスとして扱ったみたいな感じだったと思う)。私はこのVIP待遇を見て自分を完全に天才だと確信した。これは田舎特有の現象だろう。東京や大阪ならもっとレベルの高い塾が乱立しているし、周りに自分より出来る人間はいくらでも見つかったはずだが、私のいた滋賀の田舎町には、私を超える人間が見当たらなかったのだ。
視野が狭すぎる、と言われればその通りなのだが、まだインターネットも発達していなかったし、SNSなんて影も形もなかった。たとえば中学生に格闘技団体のUFCやRIZINの存在を教えずブレイキングダウンだけを見せていたら、ブレイキングダウン選手を世界最強だと思うようになっても無理はないだろう。しかし、この視野の狭さが私の勢いを加速させた。「自分は天才だ」という思い込みは、私を勉強にドハマリさせたのである。私は神に与えられたこの才能を腐らせてはならないと思い込み、勉強に勉強を重ねた。勉強していない時間をいかに減らすかということにこだわり、風呂に入る前には間違えた問題を紙に書き、風呂の壁に水分で貼り付けた。頭を洗っている時以外はそれを睨んだ。記憶術の本を読み、夜眠る前には必ず暗記物をやるようにした。
通っていた公立中学の授業はもはや完全に無駄だった。簡単なワークを終えて余った時間で、隠れて塾のテキストをやった。同じ塾の特進Aの菅井君(彼は後にも出てくる重要人物である)などは、なんと授業中に某R高校の赤本を机に丸出しで解きまくり、先生からベランダに呼び出されて激怒されていた。私はさすがにそこまであからさまにやる度胸がなかったので、「菅井、やるな」と思っていた。
そんなこんなで、私は勉強に明け暮れる中学時代を過ごした。公立中学なので(?)喧嘩に明け暮れるヤンキーもいたし、ガチのヤクザの息子もいた。しかしヤンキーたちですら私を天才と認め、温かく応援してくれた。普通にガリ勉と言われていじめられても良さそうなものだったが、私のガリ勉ぶりとそこから叩き出す偏差値は──自分で言うのもなんだが──町内では常軌を逸しており、ほとんど神の領域に達していた(あくまでも町内では)。ヤンキーたちもおそらく私のことを、国の未来を担う逸材だと考えてくれていたのだ。
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)