2022.5.31
湯の中の世の中(1)──式亭三馬『浮世風呂』にみる他者との距離
当記事は公開終了しました。
2022.5.31
当記事は公開終了しました。

江戸POP道中文字栗毛

江戸POP道中文字栗毛

江戸POP道中文字栗毛

江戸POP道中文字栗毛

江戸POP道中文字栗毛
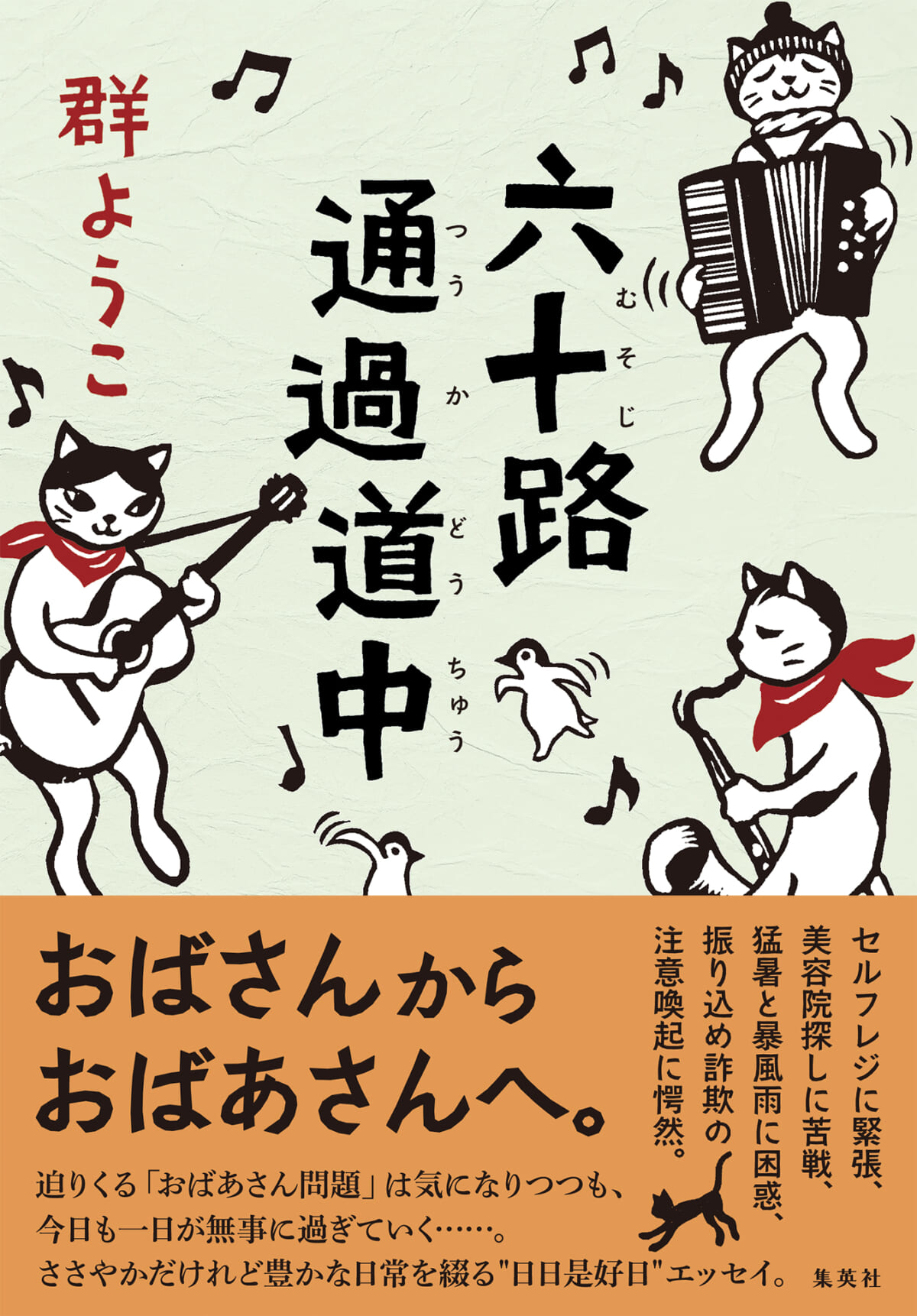
2024/5/24
NEW
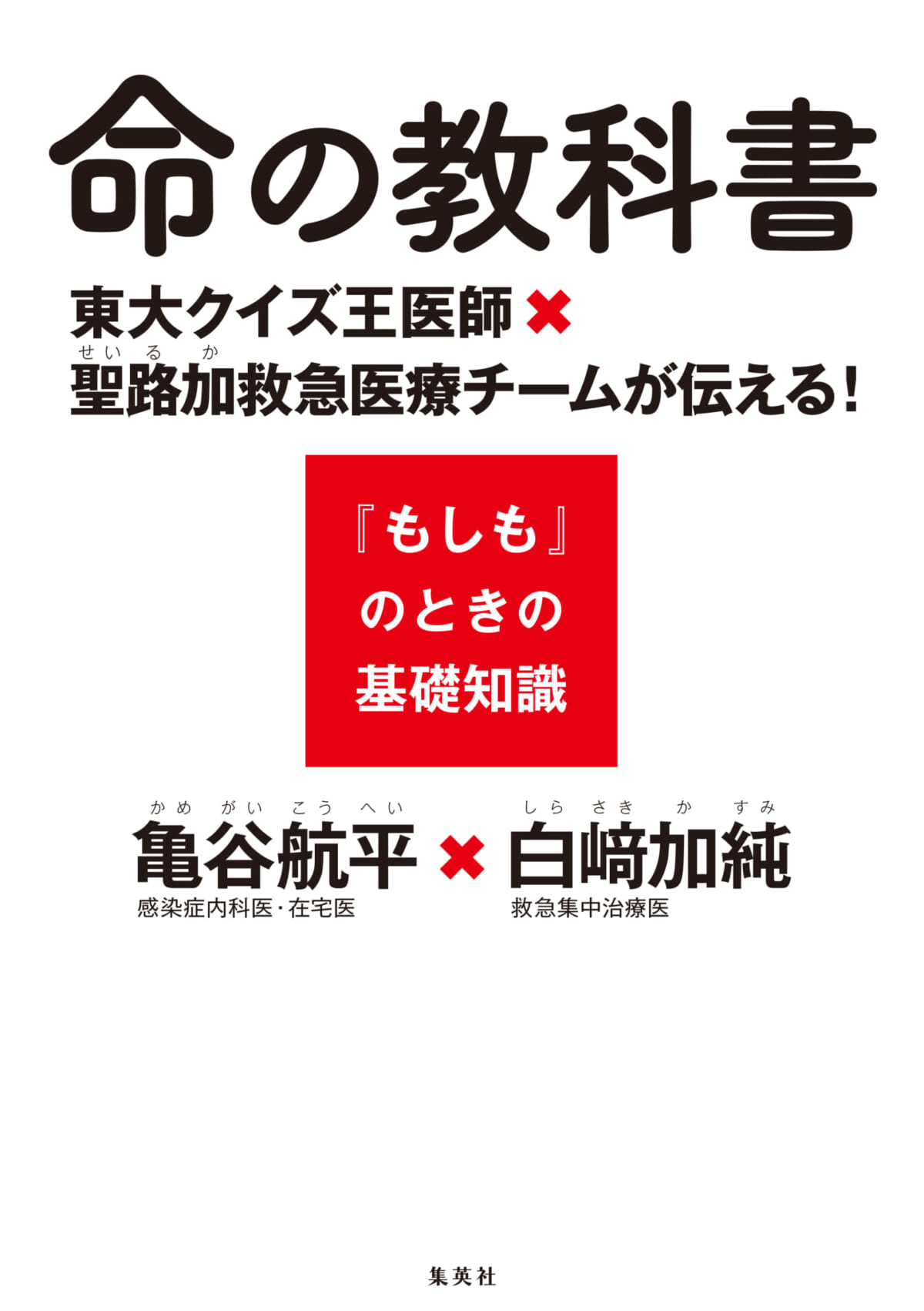
2024/3/5
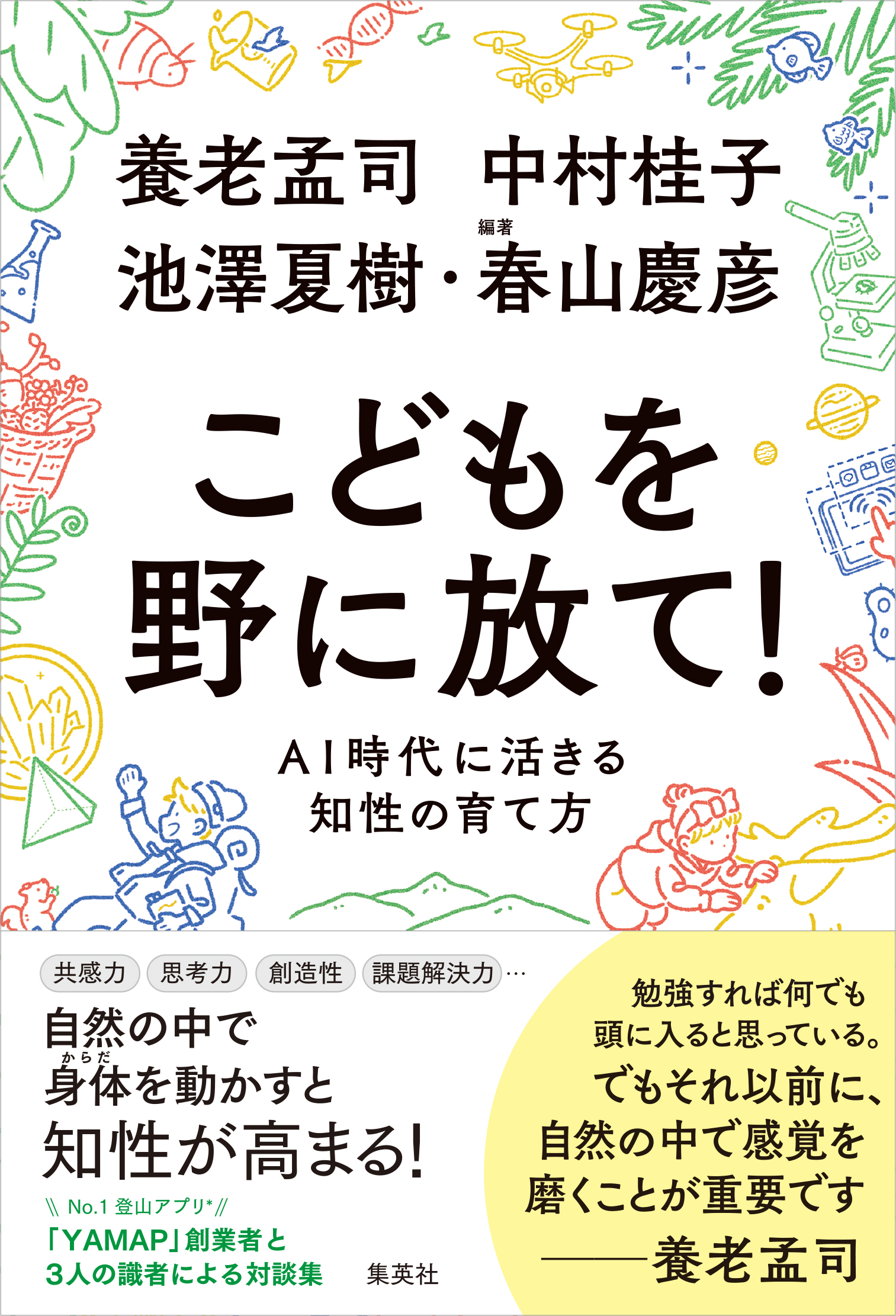
2024/2/26
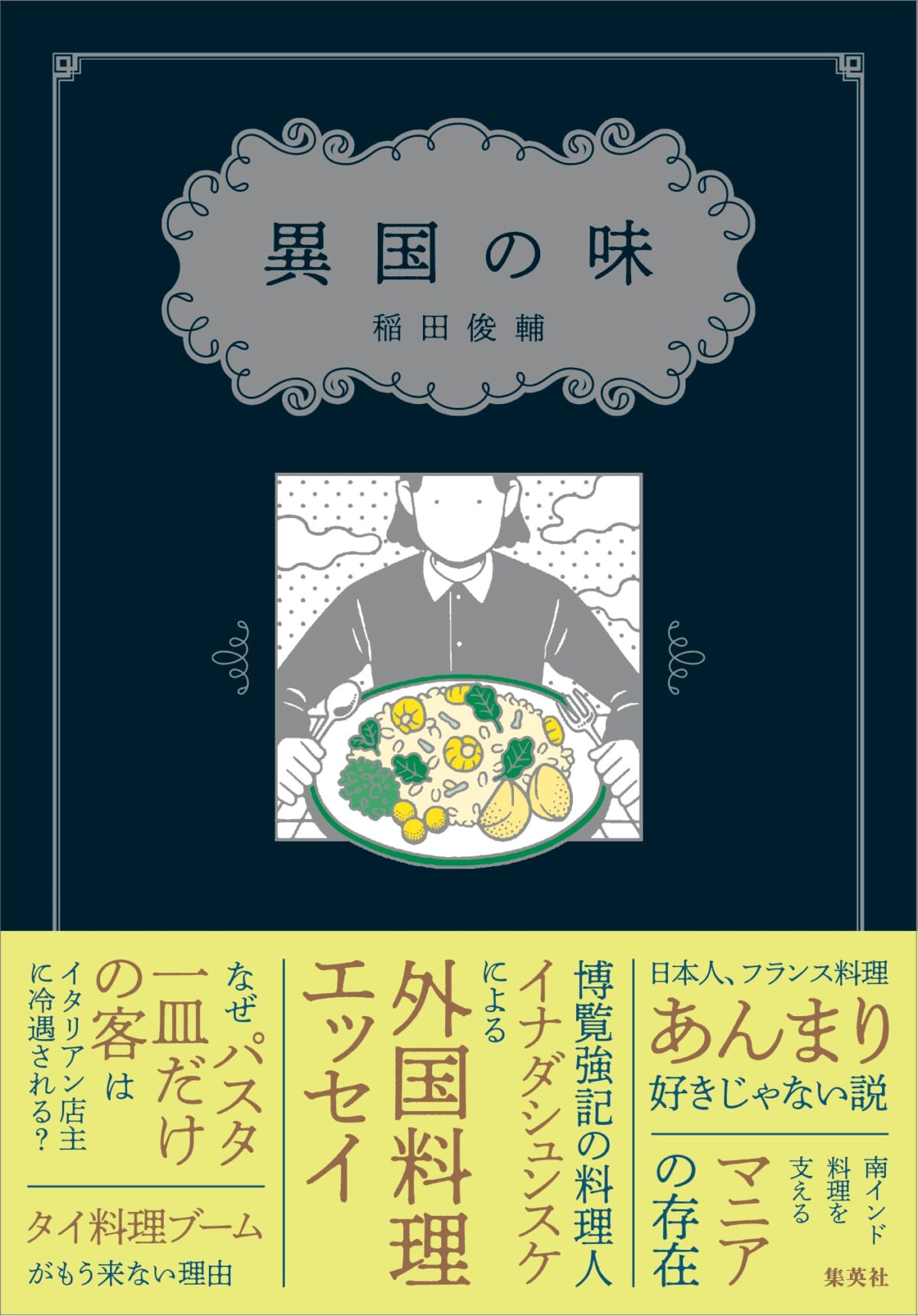
2024/1/26
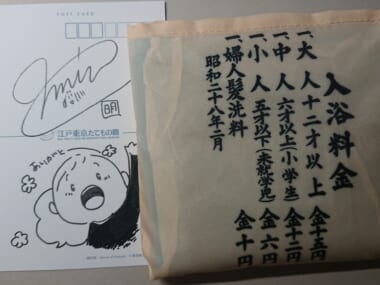
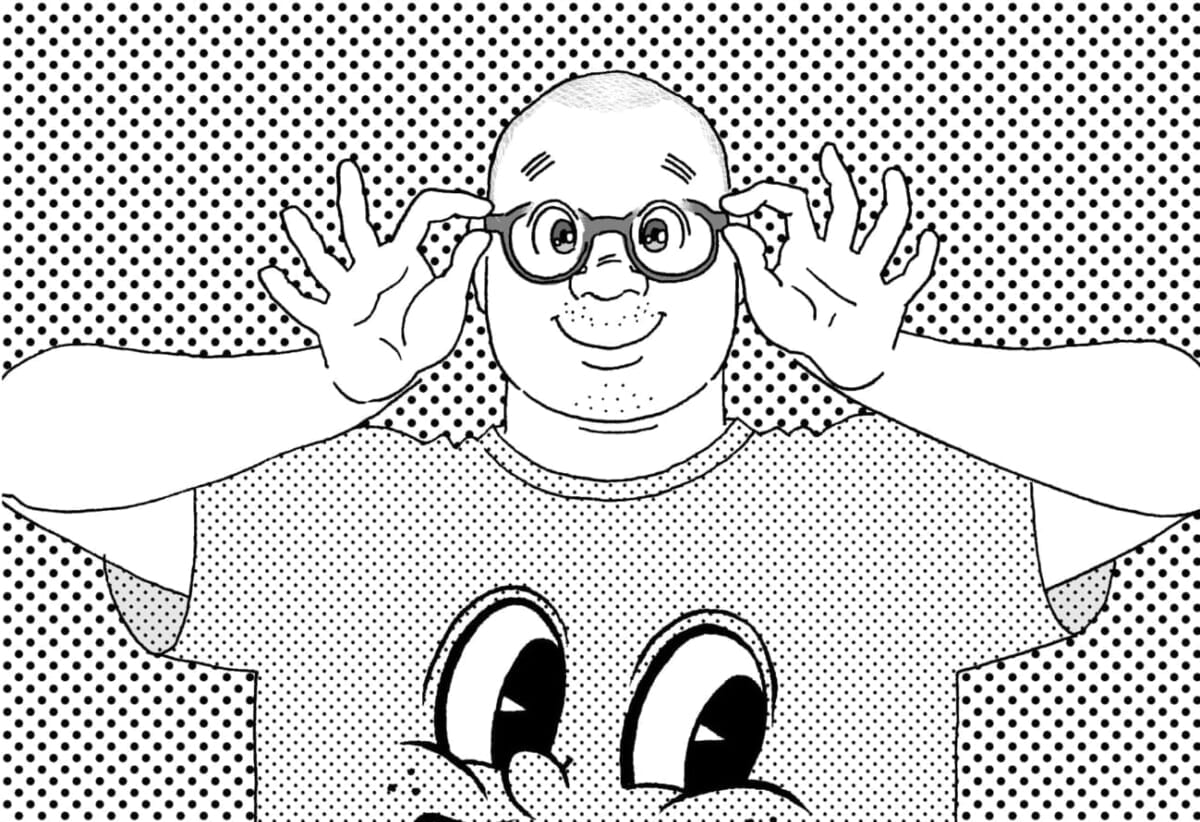
午前三時の化粧水

フィンランド くらしのレッスン

酒のつまみは、宇宙のはなし