2022.2.22
流行語ほんま草生い茂って山──『金々先生栄花夢』の一部を超現代訳してみた
当記事は公開終了しました。
2022.2.22
当記事は公開終了しました。

江戸POP道中文字栗毛

江戸POP道中文字栗毛
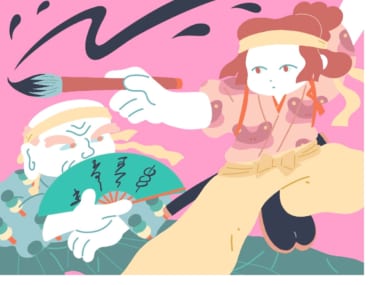
江戸POP道中文字栗毛

江戸POP道中文字栗毛

柴田勝家、戦国メイドカフェで征夷大将軍になる
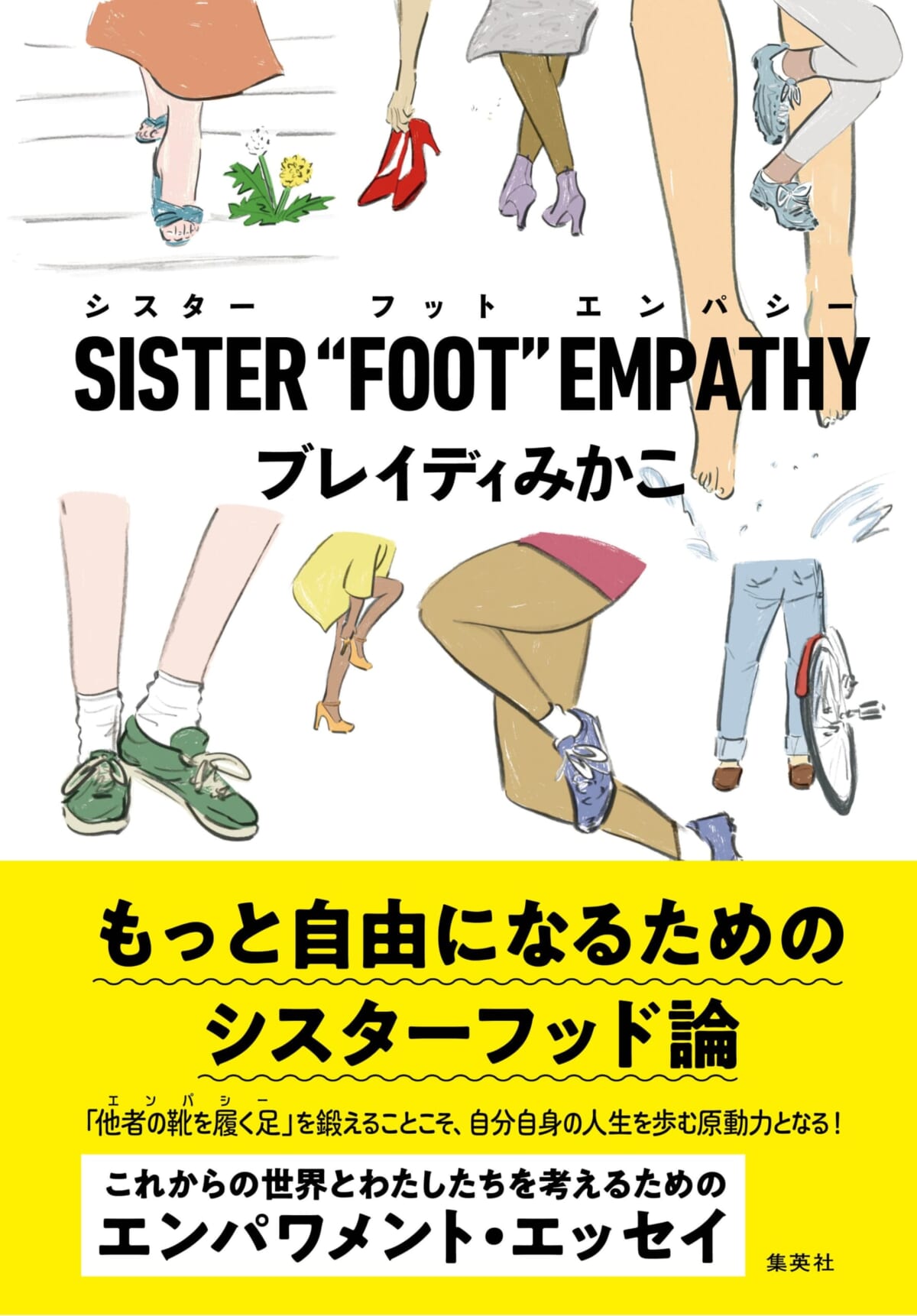
2025/6/26
NEW
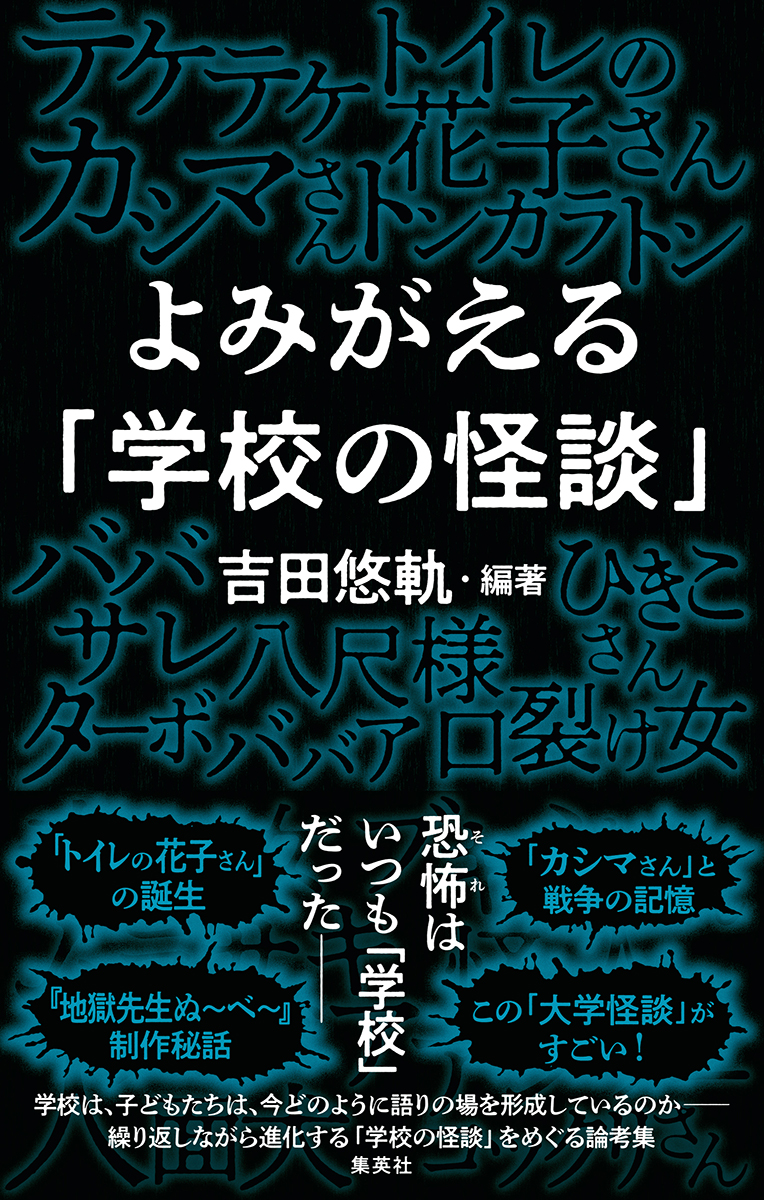
2025/7/4
NEW

2025/5/26
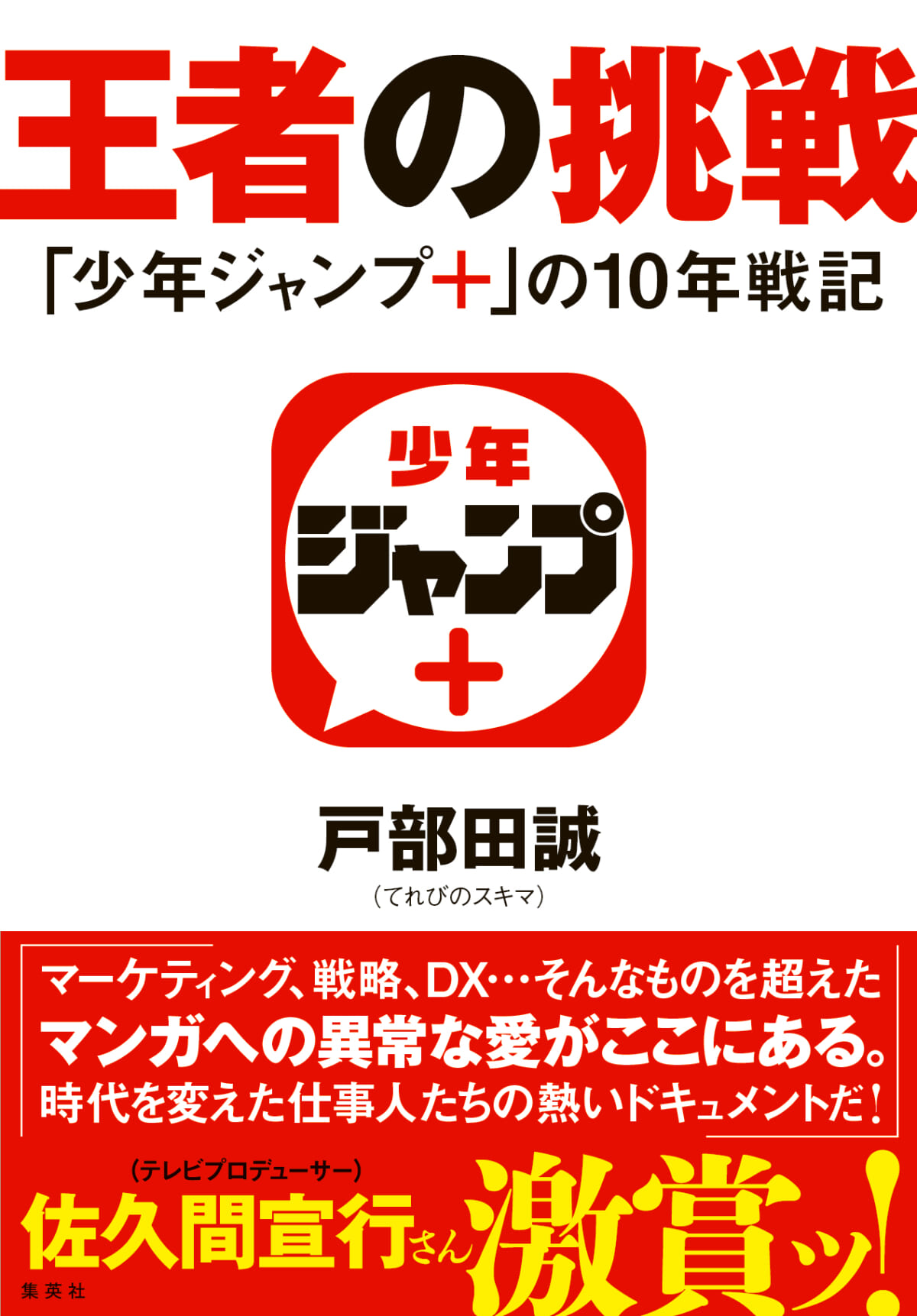
2025/5/9