2023.3.20
漂白された出会い系? 経営学者がマッチングアプリに連戦連敗して見抜いた本質とは
当記事は公開終了しました。
2023.3.20
当記事は公開終了しました。

そこそこ起業 異端の経営学者が教える競争せずに気楽に生きる方法

そこそこ起業 異端の経営学者が教える競争せずに気楽に生きる方法

そこそこ起業 異端の経営学者が教える競争せずに気楽に生きる方法

そこそこ起業 異端の経営学者が教える競争せずに気楽に生きる方法

そこそこ起業 異端の経営学者が教える競争せずに気楽に生きる方法
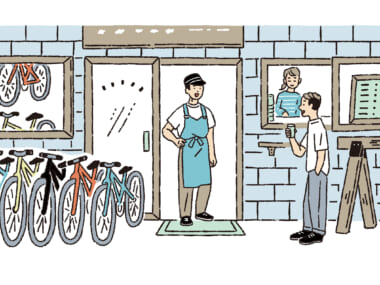
そこそこ起業 異端の経営学者が教える競争せずに気楽に生きる方法
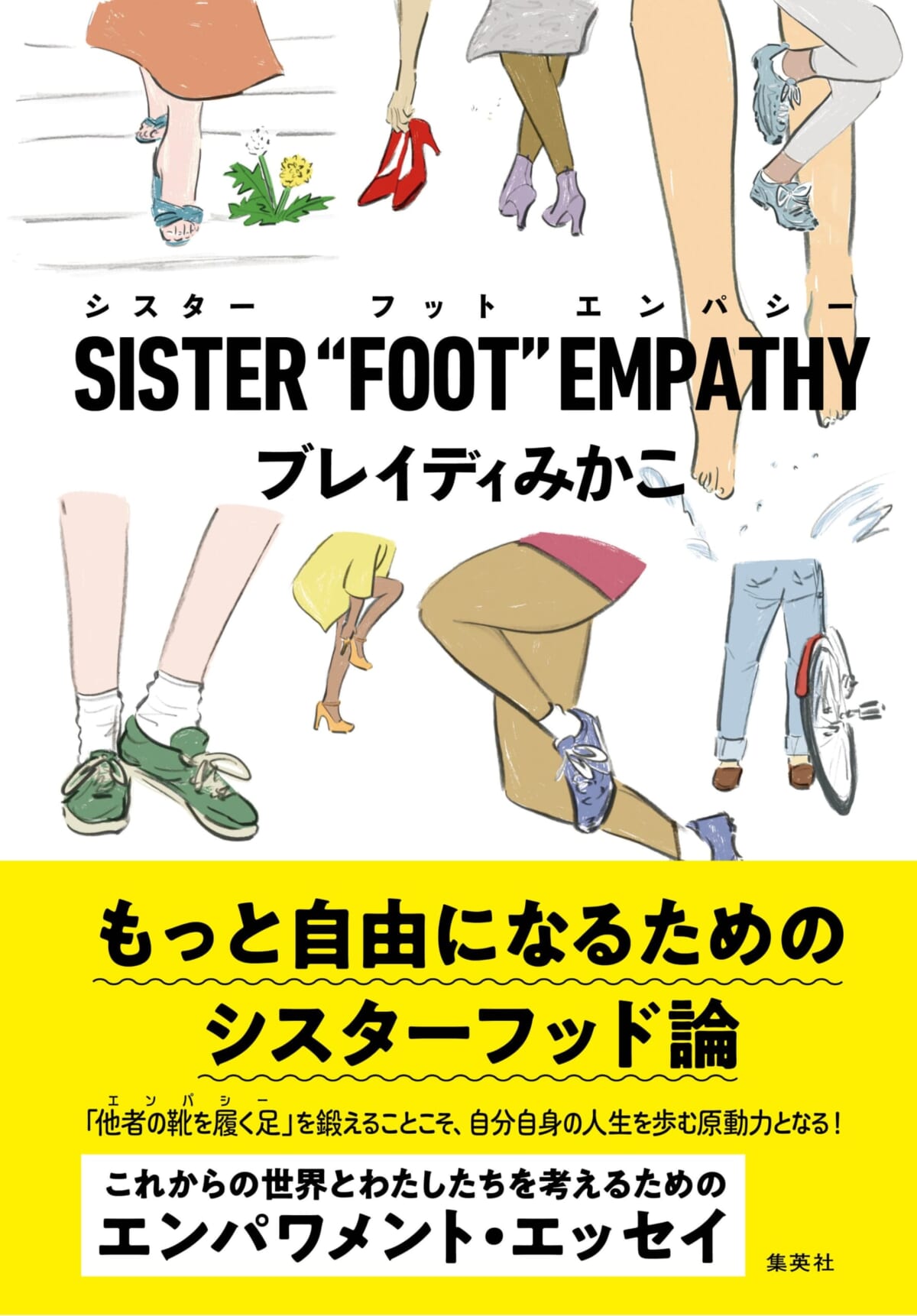
2025/6/26
NEW
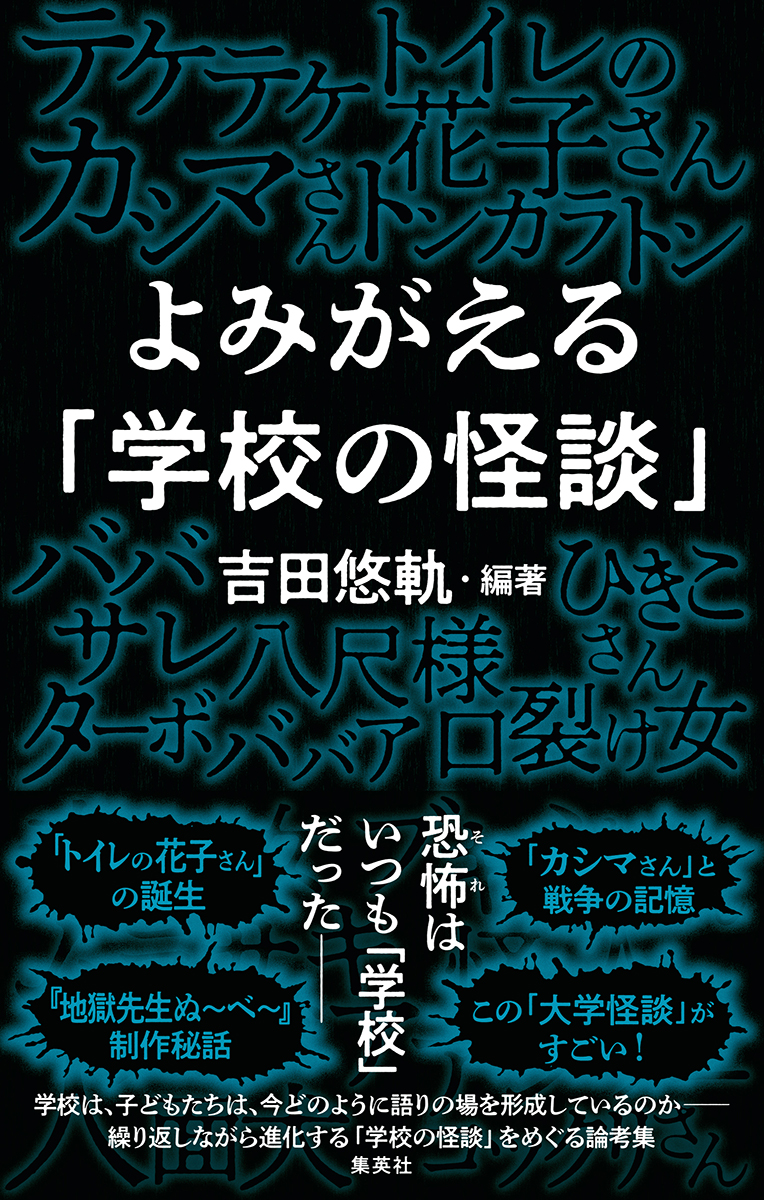
2025/7/4
NEW

2025/5/26
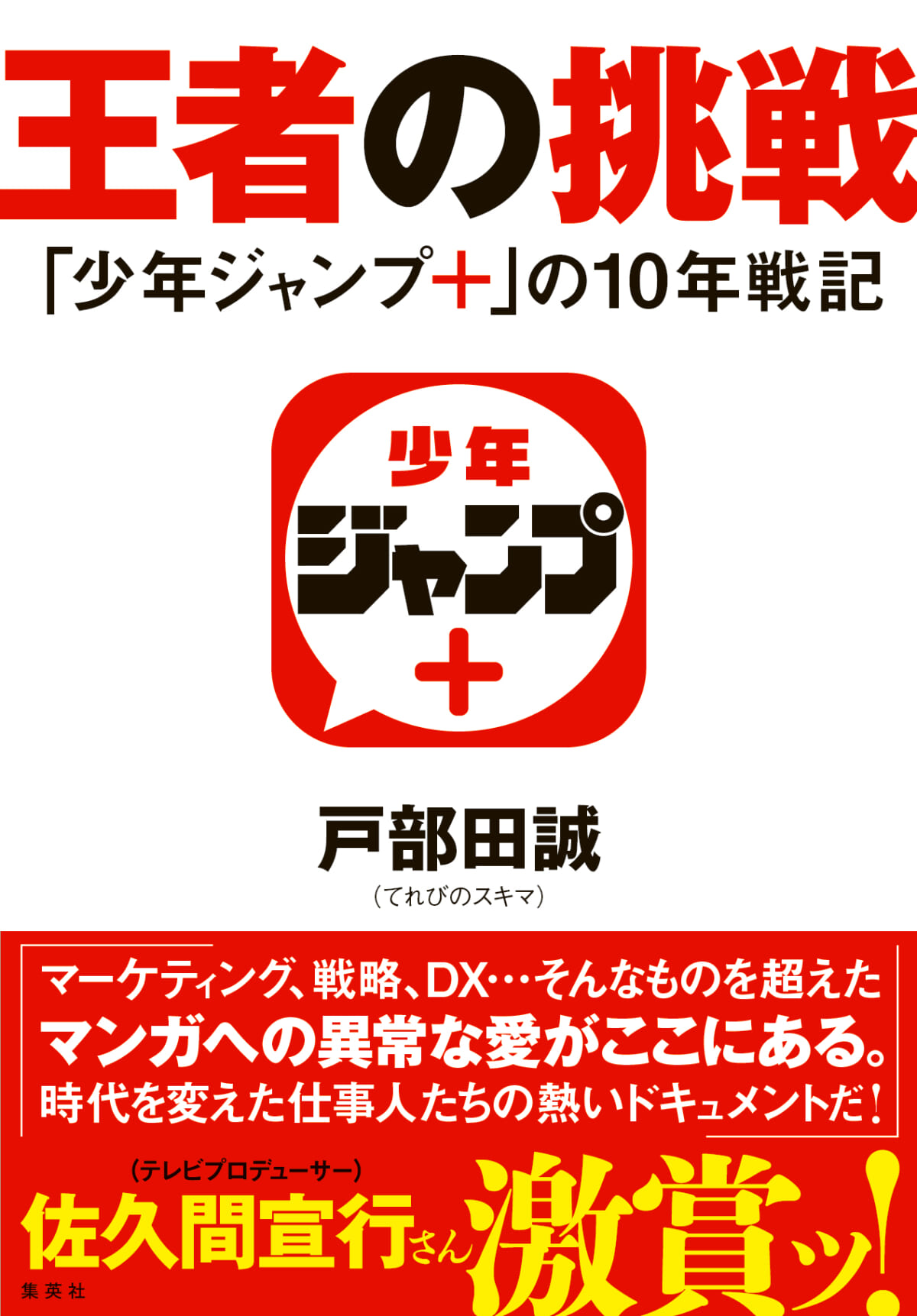
2025/5/9

もう一度、君の声が聞けたなら

私たちは癒されたい 女風に行ってもいいですか?

白兎先生は働かない
