2020.5.4
第3回 緑を探すひと
当記事は公開終了しました。
2020.5.4
当記事は公開終了しました。

今日は、これをしました
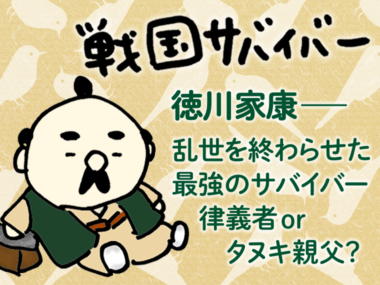
戦国サバイバー

ブスとお金

海の怪

海の怪

2025/8/26
NEW

2025/6/26
NEW
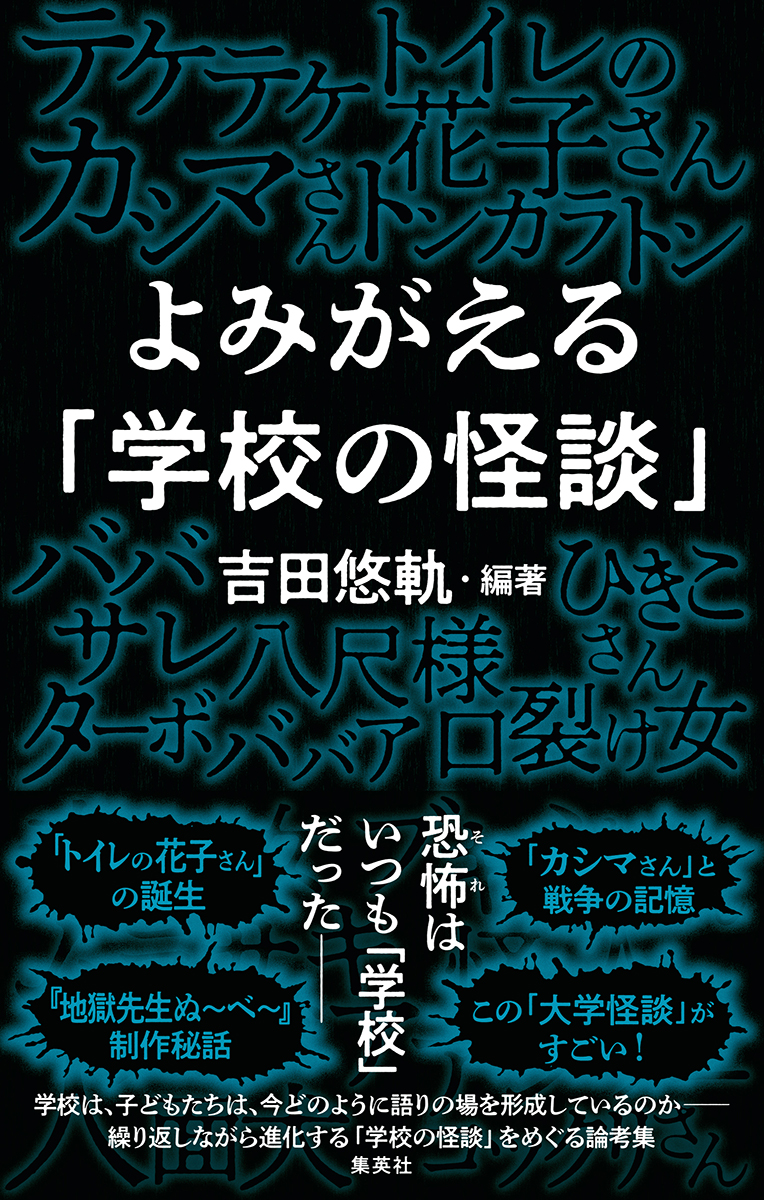
2025/7/4
NEW

2025/5/26

白兎先生は働かない

ケアとアートのダンス ~アクセシビリティのためのプロジェクト・レポート~

もう一度、君の声が聞けたなら

私たちは癒されたい 女風に行ってもいいですか?