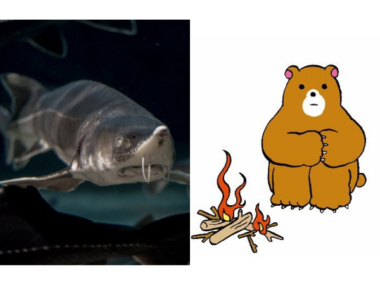2021.10.9
気になる女性が男と自分のタクシーに乗りホテル街へ向かう──新米タクシー運転手の苦い体験
日経新聞などの書評欄でも紹介された、昭和・平成・令和を貫くタクシードライバーたちの物語を、期間限定で全文無料公開します!(不定期連載)
前回は、2019年の東京で「私」が語る、新人ドライバーの失敗談でした。
第2回からの舞台は「1970年代の京都」です。新米タクシー運転手の「俺」が経験した、オイルショックと恋の物語。
いつも鏡を見てる 第2話
1章 オイルショックと京都の恋 【京都 1973~1974年】

三条大橋西詰 1973年11月15日
みやびさんにしてみれば河原町三条から粟田口まで二キロ足らずの距離を乗っているのはさぞ居心地が悪い時間だったろうが、それは俺にしたって同じだ。男と連れ立ってホテルに行くのにタクシーを捕まえたまではいいが、運転手がよりによって俺だなんて、お互い考えたくもない偶然だった。
信号待ちをしていたときに男が後ろの窓をトントンと叩き、ドアを開けたら、彼は「早よ」と誰かを呼び、自販機でタバコを買っていた女が小走りで寄ってきた姿は俺の視野の端っこに入ったけれど、顔は見ていない。「おおきに」と言いながら女がクルマに乗り、閉めますよと声をかけて振り返ったら、みやびさんだった。瞬間、表情が引きつったようになったのは彼女で、察した俺は知らん顔を決め込んだ。男は「粟田口」とだけ言い、聞いた俺は黙って頷き、そういう態度はいつもといっしょでも、このときばかりは、内心、穏やかではいられなかった。夜中にタクシーに乗った男女が行き先を粟田口と言ったら、それは粟田口を北に入ったホテル街までという意味だと客も運転手も承知している。
一か月くらい前のことだ。高島屋の紙袋を下げた若い女の客は今出川智恵光院までと目的地を告げ、はじめのうちは黙ったままだったが、ハンドルを膝で押さえながら着ていたジャンパーを脱ぎだした俺に「サーカスみたいやな」と声をかけた。「危なっかしい運転せんといて」と言いたいところを遠回しの京都流かと舌打ちしそうになり、そこに、親しげな口調で「わからへんの、うちのこと」が続き、身を乗りだすようにして話す女の姿がミラーに映った。誰だっけ。思ったが口にはださず、堀川丸太町の信号で止まったときに顔を見て、やっとわかった。西木屋町の六角を下った角に『雅』というバーがあって、店の前でいつも客引きをしている髪の長い女だ。ここのところ夜中の客がめっきり少なくなったのは飲み屋もタクシーもいっしょで、最近の俺は、客を探すのに木屋町から西木屋町、そこから路地を西に入って河原町通りへというルートを流している。一晩に二度も三度も同じ道を走っていれば、客引きの女と俺が互いの顔を見覚えるまでに時間はたいしてかからない。初めのうちは会釈をするだけだった。時間にしたら、せいぜい5秒か、長くても10秒はないけれど、気づくと、そのわずかな時間のために路地を通るようになっていた。5秒か10秒、ずっと視線を合わせるようになった。それが嬉しかった。彼女の姿がそこにないと、空車のまま、また路地に戻った。「サーカスみたいやな」と声をかけてきたのは、その女だった。名前は知らないが、店が雅だから、とりあえず「みやびさん」と呼んだ。あの日からこっち、彼女と俺はよく話をするようになり、仕事終わりに三条木屋町のうどん屋にいっしょに行ったことが何度かあった。本名は由里絵だと後になって聞いたが、俺はいまでも「みやびさん」で通している。21の俺より6つか7つ年上のみやびさん。その彼女が、男とホテルに行くのに俺のクルマに乗り合わせた。河原町三条から粟田口まで2キロ弱、5分もあれば着く距離だが、わずか5分は、吐き気を覚えるほど胸を締めつけて鳴り続ける鼓動と気まずさに占領された5分だった。二人を三条通りで降ろすつもりだったのに、男は左に曲がってくれと言い、ホテルのネオンがにぎやかな一筋目の角で「ここでええわ」と言った。俺の心臓がどっくんどっくんと大声で叫びはじめた。男と並んでホテル街を歩きだしたみやびさんが一度だけ振り返り、ほんの一瞬、俺と目が合った。
空車のタクシーが集まる場所
三条大橋西詰の路肩にクルマを止め、大きくため息をついてから残しておいたハイライトの最後の一本に火をつけ、空になったパッケージをクシャッと握りつぶしたのは、それから20分後のことである。ふ~っ、と吹いた煙は半透明の白い風船の形を大きくしながら前に進み、その勢いがなくなったとたん宙に向かい霧散していった。
一時半を過ぎたばかりだった。
カーステレオにカセットを押し込むと、ロバート・ジョンソンがギターを弾きながら歌うけだるい声が流れてくる。ミシシッピのクロスロードで悪魔と契約を交わし、ギターの腕前を手に入れる代償として自分の魂を売り渡した、そんな伝説を残すブルースマンだと何かで読んだことがある。他人の女房に手をだし、ウィスキーに毒を盛られて27歳でこの世を去ったという彼が歌う『SWEET HOME CHICAGO』だ。
本当なら明け方近くまであと2~3時間は仕事をしているところだが、近ごろのタクシーはすっかり早仕舞いになった。考えてみれば、ため息が多くなったのも、ちょうど同じ頃からだった。
この時間になると、うちの会社のクルマに限らず山科に営業所があるタクシーが三条大橋の西詰に空車で集まってくる。いつから始まった決め事か誰かに尋ねたこともないけれど、深夜から明け方にかけて北側の路肩で付け待ちしている空車のタクシーは、どうせ仕事を終えて入庫するなら山科方面への客を乗せて帰りたいと考え、客もそれを知っているものだから、わざわざここまで歩いてきてくれる。客にも運転手にもずいぶん便利な暗黙の了解事だと思う。かくいう俺も、その日の最後の客を待つためにクルマを止めていた。ここで止まると、それまで点けていたラジオを消してロバート・ジョンソンに代えるのは仕事終わりの儀式のようなもので、すると、頭の隅に三条大橋制札事件*1が浮かんでくるのもいつものことだった。近くには、池田屋事件の、あの池田屋の跡もあり、三条大橋の欄干の擬宝珠にはそのときの切り合いでついたと伝わる刀傷が残っているとも聞いた。それなのに、有名な池田屋事件ではなく制札事件の方が浮かんでくるのはどうしたことだろう。京都にはタクシー運転手が1万人くらいはいるが、そのうち、幕末期に起こったこの事件の概要だけでも観光客に話ができるのは、果たしてどれほどいるだろうかと考えることがある。10人に一人か二人、いや、いかに京都のタクシー運転手といえど、もっと少ないかもしれない。にもかかわらず、誰かに教わったのか、それとも何かの本を読んだから知っているのか、それすら記憶があやふやなのに、しかも、京都の歴史を観光客に問われても、その、いろはすら満足に答えられない新米タクシー運転手だというのに、三条大橋制札事件をそらで言えてしまうのが我ながら不思議でしょうがない。
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)