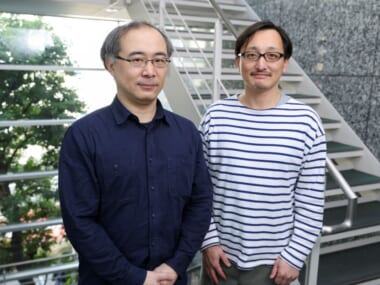2022.12.22
美術史上初の静物の描き手、カラヴァッジョが絵の中に込めたものとは 第4回 失われゆくもの、移ろうものの表現者たち
当記事は公開終了しました。
2022.12.22
当記事は公開終了しました。



米国生活で磨いた ネイティブがよく使う英会話フレーズ100

実母と義母

猫沢家の一族

2025/6/26
NEW
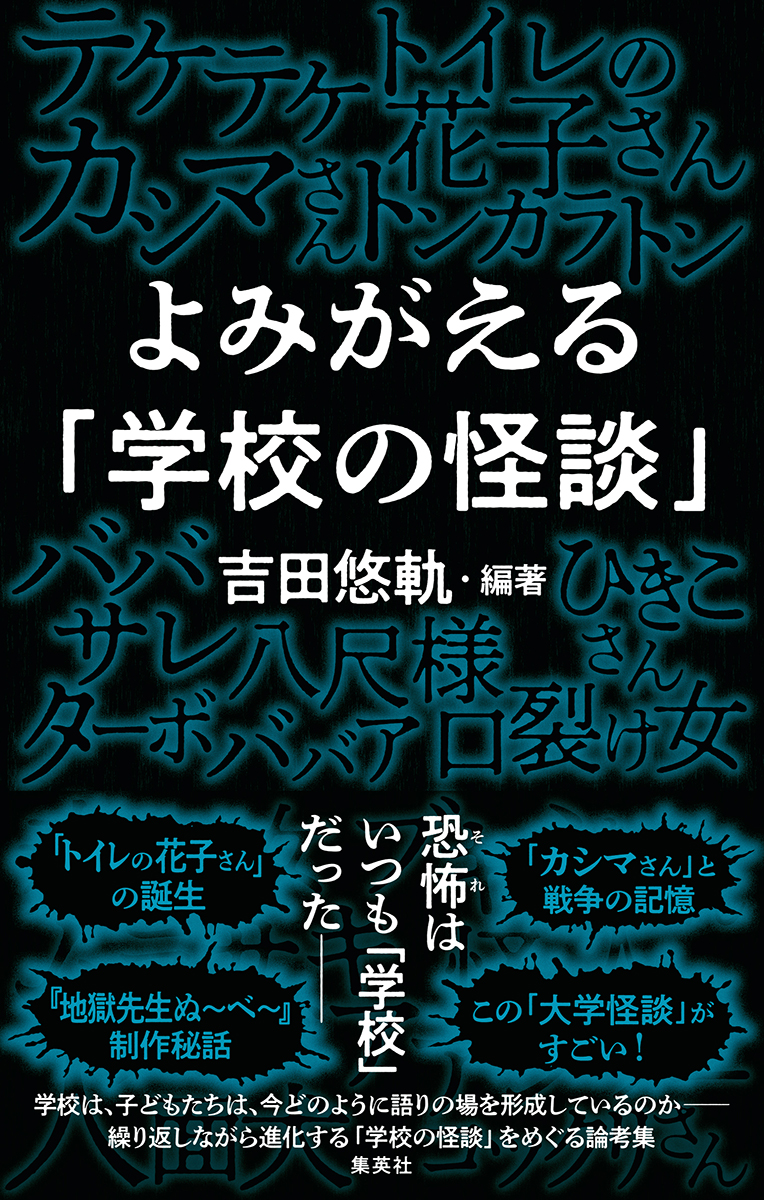
2025/7/4
NEW

2025/5/26

2025/5/9

私たちは癒されたい 女風に行ってもいいですか?

白兎先生は働かない