2021.11.30
天下一言語遊戯会──俳諧史とポピュラー音楽の意外な共通点
当記事は公開終了しました。
2021.11.30
当記事は公開終了しました。

江戸POP道中文字栗毛

柴田勝家、戦国メイドカフェで征夷大将軍になる

柴田勝家、戦国メイドカフェで征夷大将軍になる

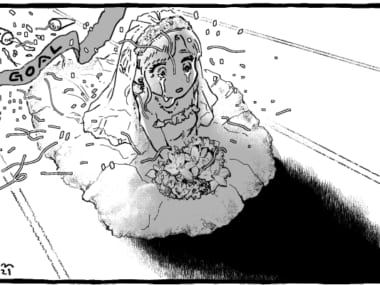
ダメ恋やめられる!? 〜発達障害女子の愛と性〜
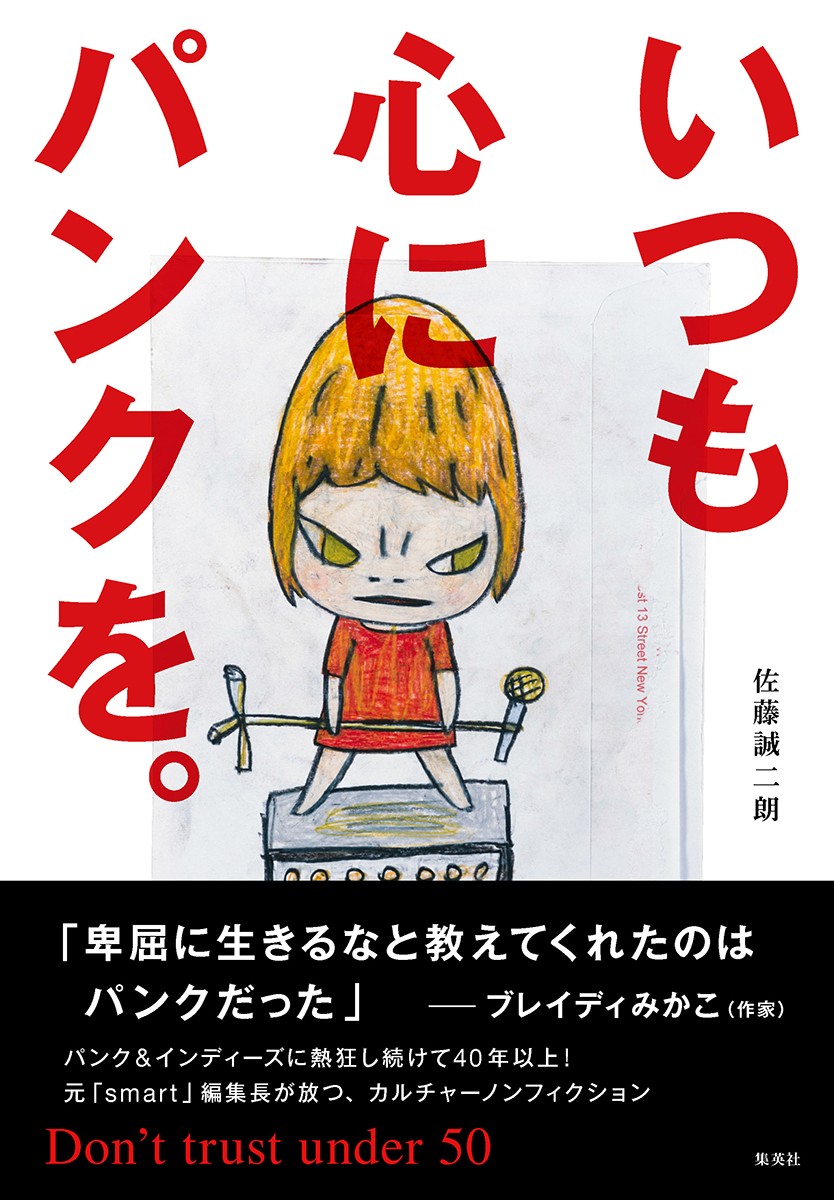
2025/8/26
NEW
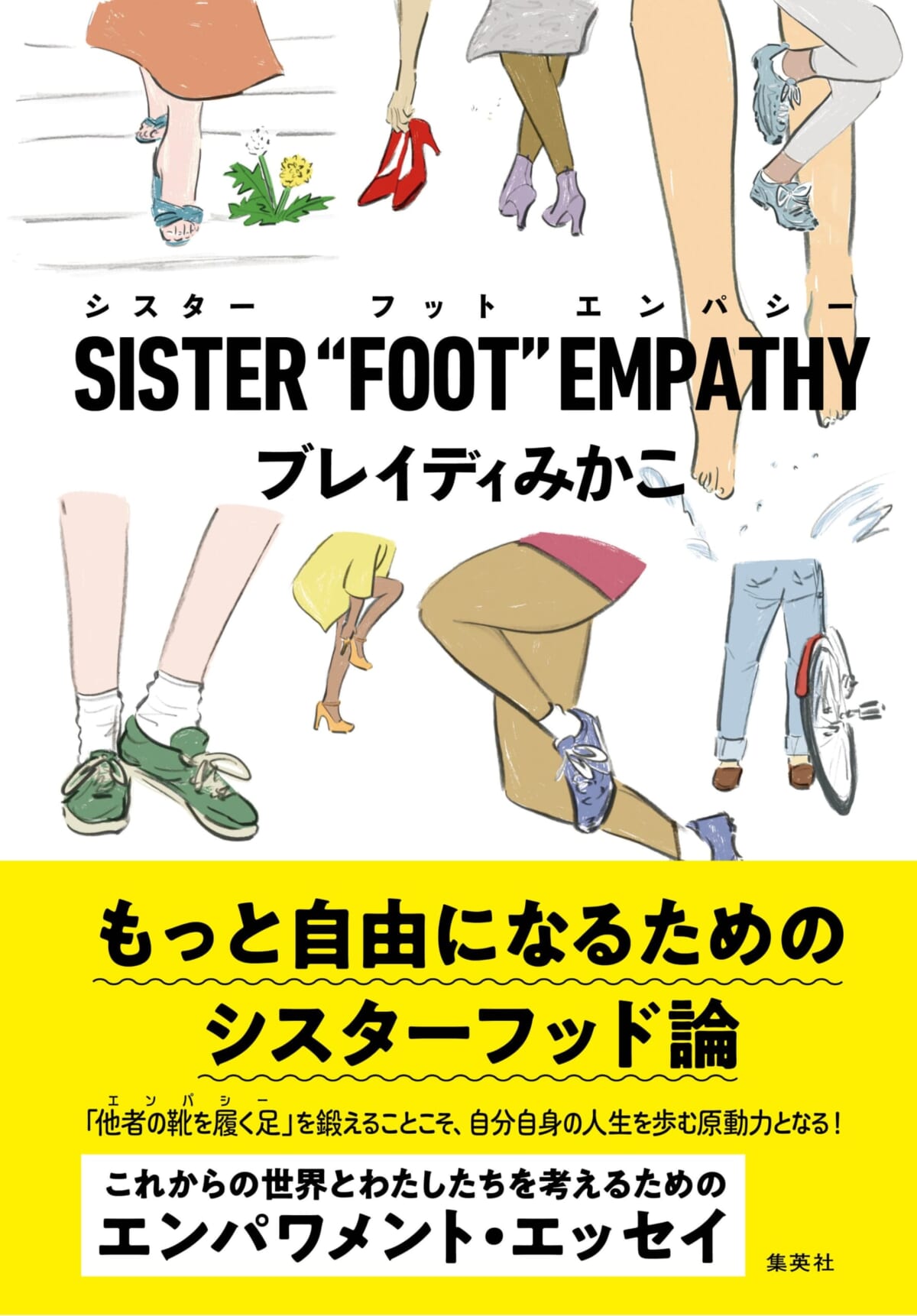
2025/6/26
NEW
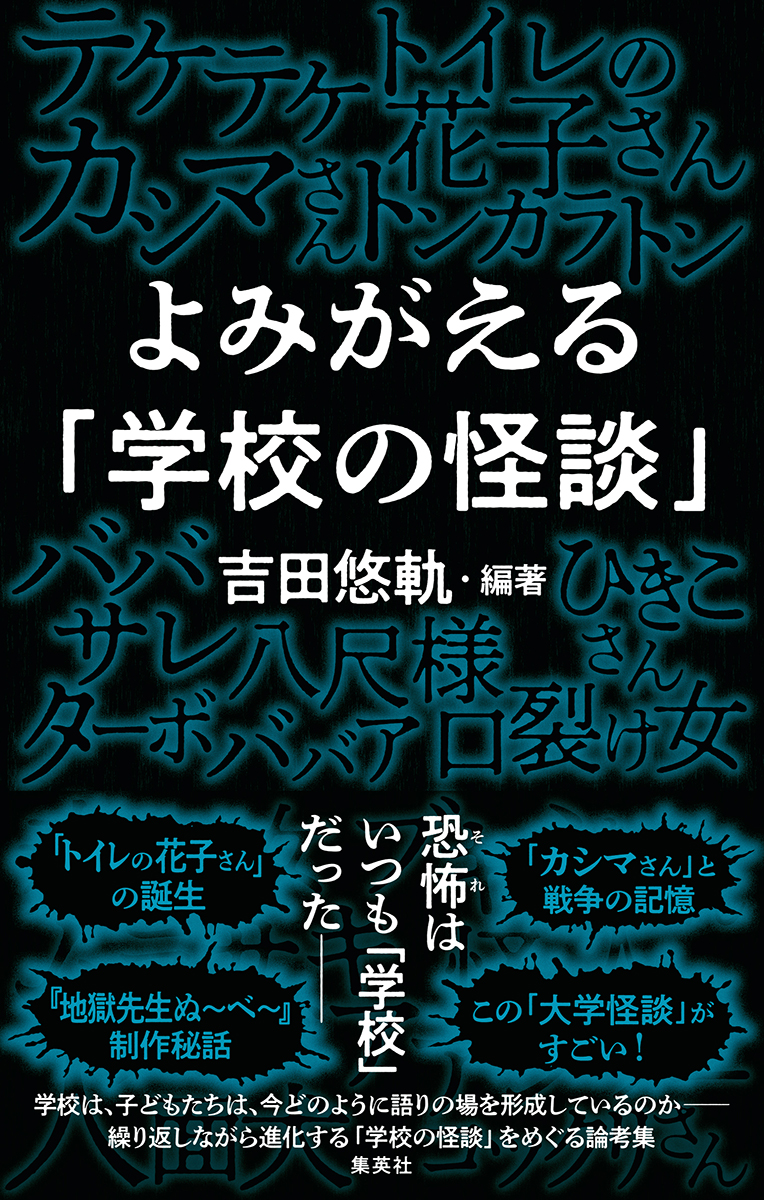
2025/7/4
NEW

2025/5/26

白兎先生は働かない

ケアとアートのダンス ~アクセシビリティのためのプロジェクト・レポート~

もう一度、君の声が聞けたなら

私たちは癒されたい 女風に行ってもいいですか?