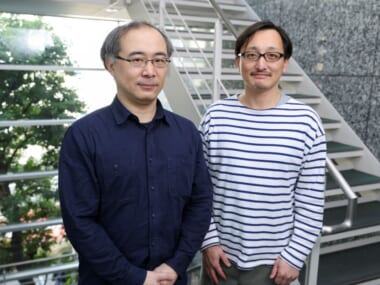2020.4.17
サイコビリー狙いで久々にオーバーオールを買ったら志村園長になった
当記事は公開終了しました。
2020.4.17
当記事は公開終了しました。

グリズリー世代のバック・トゥ・ザ・ストリート

グリズリー世代のバック・トゥ・ザ・ストリート

No Meat,No Life.を生きる男の肉だらけの日々 肉バカ日誌

MBの人生もファッションも変わる親切すぎるお悩み相談部屋

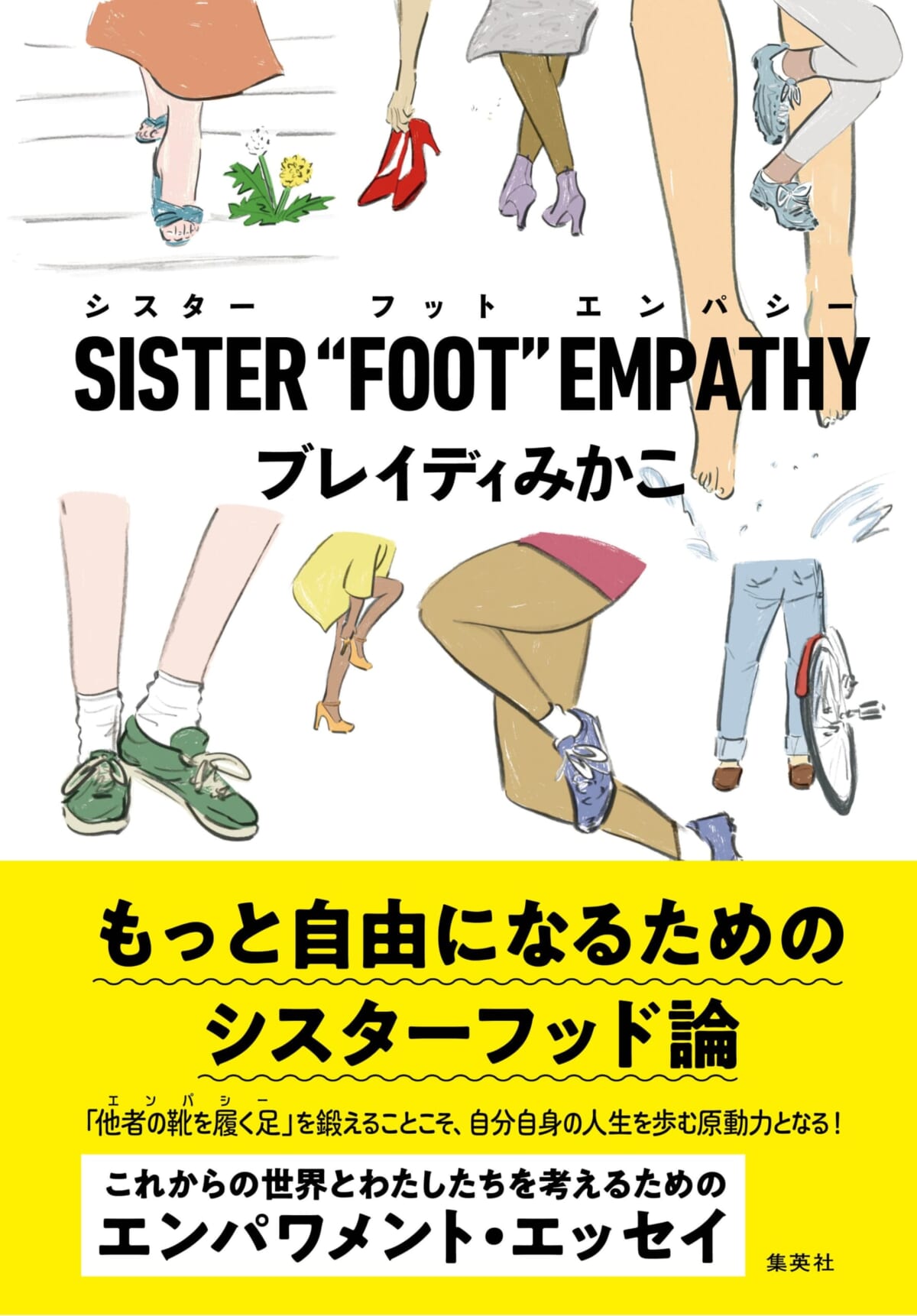
2025/6/26
NEW
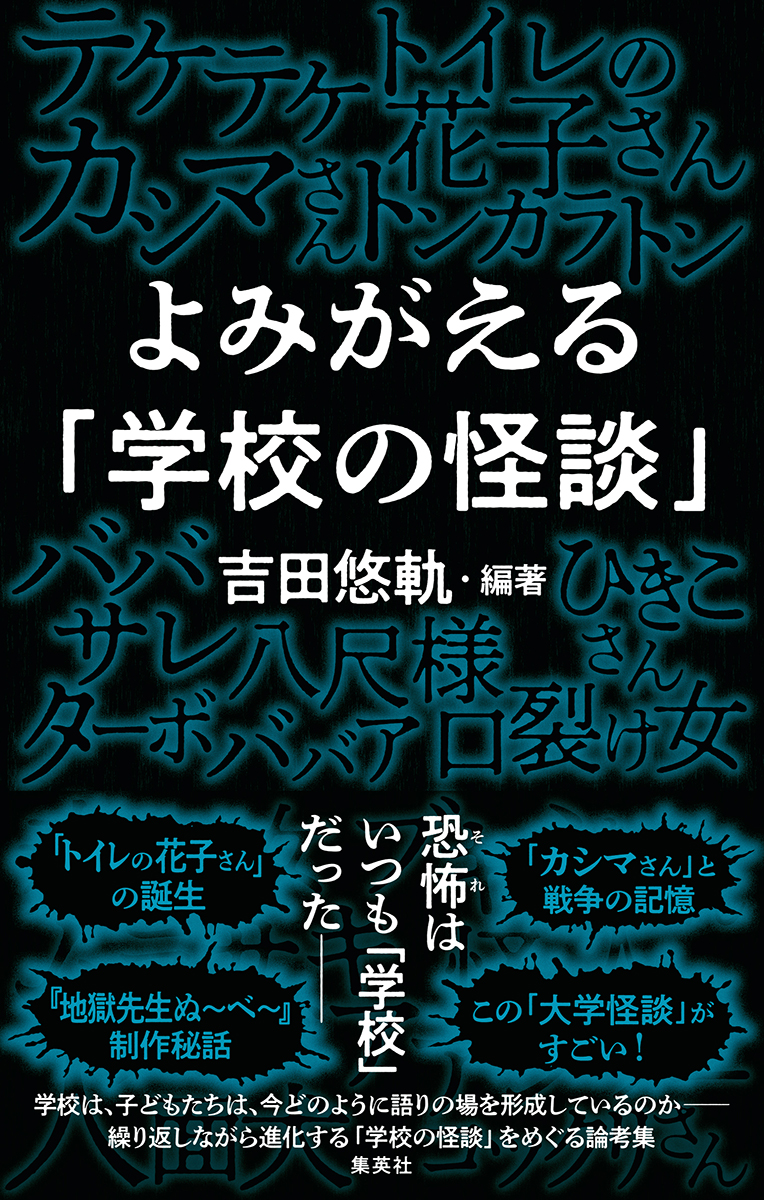
2025/7/4
NEW

2025/5/26
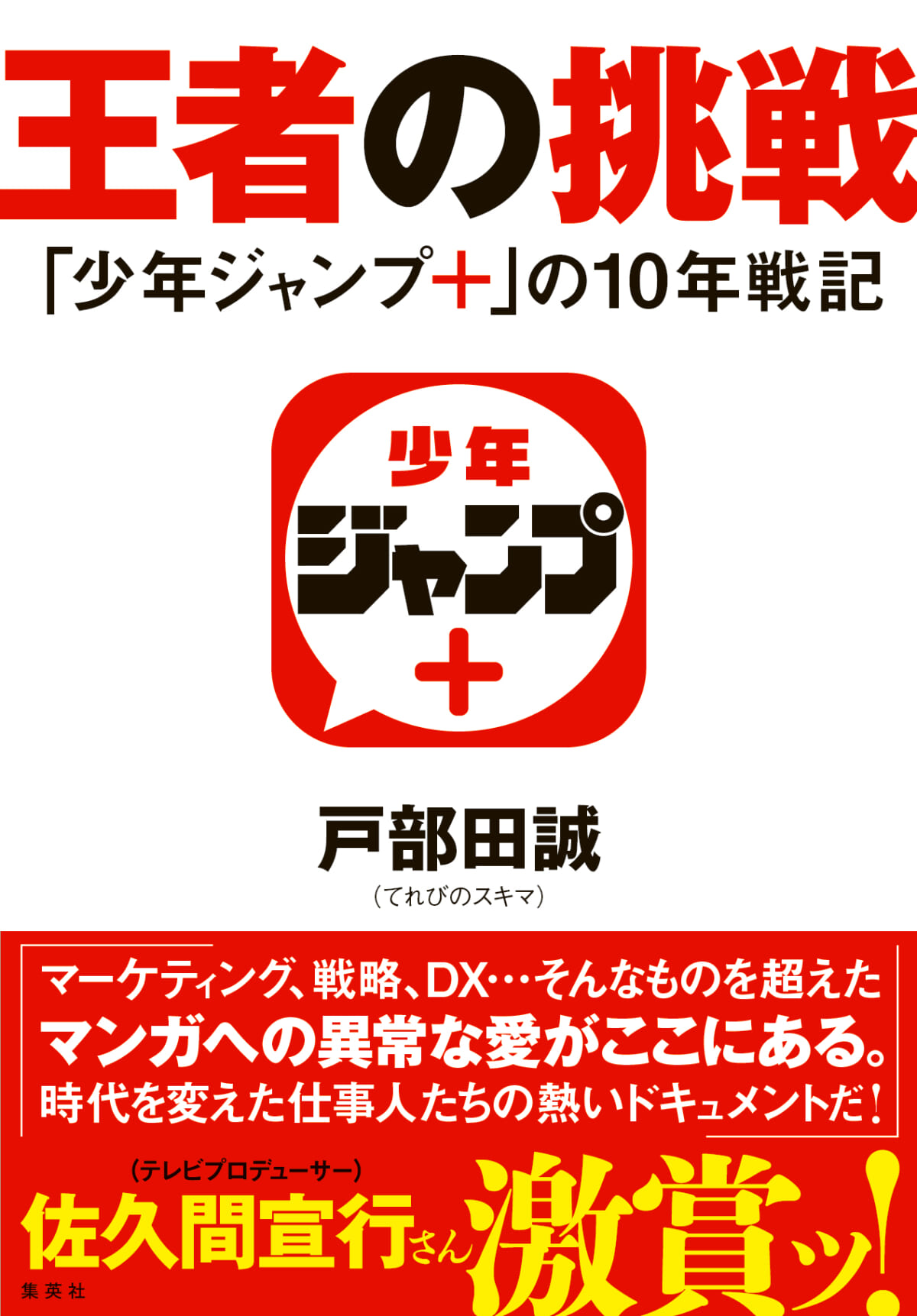
2025/5/9

私たちは癒されたい 女風に行ってもいいですか?

白兎先生は働かない