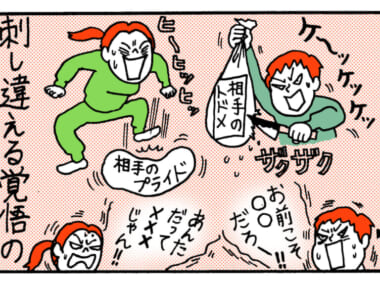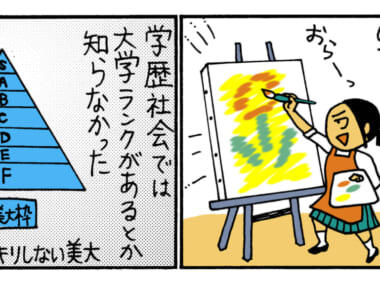2025.9.23
第5回 なぜその「ほめ」ことばは伝わらないのか?──伝わる「ほめ」を考える
大塚さんの研究手法は、当事者に実際の会話を録音してもらい、どのような場面で、どんなことばが用いられ、そのことばを通してどのように人間関係がつくられていくかを分析するというもの。リアルな会話を手に入れるのは困難を極めるそうですが、苦労の末に入手しただけあって、その中にはコミュニケーションを円滑にするためのヒントがいっぱい。
今回は、「ほめる」がテーマ。親が子をほめる、上司が部下をほめる、恋人がパートナーをほめる──。果たしてそれは、相手に正しく伝わっているでしょうか? その「ほめ」に裏の意図がある場合、相手は案外、そのことに気づいているかもしれません。田房永子さんの漫画とともにお楽しみください。
イラスト・漫画/田房永子
記事が続きます
ポジティブなことばだからといって「ほめ」ているとは限らない
「ほめる」という行為は、一般に「良いこと」と考えられている。「子ども/部下をほめて育てる」というフレーズを耳にすることも多く、普段から「人をほめる」よう心がけている人も多いのではないだろうか。
しかし、「ほめ」をコミュニケーションの中で考える際に必要なのは、しばしばHow to本などで取り上げられているような、「いつほめるか(状況)」「何をほめるか(対象)」「どのようにほめるか(表現)」、というほめる側の視点だけではない。むしろ考えるべきは、相手がどう捉えるか(評価)、つまり「ほめ」が「ほめ」として機能しているかどうか、だろう。
相手に関してポジティブなことを言いさえすれば、必ず「ほめ」として機能し、相手を「嬉しい気持ち」にさせることができるかといえば、そうとは限らない。「かわいいね」と言われて、素直に「ありがとう」と受け取れることもあれば、「本気で思ってるの?」「なんかウソっぽいな」と感じてしまうこともある。
今回は、「ほめ」がなぜ時にうれしく、時にうそっぽく、またわずらわしく感じられるのかを、「関連性理論」と呼ばれる言語理論を手がかりに考えていきたい。
※以下の会話は、当事者の了解を得て掲載しています。
女性:智美
男性:隼人
(共に30代前半・仮名)
今回は、30代前半の恋人間の実際の会話を題材として扱う。彼女・智美が、彼氏・隼人の一人暮らしの部屋を訪れた場面で、隼人は智美が遊びに来ているにもかかわらず、パソコンで仕事を続けている。
(注)
・「、」は短い「間」を表す。
・「//」は、次の発話が割り込まれた位置を示す。
・「?」は疑問ではなく、音の上昇を表す。
――1.0秒の間――
――1.0秒の間――
――1.0秒の間――
――2.5秒の間――
――3.5秒の間――
このやりとりで、隼人は智美に「かわいい」という「ほめ」を繰り返している。しかし智美はそのたびに「かわいないしそんなんゆわんでいいよ」(智美4)、「なんなんほんまそれ(呆れた調子)」(智美6)と返答したり、沈黙したりしており、隼人からのほめが肯定的に受け止められている様子はない。「かわいい」という、彼女に対するいわば愛情表現ともいえる発言が、当の彼女に効力を持たないどころかむしろ否定的に捉えられているようである。
「ほめる」側に求められること
関連性理論(Sperber & Wilson, 1986)は、「人はできるだけ少ない労力で、できるだけ多くの意味のある情報を得ようとする」と考える言語理論である。
これによると、私たちはある発話を解釈する際、その発話がなされた状況や文脈、前提知識などに照らし合わせて、最も意味のある(関連性の高い)推論を「発話の本当の意味」として選択するという。
関連性理論では、ある発話が聞き手にとって意味があるように感じられるためには、そこに「文脈効果」が必要であるとされる。文脈効果とは、刺激の知覚や認知が、その刺激が置かれている状況や前後関係(文脈)によって変化する現象のことだ。たとえば、ある人が新しい髪型にした(=刺激)直後に「似合ってるね」と誰かに言われた(=認知の変化)なら、それは明らかな文脈効果のある「ほめ」だといえる。
しかし、隼人の「かわいい」は、何の変化もない平常時に、しかも繰り返し登場する。何ら新しい情報を提供していないため、智美の認知環境(今何が起きているか)を変える効果がない=発話の内容(「かわいい」)自体に価値がないのだ。
もし隼人が本当に智美を「かわいい」と思っていることを伝えたいのであれば、彼女の認知環境を変化させるために何らかの新情報を出すはずだ。関連性理論では、聞き手は与えられた情報からしか推論できないので、意味が伝わらないのは話し手が「伝わるような工夫」をしていないからだとされる。ほめる側は相手に納得させるために用いる表現を変え、ことばを尽くす姿勢を示す必要があるのだ。
それが欠けているために、智美は「何のために彼はこの意味のないほめを繰り返すのか」と、発言の裏側にある隼人の「真意」を、状況に照らし合わせて推測することになるのである。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)