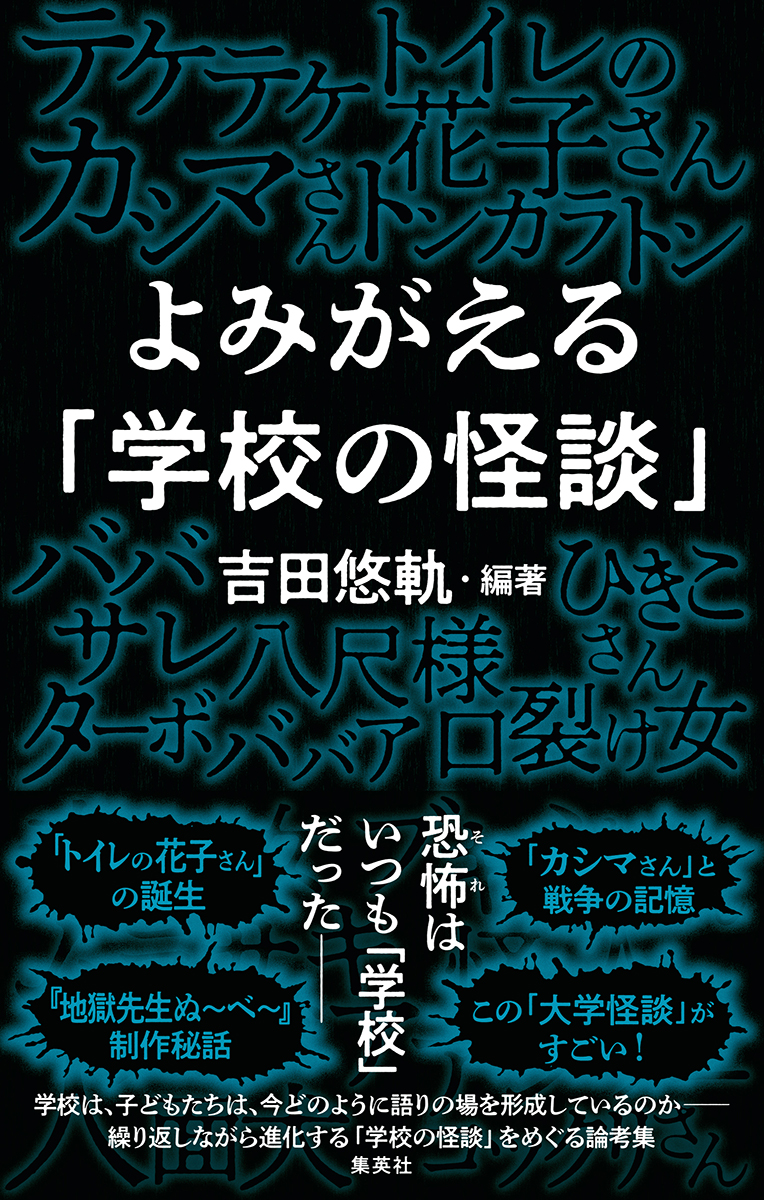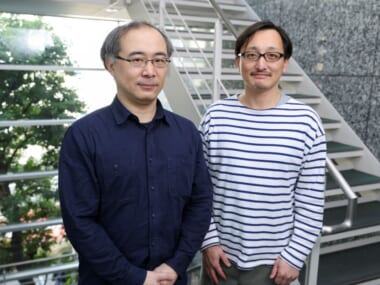2024.7.17
意外と快適……4畳の通称〝豚小屋〟での東京ライフ 第15話 南米へ行くためのアルバイト
『まじめな会社員』で知られる漫画家・冬野梅子が、日照量の少ない半生を振り返り、地方と東京のリアルライフを綴るエッセイ。
前回は、冬野さんが東京の大学へ進学することになった紆余曲折の経緯についてでした。
上京した冬野さんは、女子寮に入ることになり……。
(文・イラスト/冬野梅子)
第15話 南米へ行くためのアルバイト
大学生になった。
私は大学生活も、東京生活もやっていけるのか本当に不安だった。というのも、関東に住む従兄弟が大学を留年した時は、お盆か法事かで叔父の家に集まった親戚一同から呆れられたり説教されたり、または優しくフォローされたりと大注目を浴びていたのだ。挙句、それらが一段落した深夜に、ベロベロに酔っ払ったうちの父から「おめ、な? 親さめいわぐかげんな? な? いいが? 大学ってのは」と呂律の回らない酒臭い息でダラダラと絡まれていた。大学留年、大学中退、そんなことになれば次にこの説教プレイの標的になるのは私だ。しかも我が子なんだからもっと盛大に演目を披露できる。うちの父が威厳を示す手段は子供への説教と決まっているのだ。そう思うと絶対に大学生活で躓きたくなかった。
さらに別の従兄弟は、高校卒業後に関東の飲食店に就職し、ストレスからかじんましんが絶えず、程なくして地元に戻っている。このエピソードはいつも「(じんましんを掻きむしって付いたであろう)血まみれのシーツを叔母さんが洗濯してあげたんだど!」というセリフで締め括られ、しばらくは悲惨な上京物語として語り継がれた。ああ、東京は怖いとこだ。
そんな田舎者の心を見透かしてか、大学から送られて来た入学手続きの資料には、大学と提携する女子寮のパンフレットが同封されていた。それはさまざまな大学の学生が住む女子寮で、朝夜の食事付き、家具付き、門限23時、月7万円未満の施設である。一人暮らしがしたかった私はあれこれ理由をつけて寮の懸念点を述べたが、母は聞く耳も持たず即決。
私も金を出してもらう身なのでスポンサーには逆らえない。そうして4畳の縦長の部屋で新生活が始まったのだった。
幸いにも、隣の部屋は同じ大学の1年生で東北出身の子が入居しており、仲良くなるのに時間はかからなかった。地方出身者ばかりが集まるボロい寮では、誰しも簡単に親しくなれた。
記事が続きます
予想に反して寮生活も大学生活も、思ったより順調だった。私の入学した学科は、他の学科を受験しつつ滑り止めで受ける人が多く、本当は別の学科に行きたかったと堂々と話す人や、来年には他の学科を受けると言う人、早々に退学する人もいた。やる気に溢れる人も中にはいたが、多くの学生は何か妥協してここにいるようだし、他学科に移るなどの行動を起こさない人が大半だった。そんな雰囲気のせいか、希望通りの大学ではないということなんか簡単に忘れた。必須科目の中に興味のあるテーマもないし、選択制の科目で選んだスペイン語の授業くらいしか面白味を感じないが、大学という環境そのものが楽しいので問題なかった。高校と違い学生が放し飼いのような雰囲気であること、先生も学生を管理することに興味がなく粛々と授業を行うこと、基本的に学生の自主性に任せられていることが新鮮だった。高校生までは、スカートの丈や髪の毛の色にあんなに厳しかったのに、大学という場所に移っただけで突然そんなものは霧散する。
一応友達もできたが、授業が終わればみんなバイトに行ったり家に帰ったり、バラバラに行動することが多く、大半の時間を一人で過ごす人も珍しくない。時々、友達といても何を話すべきか悩んでしまう私のような人にとっては、単独行動が当然になる生活は気づまりする瞬間を避けられて都合が良かった。そして何より、親元を離れたこと、それだけで楽しい。これまで、都会に行って病んでしまう人、一人暮らしが寂しくて耐えられない人、家事が疎かになって生活と健康に支障が出る人、そんな話を山ほど聞いてきたが、そんな気配は一切ない。自分でもびっくりである。何日経っても何ヶ月過ぎても実家が恋しくならない。あれはそもそも、家族仲がものすごくいい人に限られた話なのかもしれない。ホームシックなんてもってのほか、通称“豚小屋”と呼ばれる狭い部屋でも、実家と違って突然誰かが入ってくることのない鍵付きの部屋というだけで心からリラックスできた。
記事が続きます
当時の私は東京に来たらやりたいことが一つあった。それは、「大人計画」の舞台を観ることである。別に舞台に詳しかった訳でもないが、私は上京する直前の春休みに、録画した『木更津キャッツアイ』をずっと観ていた。地元では東京より2週間ほど遅れて放送されていたが、私は全話録画してシナリオ本も購入し、本の中で言及されていた映画『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』もレンタルで観るくらいにはハマっていた。おそらく、その本に書かれた宮藤官九郎のプロフィールから大人計画を知ったのだろう。東京では本人の出演する舞台が観られる。目の前で、本人が、同じ空間に……そんなことある? 東京ってすごい!と、こればかりは本気で感動したものだ。それを思い出し携帯で調べてみると、本当にある。下北沢の本多劇場で行われるそれは、まだチケットも購入できるようだった。しかし、高い。チケット代は5000円前後だったと記憶しているが、当時の私には高かった。てっきり3000円くらいかと思っていた。今なら即決で購入している額だが、その頃はまだアルバイトも始めておらず、仕送りも、(自分名義の口座から自由に下ろせる状態だったが)親の目を気にして月2万円以上は下ろさないように気をつけていたので5000円は高い。私はいとも簡単に舞台を観る夢を諦めた。
さて、東京に来た地方出身者がだいたいみんな経験することだが、私も密かにカルチャーショックを受けたことがある。その一つが、東京(関東近辺も含む)の人にとって美術展は何ら特別ではないこと、だった。あるランチの時間、同じグループにいる千葉の実家から通う子が、お母さんとゴッホ展に行ったと話し、それを聞きながら私はとても不思議な気持ちになった。彼女はお洒落で可愛く気さくな子で、将来は食品メーカーで開発をしたいと話しており、特段美術が好きというわけでもなさそうだった。そう、美術が好きかどうかに関わらず、東京の人はごく当たり前に美術展に行くのだ。日常生活の中に当たり前にゴッホ展という選択肢がある。
私も中学生の頃に母とゴッホ展を見に行ったが、それは計画を立てて、新幹線や寝台列車の安い時期を狙って、ゴッホ展を目指して上野に行くのだ。母も私も、特段ゴッホが好きというわけではなかったが、小学生の頃はよく家にあった画集のようなものを眺めており、西洋絵画が好きなつもりだった。厳密には画集ではなく、新聞社の企画で月に2枚、A4サイズくらいの絵が送られて来るのを母がファイリングし保管していたものを眺めていた。ルーブル美術館の年もあれば、オルセー美術館の年もあり、3年くらいは熱心に集めていたと思う。それを見ながら、母と絵の当てっこゲームをして、これはマネ、こっちはモネ、ルノワール、セザンヌ……と有名な印象派の絵を言い当てる遊びを楽しんでいた。そして子供心に、自分はなんて絵に詳しいんだと誇らしい気持ちになった。
そういうわけで、絵が好きでわざわざ美術展に足を運ぶということは特別な一大イベントで、ついでに自分が凛とした人間になったような気持ちにさせてくれる、数少ない大切な行為だった。それが東京では別に、わざわざ目指して行く場所ではない。ちょっとした教養の一環というか、たしなみというか、みんなとの話題づくりというか、軽い気持ちでいつでもいけるのだ。その後、就職してもっといろんな人と接することで、東京にいても美術展に行かない人なんてざらにいると知るのだが、この時は、自分が熱量を持たないと行けない場所、知ることのできないものが、東京の人にとっては身近なありふれたものということに、心がザラっとした。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)