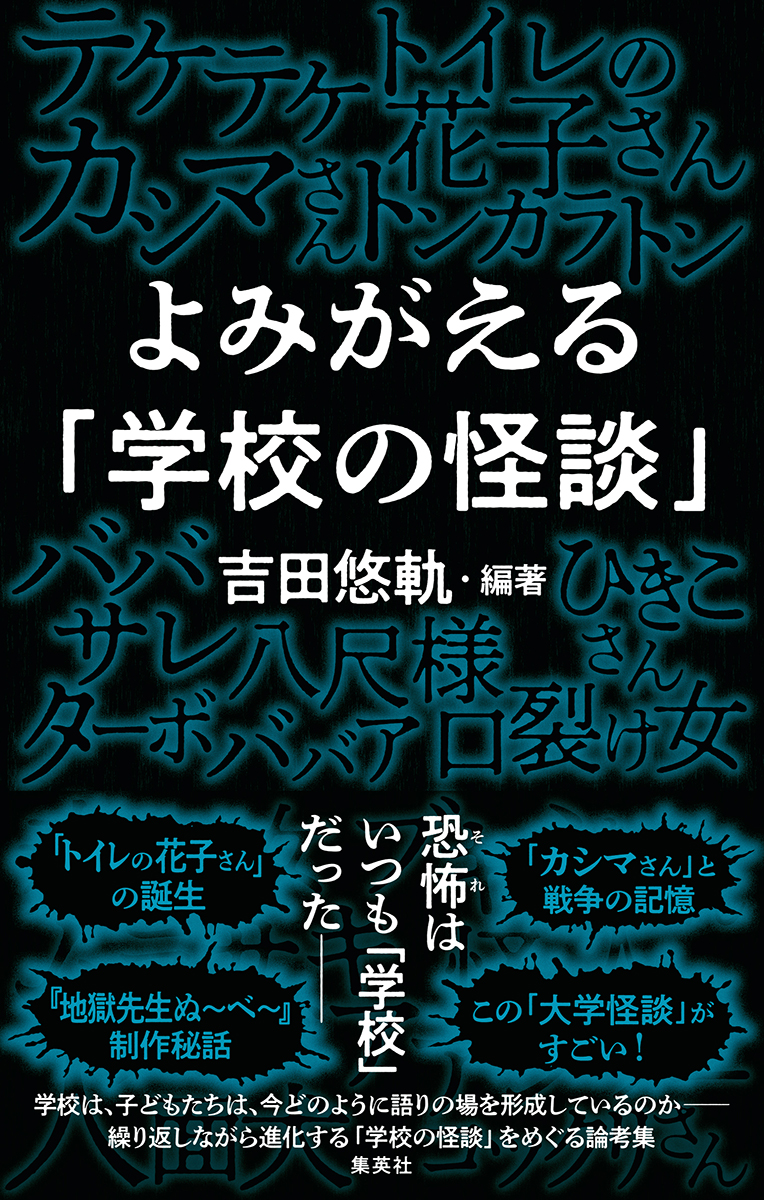2024.8.21
総合職か一般職か……ネガティブな未来予測から導いた驚きの就活メソッド 第16話 武器のない就活戦記
『まじめな会社員』で知られる漫画家・冬野梅子が、日照量の少ない半生を振り返り、地方と東京のリアルライフを綴るエッセイ。
前回は、上京した冬野さんのカレッジライフが綴られました。
アルゼンチン実習や気ままな東京生活を楽しんでいた冬野さんですが、就職活動の時期がやってきます。
(文・イラスト/冬野梅子)
第16話 武器のない就活戦記
大学時代の楽しさのピークは20歳頃と記憶している。美大に進んだ友人と音楽ユニットのcapsuleにハマり、一時期は新宿OTOで行われるイベントに熱心に通っていた。メンバーはその美大の友人と、弓道部が一緒で横浜に就職した友人、そして都内に就職したリエちゃんの4人である。毎月第一金曜の夜は新宿の「笑笑」で0時過ぎまで飲んでからOTOに出向き、知らない名前のカクテルかジントニック(なぜかジントニックが一番いい飲み物だと思っていた)を1、2杯飲み、狭いクラブで音と人に揉まれ、始発で帰ったり誰かの家に泊まったりしていた。この4人で集まっていた期間は半年ほどだと思うのだが、この時期は高校時代に抱いていたリエちゃんに対する憎しみのようなものも薄れ、私にとっては若い時間を最も楽しく過ごした数ヶ月だった。
リエちゃんは成り行きで上京した私と違い、小学生の頃から「将来は東京に行く」と言い続け本当に上京し、1年ほどで転職もして、かっこいい彼氏もできて、望んだもの全てを実現する行動力には素直に感服した。人によっては、就職して彼氏を作るくらいなんてことはないだろうが、私みたいに将来に消極的な人間は、まず就職を先延ばしにするための進学という面もあったので、働くどころか転職までしているリエちゃんはもうレベルが違ったのだ。
リエちゃんに限った話ではないが、私のいたごく普通の高校では、卒業したら就職するというのは珍しい話ではない。例えば「(兄の進学費用で手いっぱいだから)お前は就職しろ」と親から言われて育つ家というのはよくあった。もちろん、それを言われた本人は内心深刻に悩んでいた可能性もあるのだが、このような話は友人同士でもわりと気軽に共有され、それを聞いて憤りを表明したり同情したりする人もいなかったと記憶している。少なくとも、酷い話だが私はそうだった。こういうことはよくある普通の話で、私もきっと、兄や姉がいたらまず進学なんかしてないだろうし、特に反発することもなく受け入れただろう。
記事が続きます
そんな経験をしている人はバイト先のパン屋にもいた。学部は違うが同じ大学の1年生で、物事に自分なりの意見があり話が面白く、一緒にシフトに入るのが本当に楽しかった。彼女の場合は両親の関心が兄に向いており、彼女は奨学金とアルバイトで学費を賄う苦学生だった。彼女はいつも親に対して交渉や説得が欠かせず、その手腕は目から鱗だった。彼女は母親に電話する前にはYES/NOチャートを作り、想定問答を用意し、相手の出方によってそのチャートを見ながら対応を変え、どうにか自分の希望する流れに持っていけるよう慎重に誘導するらしい。それを聞いて、親に電話するのにそんなに手間をかけるのかと驚いたが、私こそ行うべき準備だと思った。その後輩は、学科は忘れてしまったが理系専攻で、小説が好きなので文学部と迷ったが、同じくらい関心のある今の学科に入ったそうだ。文系の趣味があっても自ら進んで理系を選択する、彼女のような娘だったら母も喜んだだろう。
記事が続きます
私にとって母は常に対立する存在だった。私も幼少から愚鈍な娘なので、そんな娘の選択や決断が信用ならないというのはわかる。しかも母は学校の成績が優秀で、仕事も好きだったようだ。だが、当時は結婚したら退職する時代である。結果的に自分の人生の全てを捧げて育てた娘が、明らかに犠牲に見合っていないとくれば、その落胆と怒りも今なら理解できる。しかし理解と私怨は別だ。一度だけ、私は母に仕返しをしたことがある。
大学に入って何度目かの長期休暇に実家に帰ったある日、母が「お店を出そうと思うの!」と言ってきた。なんでも、この辺りは病院が近いが飲食店が少ないので、家の敷地の一部を店にすればきっと採算がとれる、それを誰だか専門の人にも言われたそうなのだ。私は一瞬心配になったが、好きにすればいいと思った。が、瞬時に思い直した。私だって大学進学の時はこっぴどく全否定されたのだから、今度は私が母の夢を全否定する番じゃないか。高揚した表情で夢を語る母の姿にイラつかなかったといえば嘘になる。ここは冬野家だ。私の経験上、この家では夢や願望を語ることすら許されなかったはずだ。
私はその鉄則に従い愚か者を咎める口調で「本当に大丈夫なの?」と声を鋭くした。「採算が取れるってそれ本当? で? ダメだったらどうすんの? 本当に大丈夫なの? 無理じゃない? 借金とかできるんじゃない? 店なんて無理だよ、無理無理無理!」と声を張り上げ威圧した。母の悲しそうな瞳と、何か言い返したいけれど言葉がないという不満と苦しさを溜め込んだ表情を見て、私はとても満足した。この表情はいつも私がやってきた表情だ。何か言いたいけれど言っても無駄だし言うだけ惨めになる、全身を駆け巡るフラストレーションをただただ引き受ける悲しい無力感、それを今母が体感している。
母は調理師免許を持ち長年飲食関係のパートもしてきたので、店の運営で大きく失敗することもなかったかもしれない。母は食に関してだけは寛大で、そのおかげで私も子供の頃からランブータンやヤングココナッツ、手作りのスコーンなど、目新しい食べ物にありつけた。一度、ドリアンを買ってうっかり熟す前に食べてしまったことがあり、二人で味の薄さに困惑したというのは笑える思い出話となっていた。それを思い返すと可哀想なことをしたと思ったが、むしろ時間が経つにつれて新たな怒りが沸々と湧いてきた。いつも私に「自営業なんて大変、不景気になればすぐ潰れる、借金抱えて苦労するし、みんなが休んでる時休めないんだよ」と言い聞かせてきた“不幸で大変な自営業”を、母だって本当はやりたかったのだ。しかし、私もこれを真に受けて夢見ることさえ律儀に禁じてきたのに今さら覆すなんて、急に梯子を外されたような、騙されたような気持ちになった。もちろん、私のような未熟な若造が“お店屋さん”を夢見るのと、やっと子育てを終えて自分のための時間を持てるようになった母親が描く“自分の店”では後者の方が現実的だし、長年の苦労を鑑みればそのぐらいの夢でも持たないと生きる意味がない。それをわかった上での攻撃だった。私もだいぶ意地悪で酷薄な娘である。
記事が続きます
さて、大学生活も半ばを過ぎ、私は寮を出て学生マンションに住みはじめ、真の一人暮らしを満喫した。大学3年生から始まるゼミも、入学当初から目をつけていた活気ある楽しそうなところに入ることができ、人生で初めて“順調”という文字を頭に思い浮かべる。そこは先輩による面接を経て入るため、一旦この面接を受けてから他を検討しようという学生が多く、結果的に人気のゼミのようになっていた。実際は、人気があるから面接をしていたわけではなく、先生の発案で、就活が始まる3年生のために面接官を経験させたら役立つだろうという理由らしかった。しかしそれをまだ知らない私は、ここに入ることが決まると「私は面接を通過したのだ」と誇らしい気持ちになっていた。留学生や編入生も多く、皆面接があるゼミを選ぶような学生だからか、積極性と自信を感じる人が多かった。実は私がこのゼミに入りたかったのは、夜になるとお好み焼きを作ったり外国のお菓子を持ち寄ったり、美味しそうなものに溢れているのを見かけて楽しそうだと思ったから、というしょうもない理由だった。それでも、なんだか周りがやる気に溢れていると自分も元からそんな人間だったかのような気分になる。このゼミに入ったことで学祭の屋台を出店することになったり、みんなでタイに行ったりと学生らしい青春も味わい、私って意外とアクティブな一面があるんだな、なんてどんどん自分を誤解していく。
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)