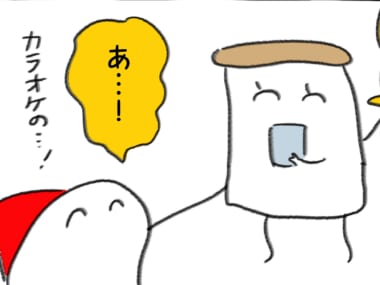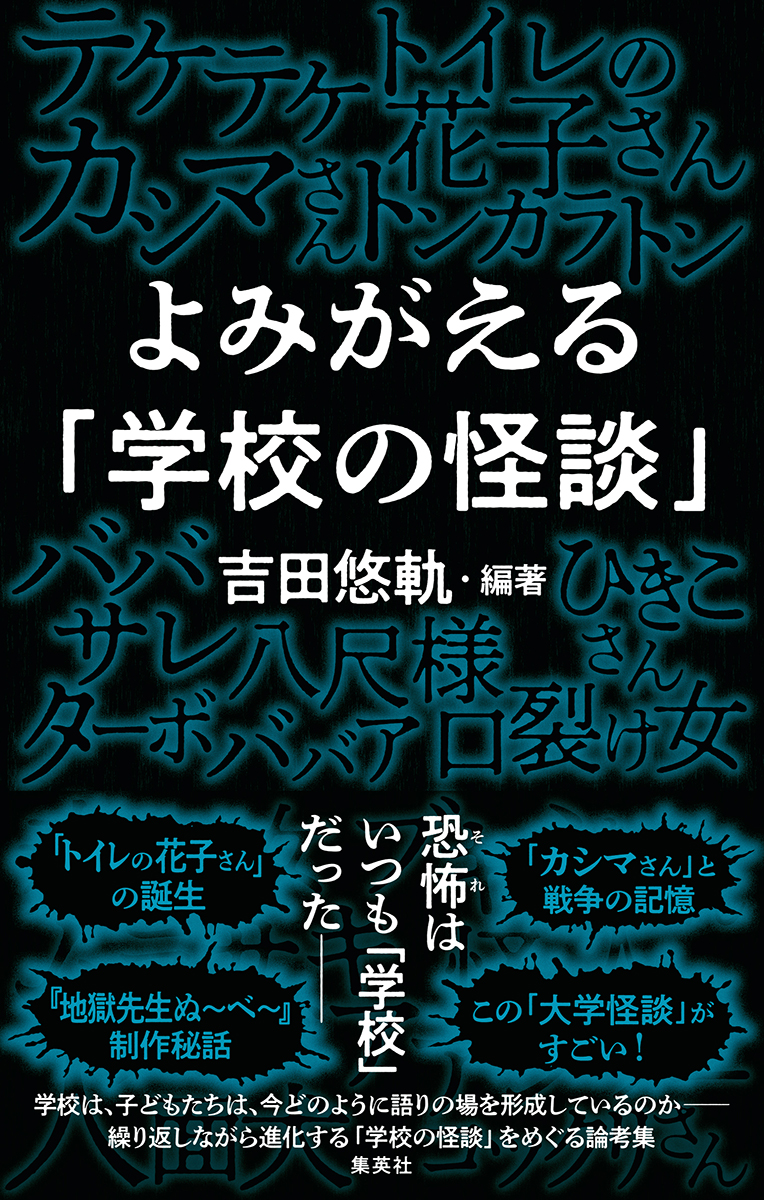2024.6.19
「英語なんて勉強してなんになる!」娘を栄養士にしたい母との攻防戦 第14話 進路希望という名の絶望
『まじめな会社員』で知られる漫画家・冬野梅子が、日照量の少ない半生を振り返り、地方と東京のリアルライフを綴るエッセイ。
前回は、無理やりメル友を作り、恋愛しようと悪戦苦闘した女子高時代の経験が明かされました。
そんな冬野さん。進路を決めるにもかなり後ろ向きな事情があったようです。
(文・イラスト/冬野梅子)
第14話 進路希望という名の絶望
映画を見る合間に気が向いたら部活に行く、そんな穏やかで気楽な生活はそう長くは続かなかった。部活内でつるむことの多かった友人が辞めてしまったのだ。
発端は、私たち2年生が3年生の悪口で盛り上がっていたことが本人たちにバレてしまった事件である。もともと部活内の空気は最悪だったのだ。私たちが入部した頃から時折言われていたことだが、「今の1年生はすぐ帰る」「本気で大会に出たいんだったら先輩たちが自主練している間も一緒に残って『撃たせてください』と申し出るくらいの気合を見せろ」などと言われており、日々ギスギスした空気は増幅していた。
そんなある日、いつものように軽く自主練をして真っ暗になった19時頃、体育館裏の用具室で着替えをしつつみんなで悪口に花を咲かせていると、一人が「しっ! 誰かいる」と窓の方を指した。私は気づかなかったが、窓を開けると道場に走って消えていく後ろ姿があったらしく、先輩に違いないと大騒ぎになった。「どうしよう?」と慌てるみんなを横目に、私と友人は「早く逃げよ逃げよ!」と促していた。ところが他のみんなは、ちゃんと謝った方がいいとか、逃げたら余計にやばくなるとか、きちんと関係を修復しようという人がほとんどだった。そうこうしているうちに先輩たちが現れ、真っ暗な体育館で、先輩たちと私たち20人ほどで大きな輪を作り怒号と号泣が響き渡ったのだった。優しいタイプの先輩は「みんなこんな状態でいいの?」と嗚咽を漏らし、気が強い先輩は「ふざけんじゃねーぞてめーら!」と殴りそうな勢いで怒鳴り、後輩陣は下を向いて謝ったり泣いたりしていた。なんとなく部内に滞留していた重苦しい苛立ちがついに爆発したといった感じで、ともかく最後は全員が泣いていたと思う。それを唖然とした表情で眺めるのが私と友人の二人だった。この出来事は二人の間でしばらく語り継がれ、「うちらだけ泣いてなかったね」とか「だからあそこで帰ってればよかったのに」と盛り上がった。
記事が続きます
それから数日して友人は「辞めちゃおうかな」と漏らすことが増え、とうとう本当に退部届を出した。私やリエちゃんなど、部活内で同じグループに属していた5、6人ほどは本気で引き止めたが、友人の意志は固く覆ることはなかった。先日の一件で分かったことだが、リエちゃんたちは案外部活に本気だったのだ。先輩たちとの関係を本気で案じていたようだし、最近は大会の補欠にも選ばれ以前より熱心に練習している。友人が辞めれば、真にやる気のない人は私一人になってしまう。死活問題だ。当の友人は、もともと美大を目指していたので「部活を辞めたら絵の練習でも始める」と前向きで、非常に建設的な退部である。引き止められない。実は私も触発されて退部を試み、「映画部にでも入ろうかな」と母に言ってみたところ、何をする部活なのかと怪訝な顔をされ、「毎週木曜に部室で映画見るの」と返すと「そんな部活入るくらいなら勉強せ!」と一喝されたのだった。当然である。今までは友人と一緒に冷めた態度で部活の根性論を笑っていたのに、彼女は将来を見据えていて私はひねくれていただけだったと気付かされた。映画『ゴーストワールド』でいえば、彼女はレベッカで私はイーニドである。結局、私は推薦入試を視野に入れていたので、面接で部活を頑張った学生を演じるためにも辞めなかった。
高校3年生になるといよいよ受験の空気が濃厚になる。私のクラスは「文系進学クラス」と呼ばれるもので、文系の四大・短大・専門学校を目指す生徒がおり、多くが推薦入試で入れる学校に進学するため受験ムードは薄く、日々の生活をきちんとこなし内申点を維持するような穏やかなクラスだった。このクラス分けは2年生になる時に行われるが、私を栄養士にしたい母とは当然一悶着あった。栄養士になるなら理系進学クラスと呼ばれる、国立の四大や理系大学を目指す成績のいい子だけが行くクラスを選択しなければならないが、まず理系の勉強に興味がないし、親しい知り合いもいないこのクラスには入りたくないので必死に説得した。「成績が悪ければ内申点が下がり、推薦をもらえない」この一言が効いたのか文系クラスに入ることができた。生まれて初めての説得である。私にとってはこの文系クラスの選択をもって、栄養士にはならないという意思表示に代えさせていただいたつもりだった。
記事が続きます
ところがある日、「おめ、勉強合宿さ行げ」と母から通達があった。勉強合宿とは夏休みに行われ、主に理系進学クラスの子だけが参加する、文字通り3日間勉強漬けの合宿である。授業も理系進学者向けの授業であり、物理などを選択していない私が今さら参加したとてちんぷんかんぷんになることは間違いないのだが……。
母は私が文系クラスであることを知らないのだろうか。とはいえ、もう部活も引退し、毎日暇そうに過ごしているのは間違いないので参加しない言い訳が見つからない。
当時の私は、映画にハマったことをきっかけに映画配給会社で働きたいと思い、そのために英語の勉強を中心とした学部に行きたいと考えていた。
ちなみに映画配給会社という存在を知ったきっかけは、深夜のテレビ番組だった。なぜ『アメリ』がヒットしたのかというテーマで配給会社が取り上げられ、配給の担当者がインタビューされていた記憶がある。そこで初めて、この世には海外から映画を買い付けて、それを日本に広める仕事があると知り、自分がまだ見ぬ映画を“発見”する姿を想像してワクワクした。これなら就職という形を経て映画に関われる。子供の頃は漫画を描いていた人間なので、当然、美大に憧れたこともあったし、映画にハマってからは映画監督や脚本家という仕事に憧れたこともある。それでもやはり、食べていけるのか、そもそもなれるのか、という壁に早々にぶち当たり、未来を妄想することもできなかった。こういう仕事にもおそらく“なり方”はあるのだが、当時は全く想像もつかず、まずは天賦の才が見出されないことには始まらないというイメージを持っていた。とりわけ10代の私は才能信仰が強く、芸術分野はもちろんだが、運動や勉強も才能がものを言い、才能がなければ恐ろしく時間をかけてお金をかけて努力しても、かけた分の元は取れない。そして費やした時間やお金を回収できなければそれは“失敗”であり、その失敗も一過性のものではなく、何か人生そのものへの烙印のように半永久的に引きずる重荷だと思っていた。だから不確定なものに時間やお金をかけることを忌避し、自分には勉強の才能がないことを言い訳に、今の自分の成績でも入れそうな大学に行こうと目星もつけていた。
それでも英語を勉強しようと思ったのは、映画にハマり始めてから英語の成績が上がったこともあり、自分には語学の才能があるのかもしれないと思ったからだった。が、そんなことは両親には言っていない。私が理系の勉強も、高度な勉強も必要としていないこと、そして映画配給会社で働くために英語を勉強したいことも。そして、この勉強合宿に参加させるということは、栄養士の夢も捨てていないということだ。
母は私を産む時に会社を辞め、以降は給食のパートなどをしつつ調理師免許を取り、老人ホームの調理場やレストランの調理場などでパートをしていた。その過程で栄養士と関わることもあったらしく、ある時から「ただの栄養士じゃなく管理栄養士になりなさい」と日々言われるようになっていた。その度にうんざりしながら何も言わず渋い顔をしてやり過ごすことで争いを先送りにしてきた。そして今回も、私はなるべく揉めたくなかったので渋々参加することにした。ほぼ知り合いのいない中で、食事をし、共用の風呂に入り、あまり誰とも喋らず、食堂では幽霊のようにぼんやり存在し、耐え難いほどに意味不明で退屈で、ついていけない授業の時間が過ぎるのをひたすら待った。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)