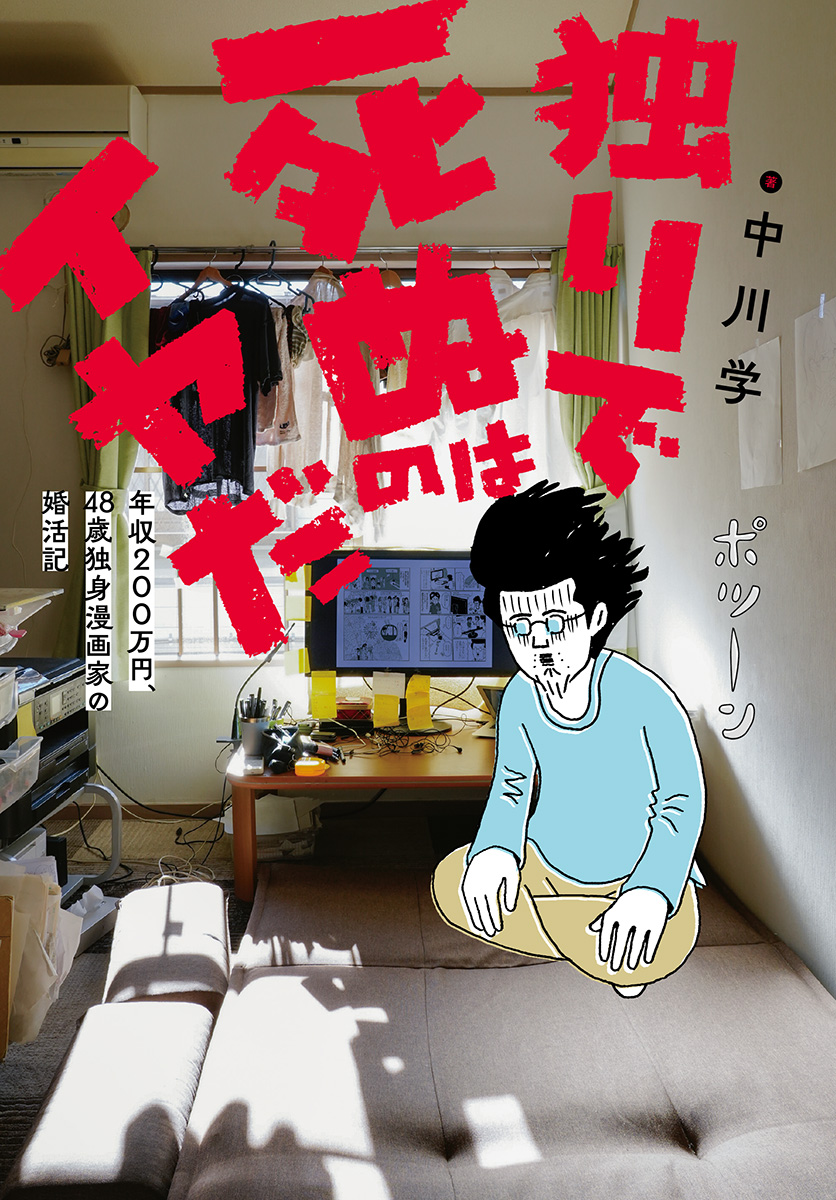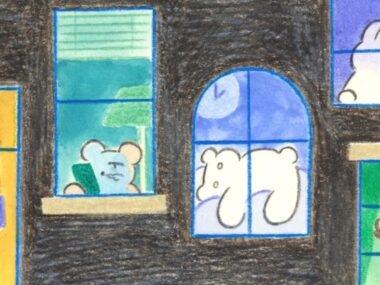2024.8.6
かつて虐待してきた母親は「弱者」になっていた【育ちの良い人だけが知らないこと 最終回】
前回は、かとうさんの恋人が投資詐欺で逮捕されたエピソードを綴りました。
今回でついに連載最終回。かとうさんの「育ち」と切っても切り離せない、「虐待」というテーマです。

記事が続きます
避けては通れない「虐待」の経験
目を覚ましてもすぐには起き上がれない日がある。
目を開いたまま、枕と反対の壁側にかけてあるモスグリーンの時計を見つめ、激しく脈打つ心臓に手を当てながら息を整える。そのまま数分を布団の中で過ごしてから腕の力で身体を起こすと、足元でまだ眠っている愛犬の身体に顔を埋める。
それはほとんどの場合、猛烈な悪夢にうなされた翌朝だ。
動悸が激しく、額と背中が汗ばんでいる。深夜、何かを叫び、その自分の声で一度起きた記憶がうっすらとある。これは度々起こることなのに、その苦しさに慣れることはない。
この連載が始まり、私自身の「育ち」と向き合って半年近くになる。
第一話を書き始めたときにはこの「育ちの良い人だけが知らないこと」というテーマをどのように締めくくるのかを全く想像できなかった。
だが回を重ねるごとに底しれぬ己の育ちの闇深さと向き合うことになり、おそらく「育ち」との決着をつけるにあたって避けては通れないのが虐待を受けた経験なのだろうということが少しずつ現実味を帯び始めた。
それは疑う余地もなく育ちが良くない自分自身のルーツである。
一言だけ先に申し上げておくと、この原稿は身の上の不幸を書き連ねるものではない。
得られなかった愛情や社会を恨むのではなく、恥ずかしい黒歴史を作りながらも、いつだって幸せになる方法を模索している。
記事が続きます
「うちの親はおかしい」となかなか気づけない
私の「育ち」と決着をつけるために「育ちの良い人」に擬態する以前の話をしよう。
自分が幼少期に虐待を受けていたと気がついたのは高校を卒業して家出をした後のことで、それまでは母親のことを「我が家にはよくキレる情緒不安定で教育熱心な女がいて私の世界を牛耳っている〜!」くらいの認識しかしていなかった。
被虐待者が「自分は虐待を受けている」と気がつかないケースは多いという。「うちの親はどこかおかしい」と気がつくのに時間を要するし、他の親と比べてみてそこに気がついても第三者に助けを求める選択肢がなかったり、他と違うことは恥ずかしく感じて隠そうとしたりする。
2000年に児童虐待防止法によって児童への虐待の禁止や虐待した児童を発見した場合の通告の義務が生まれたが、それは治安の悪い地方エリアにはすぐに影響を与えるものではなく、児童も大人も問題意識が高いようには思えなかった。
私の住んでいた地域では教師ですら2010年前後の時点で校門に竹刀を持って立っており、暴力を匂わせるような脅しもあったがそれを教育委員会に通報する親はいなかったのだ。
通っていた公立中学校のクラスメイトの中には何日もお風呂に入らせてもらえないせいか、いつも髪の毛のふけが肩に溜まっていたり酸っぱい匂いがする女子がいたし、いつも痣だらけだった男子がある日母親をボコボコに殴り倒し救急に運ばれたという噂もあったが、当時そこに学校や福祉が介入するといったことはなかった。
そんな話に比べれば母親が私に浴びせる暴言や暴力は酷いものではなかったし、毎日ご飯が用意されて温かいお風呂に入り自分の個室で眠ることだってできた。
母の平手打ちによって額が壁にぶつかり腫れてしまったり、雪が積もる夜に靴を履かせてもらえないまま外に一時間放置されたりするといったことも度々あったが、それを虐待と思わなかったのはやはり育った環境、「育ち」から生まれた。
泣き声や大きな物音、両親が罵り合う大声が特別なものではなく通報されることがない環境では、それらは日常の何気ない一コマに過ぎないのだった。地域というコミュニティが上手く機能していない典型である。
中学生のころ『Itと呼ばれた子(幼年期)』(デイヴ・ベルザー著,ヴィレッジブックス)を読んだことも影響した。この著者がガスコンロで焼かれたり赤子の汚物を食べさせられるなどの虐待を実親から受けていた描写があったのだ。
この著者に同情することで「自分の境遇は不幸ではない、自分の親は優しい時もあるのだから」と考えたことを覚えている。
自分よりも恵まれない存在を憐れむことで、自分は不幸ではないのだという安心感を得ていた。
母の爆発は予想できないため家は常に緊張感に包まれ母の機嫌を伺いながら生活していたため、私は自分を責め続けた。
いくら勉強しても習い事を頑張っても「ダメな人間」で「恥ずかしい存在」だと繰り返し刷り込まれていたため、いつしか死にたいと言い始めるようになった。初めて自殺を考えたのは小学4年生で、住んでいたマンションの最上階に何度も足を運んだ。
『毒親の正体――精神科医の診察室から』(水島広子著,新潮新書)を読んで感じたのは、私の母はASDかつ、不安型の愛着スタイルの可能性が高いということだ。
子供をコントロールしたがり、それが思うようにいかなかったり予想と違う反応があったりするとパニックになって反射的に私を怒鳴りながら物に当たり、時折手を上げるといった有様は理想の母親像からひどくかけ離れていた。
時々母は突然優しくなって、怪我をした部分に砂糖を水で溶いたものを塗ってくれた。
「こんなことをさせないで」とか「ごめんね」とか「大好き」と言いながら頭を撫でてくれる。おばあちゃんの知恵袋だという砂糖水は、患部に塗ると腫れが早く引くと母親は繰り返し私に伝えた。
母が砂糖水を塗ってくれるとき、私はちゃんと愛されてるのだと実感するのだった。紛れもなくDV加害者と被害者の関係だ。
実家を整理しているとき、父親が撮ってくれた私の成長記録ビデオを見つけた。
「2歳・誕生日」と書かれたビデオを再生すると、初めてのバースデーケーキを目の前にしながら、私は悲しそうに俯いていた。ちっとも嬉しそうではない私を見て「悪い子だったからさっきお母さんに叩かれたんだよねぇ」という母親の猫撫で声が録音されていた。
その言葉を気にも留めない父も含めて、当時既に家族の関係は歪んでいた。
母は毎日父のことをダメな人間だとか臭いとか気持ち悪いとか言ってこき下ろしていた。父の味方をすると「父と出て行け」と冷たくされる。
目の前で父と罵り合うのはほとんど毎日のことで、母に嫌気がさした父はお酒を飲んで帰宅が深夜になった。私は父に対して「私に母を押し付けて逃げた!」と恨みがましく感じた。
それでも親に愛されるために必死で愛される努力を重ねていた。
どんな受け答えをすれば母を喜ばせることができるのかにリソースを割き続ける私の思考や行動は子供らしい愛らしさからはかけ離れていたようで、文句はつけられても可愛がられた記憶はほとんどない。
私が「良い子」なら母は怒らないのだと思い込み、勉強や分担されている家事や笑顔で母の愚痴を聞くことを努力した。しかしどれだけ努力しても母の加害の矛先は私に向かった。
中学生になるといつでも死ねるようにと首を吊る用のベルトをクローゼットに隠し持ち、高校生になると抗精神薬や眠剤をジップロックに入れて集め始めた。それらはネットで知り合った女の子が「効かないから」とプレゼントしてくれたり、第2話で登場した葵が先輩からもらったりしたものを横流ししてもらったりしたものだった。
ジップロックがパンパンになったらそれを一気に飲んで死のうと思っていたが、その考えを安定剤として私は生きることができた。
転機となった男性との出会い
転機となったのは高校生になってから出会った8歳年上の男性だった。
当時既にシラフでいられず年齢を詐称して飲んでいたお酒の席で出会ったのだが、愛されるために自分の価値を提供することに疲れ切っていたとき、初めて否定をされることなく存在を受け入れてくれた人だった。
その関係は男性の下心から始まったものだったが、私はその男性にどっぷりと依存すると彼が一人暮らしをする部屋から学校に通ったり通わなかったりした。
当時東京に単身赴任をしていた父は私の変化に深入りせず、母は毎日100件を超える着信や「帰ってきなさい」という内容のメールを私の携帯電話に残した。罪悪感などは一切なく、煩わしいだけだった。
家に連れ戻されても翌日には「学校へ行く」と言ってそのまま男性の家に戻った。
それを続けていると「世界って意外と家の外にあるんじゃないか」ということに気がついた。
生活は大変だろうという漠然とした不安にさえ打ち勝つことができれば家を出ることは可能だった。
大学に行くことや就職をすることよりも親から離れて生きることが私の最優先事項となった。生きるためである。
そして同級生たちが将来や目標のために勉強に励んでいるときに、アルバイトと貯金を始めた。
あの頃身近に「トー横(新宿東宝ビルの横)」が存在していたら、私はそこに入り浸っていたことだろうことは容易に想像がつく。
未成年がアルコール度数の高いお酒や薬を乱用しているという画像や投稿を見るたび、他人事とは思えない。だが、そこから抜け出す選択をするのは本人の意思でしかない。
本人が選択をしないのなら、どんなに強制的に立ち退かせたり一時的に保護したりしても意味がないのだ。
長い時間をかけて愛を与え続けられる大人がいないのなら、彼らは傷を舐め合う方が心地が良いだろう。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)