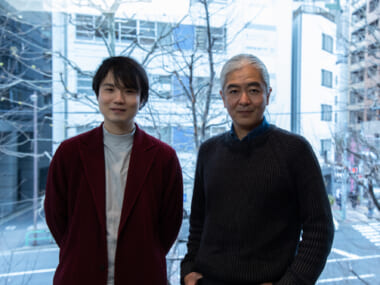2024.10.2
豊かなクオリアとしての「純粋経験」──立命館大学准教授・石原悠子インタビュー
「純粋経験」
西田哲学は難解なのですが、特に重要な「純粋経験」という概念があります。この言葉は西田が米国の哲学者であるウィリアム・ジェームズ(1842~1910)から借りたものですが、西田が言う純粋経験とは、主体と客体が未分化の、純粋そのものの直接経験ということです。
よく意識をめぐる議論で「赤い色を見ている」という経験が出てきます。これは通常は、「私」という主体が、「赤い色」という客体を見ている、と解釈されています。主体と客体があることが前提になっているんですね。
しかし西田は、それは根本的な経験ではないと言うのです。主体と客体が分離した経験とは別に、もっとファンダメンタル(根本的)な、主体と客体が一体化した経験があり、それが純粋経験であると彼は言います。
西田が挙げた純粋経験の例としては、「崖を必死で上るとき」というものがあります。危険な崖を必死になって上っているときは無我夢中ですから、「崖を上っている自分を観察している自分」はいない。そこにいるのは「崖を上っている自分」、もっと言えば、「崖を上っていること」だけである、というのが西田の主張です。西田は他にも、熟練した音楽家が楽器を奏でている状態を純粋経験の例として挙げています。
私はそういう西田の主張を読んだのですが、正直に言ってよくわからなかった。主体と客体が分かれているのは、科学に限らず近代のものの考え方の前提ですから、そうではない世界があるというのが理解できなかったんですね。しかしある日、純粋経験を理解する日が来ます。

記事が続きます
当時の私は筑波大学のそばに住んでいたので、徒歩で大学に通っていました。その日もいつも通り図書館で西田の本を読み、わかったようなわからないような気になりながら夕方、家に帰ろうとしていたのですが、いつもの道の信号待ちでふと道路わきにあった街路樹を見たときに、「純粋経験」がやってきたのです。
その横断歩道は毎日通っていた道ですから、私がそのとき見た街路樹も、見慣れたありふれた木です。つくば市は歩道が整備されていますから、街路樹はいくらでもあります。特別なものではありません。
しかし、その日、そのときのその木は違いました。いつもその木を見るときは「私が木を見ている」というふうに主体としての私と客体としての木が分かれていたのに、その瞬間は違う。「木そのもの」が経験されたのです。
この経験を正確に言葉にすることは不可能です。近い表現を試みるなら、「私が」「木を」見ているという主客の区別がなくなり、何度も見たはずのその木がとてもビビッドに、リアルに感じられたということになります。
ただ、そんな生ぬるいものではないですね。私は茫然として、しばらくそこに立ちすくんでいたと思います。涙が出ていたかもしれません。
私はこうして、主客未分の経験というものを知りました。西田の言う純粋経験です。
私=経験が起こる場所
こう言っても、ちょっと納得がいかない方が多いと思います。主客が未分の経験があるとしても、それを経験している「私」はどこにいるのか? という疑問が成り立つでしょう。
たしかに、「純粋経験をする私」という存在を考えることはできます。ある日のつくば市で立ちすくんだ私のように。
ただ、それは客体に対する主体ではないんですね。後に西田は、「純粋経験が起こっている場所そのものが私」なんだ、という主張をします。これを「場所的自己」と呼ぶのですが、つまり、あるものに没頭しているときの「私」はそのものと一体化しているということです。「私」が消えていなくなったわけではないけれど、「私と対象」という区別が消えているということです。
どうしても話が抽象的になってしまうので私の経験に即して話すと、普段、つくば市の街路樹を見ているときは、「私が」「木を」見ている、という感覚がありました。しかし純粋経験が起こったときは、両者の区別がなくなり、私と街路樹が一体化していたということです。西田はよく「物となって見、物となって行う」という表現をしますが、ある意味で私が木そのものになっていたんですね。
くり返し言うように、そのとき「私」が消滅したわけではありません。でも、そのときの「私」は、主客が分離していたそれまでの「私」ではない。西田は、純粋経験が生じているときの「私」は、「純粋経験が生じている場所」だと言っています。「私」が主客を包み込むのです。
西田は、「私」とは本来そのように、純粋な経験が生じる場であると主張しています。主体と客体は、あくまで自らを内省することによって分離されるもので、元々はそうではないのだと言うんですね。
豊かなクオリアとしての純粋経験
「純粋経験」という体験を言葉で説明することはできません。言葉にするという行為そのものが、主体と客体を区別することを要請するので、無理な相談なのです。
しかし、今の私が関心を持っている意識研究の概念を使うと、純粋経験を別の角度から伝えることができるかもしれないと思っています。
意識の質のことをクオリアと呼ぶならば、純粋経験は通常の経験とは異なり、極めてリッチなクオリアなのです。どのくらいリッチかというと、大学生だった私がつくば市の交差点で涙ぐむくらいです。あまりにリッチすぎて危険なくらいです。
だから、私たちは普段、さまざまな「色眼鏡」をかけることで経験のリッチさをそぎ落としているようにも思います。「街路樹」という言葉も一つの色眼鏡です。
でも、ふとした瞬間に、対象に向けていた色眼鏡が外れるような経験をしたことがありませんか? たとえば、何かのきっかけで、長く付き合ってきた知人の意外な一面を知ることができたとき、「あ、今までの自分は色眼鏡をかけてこの人を見ていたな」と感じることがありますよね。あの感じに近い感覚です。
人間は多面的で複雑なのに、普段は色眼鏡をかけることで「このひとはこういう人/あのひとはああいう人」と、リッチさをそぎ落としていますよね。しかし、ある瞬間にその人の全体が、とてもリアルに感じられる。そのときは、いつものように斜に構えて相手を観察している「私」はいなくなり、何らかの意味で相手と一体化していたりしないでしょうか。
そして多面的でリアルなのは他者に限られません。一個のリンゴも、つくばの街路樹も同じです。そしてその極めてリッチなクオリアを純粋経験できたときには、「対象」と「私」の区別がなくなり、私は純粋経験が起こる「場」に変化します。豊かなクオリアが、「私」の定義を変えるんですね。ただ変化すると言っても「私」という場所がそこで初めて登場するわけではありません。「私」という場所はつねにあります。普段はいろいろなモノや人と区別した「私」という存在にばかり目を向けていてそれに気づかないだけで。
純粋経験と意識研究
私の、「私」をめぐる探究の旅はここまで来ました。
冒頭で言ったように、今の意識研究では「意識とは『私を見ている私』である」という、主体と客体を分けて考える高階理論が前提になっています。もちろんそういうクオリアもあると思うのですが、高階理論を前提にしてしまうと、そこで行われるのはクオリアについての説明ではなく、「クオリアについての説明についての説明」になってしまうように思います。
私の立場は異端かもしれませんが、主客未分の純粋経験を想定する西田哲学を意識研究に応用し、さらに他分野の研究者の皆さんと協同できれば、新しい知見を加えられるのではないかと考えています。
私を含めた研究者も「色眼鏡」にとらわれがちです。とくに学際的な意識研究では、色眼鏡から自由になれる西田哲学の現代的な意義は大きいと思っています。
次回連載第4回は11/6(水)公開予定です。
石原悠子(いしはら・ゆうこ)プロフィール
2010年筑波大学を卒業。2013年京都大学大学院文学研究科を修了し、2016年にデンマーク・コペンハーゲン大学で博士課程修了。その後、アメリカ・プリンストン高等研究所の招聘研究員、東京工業大学地球生命研究所の研究員などを経て、2019年に立命館大学グローバル教養学部に着任。現在は同学部の准教授。
京都学派の哲学や現象学を主な専門分野とし、近年は「遊び」の哲学を研究テーマとしている。2024年1月に、アメリカ・バークレー仏教寺院で長年仏教や道教を教えているSteven A. Tainer氏とIntercultural Phenomenology: Playing with Reality(Bloomsbury社)を共著。日常における私たちの様々な色眼鏡をいったん「判断停止」(エポケー)してみたらもっと世界、実在がよりよく見えるのでは?(それを”playing with reality”=「実在と遊ぶ」と呼んでいる)という提案をする実践書。現象学の方法論であるエポケーを援用しつつ、西田幾多郎や禅の思想、また日本古来の自然についての考えなどを織り交ぜながら、最終的には主客の二元論のエポケーへと誘う。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)