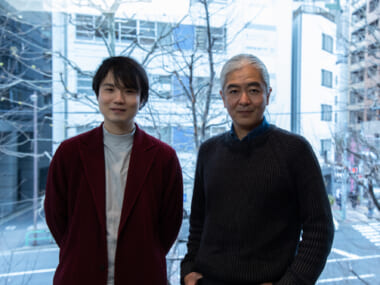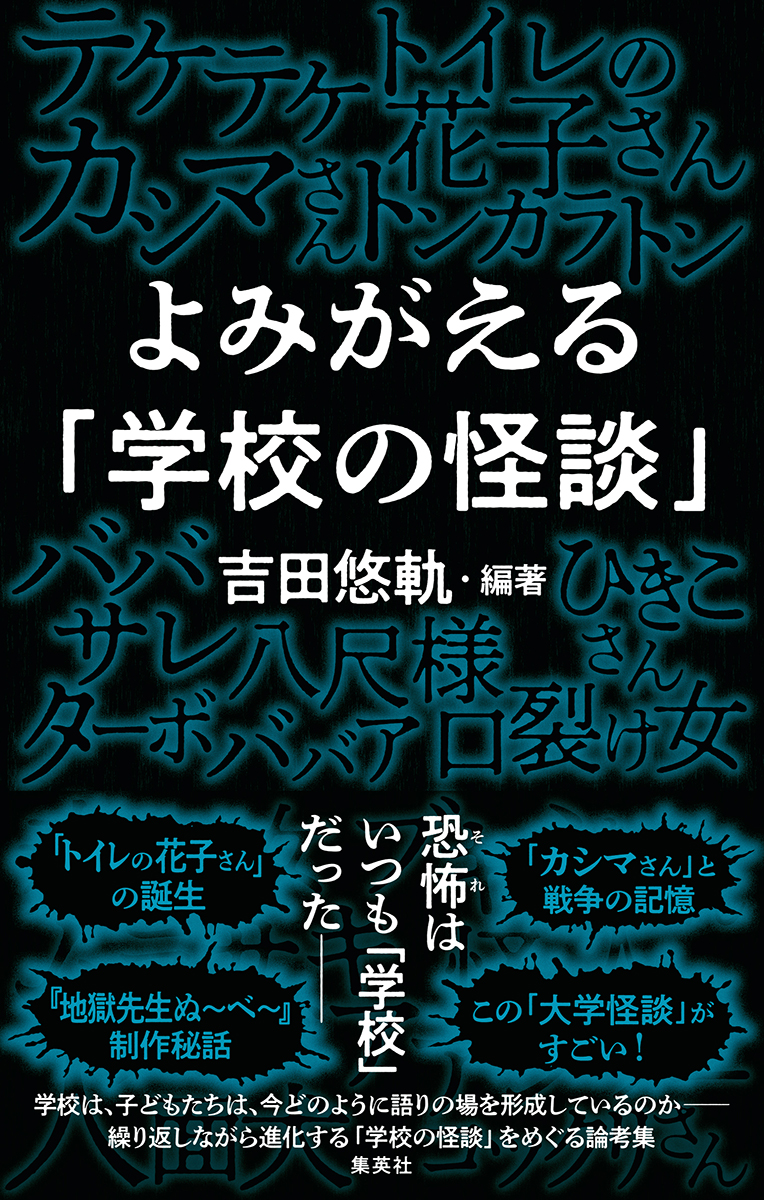2024.11.6
現象学からのクオリア・意識研究への問いかけ──北海道大学大学院教授・田口茂インタビュー
こんな問いを考えたことがある人は多いかもしれません。
そういった「赤い感じ」や「コーヒーの香りのあの感じ」等は、〈クオリア〉と呼ばれています。
重要なテーマであっても、これまで科学的にアプローチしにくかった〈クオリア〉。
そこにいま、様々な分野の最先端の研究者たちによる、新たな研究が進んでいます。
〈クオリア〉を探求する多様な研究者に話を聞く、インタビュー連載です。
科学的な実験や数式ではなく、言葉を武器とする営みである哲学。
そんな哲学を専門とする田口茂氏は、意識やクオリアをめぐる数々の言葉には、改めて考察をし直す価値があるという。
(聞き手・構成・文責:佐藤喬、特別協力:藤原真奈)

記事が続きます
意識をめぐる言葉のゆらぎ
意識についての議論を見ていると、しばしば、われわれ自身意味をはっきり理解していない言葉が使われることがあります。
たとえば「意識は『実在』するのか」と言ったときの「実在」とは、厳密には何がどうなることか。モノとして触れるこのスマホは実在していると言ってよさそうですが、しかし、そうではない数の「1」や「過去の記憶」は実在していないのか。そう決めつけることもできないですよね。この「実在」のように、研究の世界を含めて気軽に使われている言葉が、実はちゃんと正確に理解されていないことは非常に多いのです。
「クオリア」も同じです。
よく、クオリアの例として「赤の赤さ」とか「赤を見たときの独特の感じ」などと書かれたりしますよね。意識についての議論を読みなれた人ならなんとなく納得してしまいそうな表現ですが、改めてじっくり考えると、これらは十分な説明と言えるのでしょうか。
「赤さ」とは? 「感じ」とは? なにか、それらしいことを言っているようでいて、実はあいまいで、場合によっては矛盾をはらんでいたりはしないか。
私が専門とする哲学は、数式や実験ではなく、言葉を武器とする学問です。なんとなく読み過ごされる言葉や概念を改めて考察しなおすのは、哲学の大事な仕事の一つです。
厳密に定義された言葉を使っているように見える科学の世界も、根本まで深掘りしていくと、意外と日常用語に近い素朴な概念が「なんとなく」流通していることがあります。そういうときは、哲学が必要になるでしょう。
「私を見ている私」は存在するか?
意識について一例を挙げると、やはりその理解には少し問題がある場合が少なくないようです。意識を「自分を見ている自分」であるとか、それに近い意味で「より高次の思考」などと表現されることがありますが、よくよく考えてみると、これはちょっと問題があるのです。
たしかに「あ、自分は今、赤い色を見ているな」とか「お茶の熱さを舌で感じているな」と、「自分を見ている自分」を意識と呼んでも良さそうな気はします。しかし、このように「ある経験をしている自分A」と、「それを外部から観察している自分B」という二つの存在を意識の条件にしてしまうと、じゃあ自分Aを観察している自分Bの存在を認識するためには自分Bをさらに外部から観察する自分Cが必要になり、すると、それをまた外から見る自分Dが必要になり……と、無限に続くことになってしまう。これを「無限後退」と呼びますが、説明としては成り立っていません。
このように、それほど深く考えずに前提とされていることに、実は問題が潜んでいることは少なくありません。
科学的なアプローチと現象学的なアプローチ
哲学の中でも、私は「現象学」と呼ばれる分野を専門にしています。現象学は一切を「現われ」という側面から研究する分野で、たとえば「レモンが見える」という視覚的な経験は、レモンのこちら側の面が、私に対して「現われ」ている、という風にとらえます。
ただし、レモンのすべてが現われているわけではありません 。レモンの裏側や中身は、そのときの私に対しては現われていないからです。レモンに対しては無数の視点があり、それらが同時に現われることはない、つまり視点を抜きにモノを見ることはできないというのが現象学の考え方です。
ともかく、このように多くの場合、「現われ」には受け手がいますから、現象学は結局のところ意識の哲学的研究でもあったのです。意識についての哲学というと多くの方がいわゆる「心の哲学」をイメージされるかもしれませんが、心の哲学は主に分析哲学という少し違う分野の営みです。が、現象学では、心の哲学が成立するずっと前から、意識が研究されてきたのです。
私はその現象学の分野で自我や間主観性などを研究してきました。とくに「意識」を研究テーマに掲げてきたわけではありません。
しかし2010年代にこの「クオリア構造学」を率いる土谷尚嗣さんたちと知り合ったことで意識についての科学的な研究に具体的に親しむようになり ました。
意識を記述する難しさ
科学的な意識研究はとても興味深かったのですが、哲学者としては疑問を感じることもありました。それは、そもそも科学的な意識研究では意識をどのように理解していて、その意識についての何が分かれば、意識をとらえたと言えるのか。ゴールがはっきりしないと感じたのです。
意識をなにか実体があるようなものととらえていて、それを追いかけているようにも見えましたが、それはそもそも「意識」と呼ばれているものを取り違えているのではないか。そのような疑問もありました。
科学的な意識研究者にこういうことを言うと水を差すようで申し訳ないけれど(笑)、意識の特殊さを言葉で記述する試みを続けてきた現象学者としてはここまで突っ込んで考えたいと思ったのです。
意識は非常に特殊な構造を持っています。先ほど述べたように、「意識する私」とは別に「私を意識している私」がいるという構造は無限後退に陥りますから、ちょっとおかしい。そうではなく、両者は同じ場所になければいけません。
言い換えると、意識は、意識自身を意識している。見る側と、見られる側が同じ場所にある。そういう構造は日常にはありませんから、二次元とか三次元の図で表現することはできません。非常に変わった構造があり、それをうまく記述したいと私は考えたのです。
意識を記述するために役立ちそうなのが、数学の一分野である「圏論」です。プリンストン高等研究所のピート・ハットさんとの交流を通して 数学者の西郷甲矢人(さいごう・はやと)さんと知り合い、たとえば圏論の「モノイド」という概念を使うと、意識の不思議な構造をクリアに形式化できるのではないかと考えました。これについては、西郷さんとの一連の共著論文があります。ちなみに西郷さんとは共著書『〈現実〉とは何か──数学・哲学から始まる世界像の転換』(筑摩選書, 2019)もあります。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)