2020.8.19
これからの住まいを考える
当記事は公開終了しました。
2020.8.19
当記事は公開終了しました。
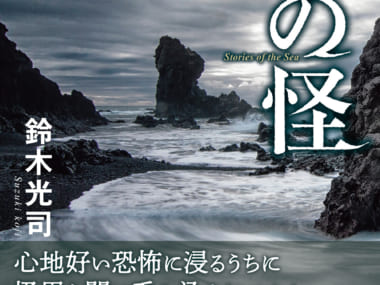

土を編む日々
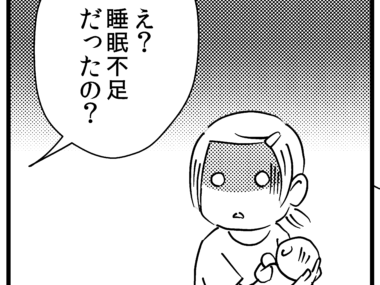
実家が放してくれません

戦国サバイバー

犬と本とごはんがあれば 湖畔の読書時間
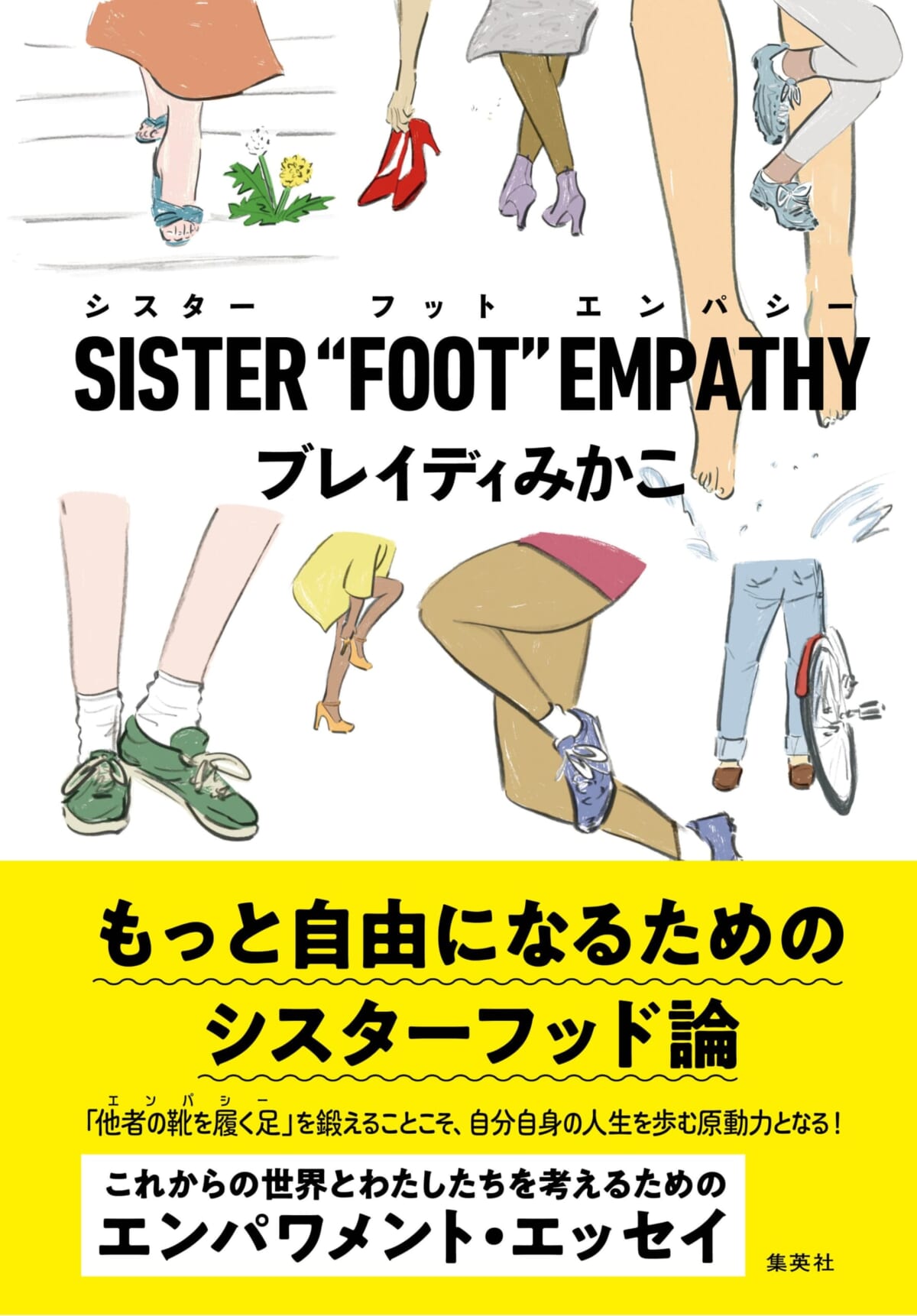
2025/6/26
NEW
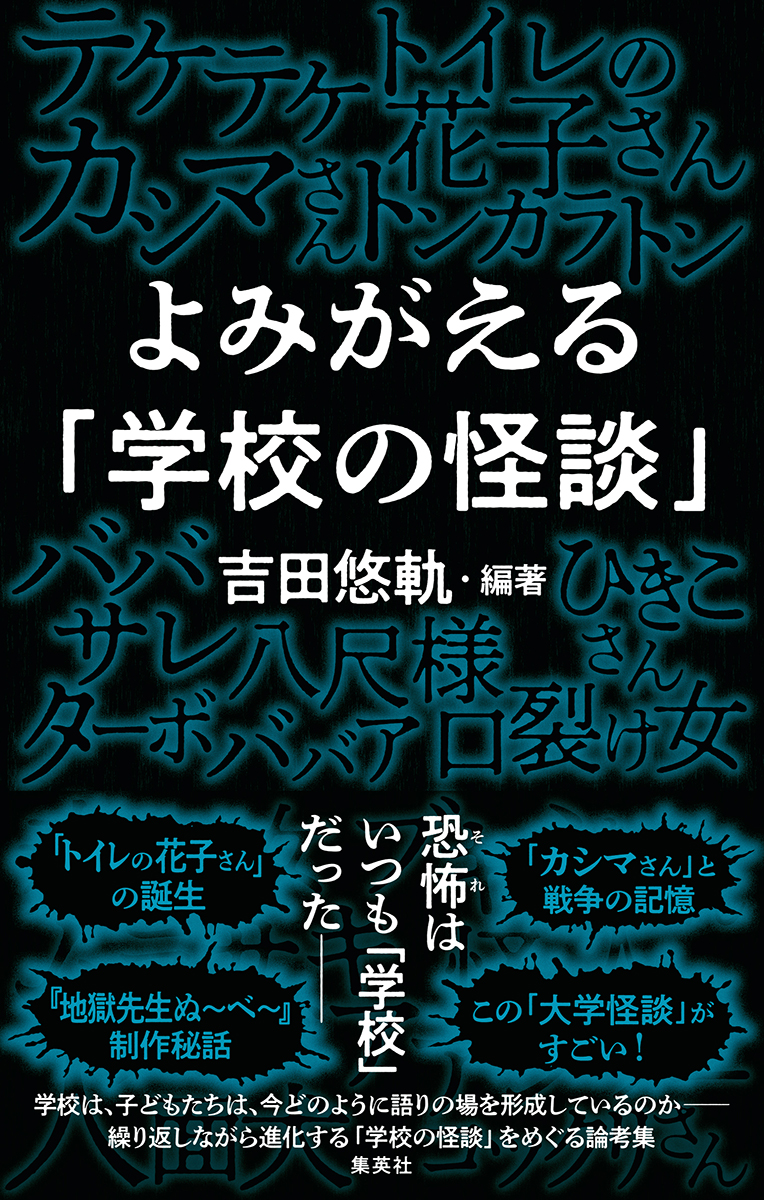
2025/7/4
NEW

2025/5/26
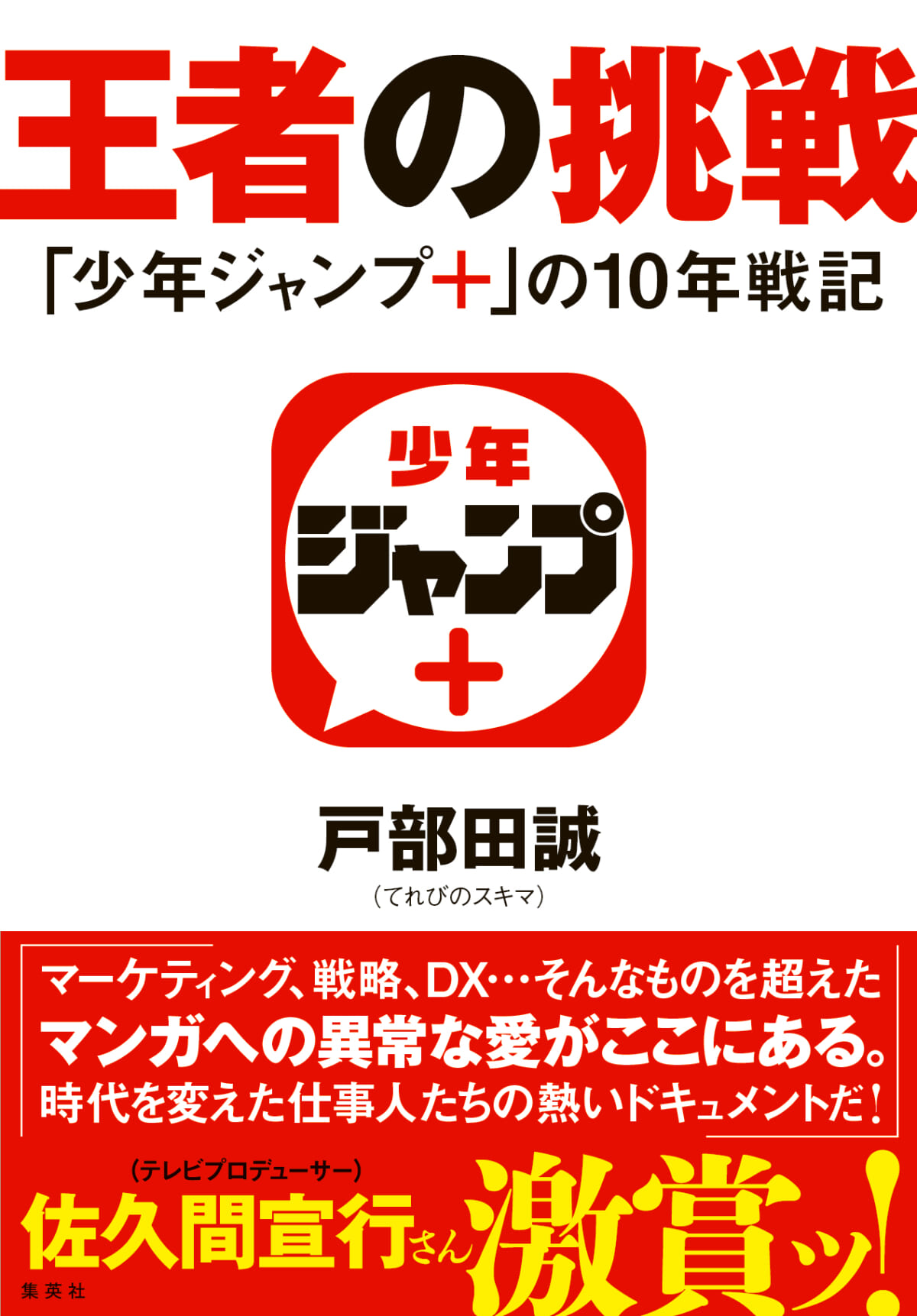
2025/5/9

白兎先生は働かない

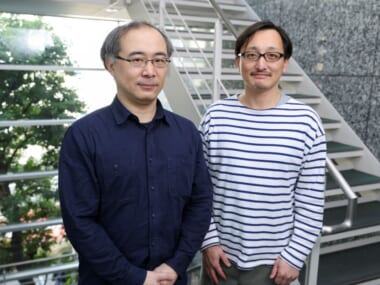

ケアとアートのダンス ~アクセシビリティのためのプロジェクト・レポート~