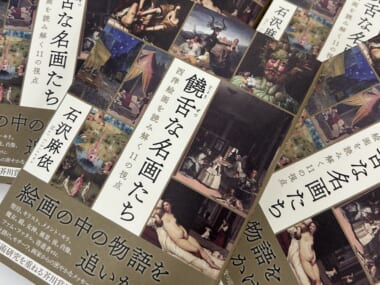2022.12.2
ハーバードのことは考えずに、東大だけを見て「すごい」と思い込むことの幸せ感 第6回 東大信奉と低学歴信仰
当記事は公開終了しました。

2022.12.2
当記事は公開終了しました。

饒舌な名画たち 西洋絵画を読み解くための11の視点

六十路通過道中
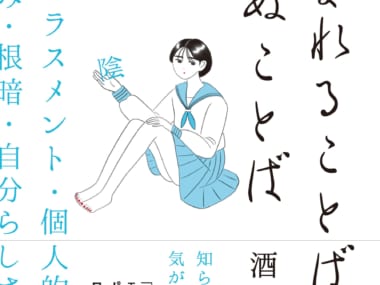


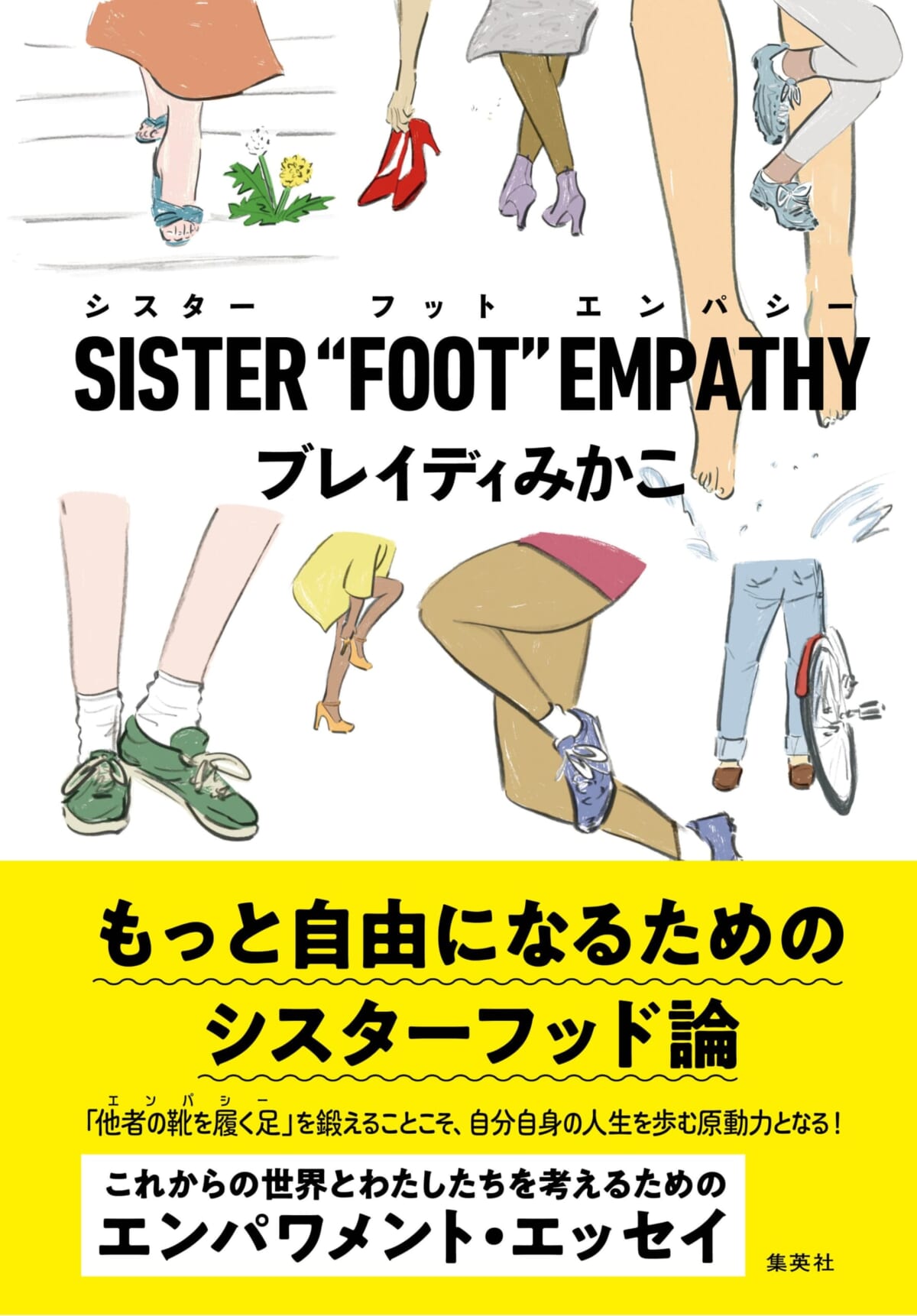
2025/6/26
NEW
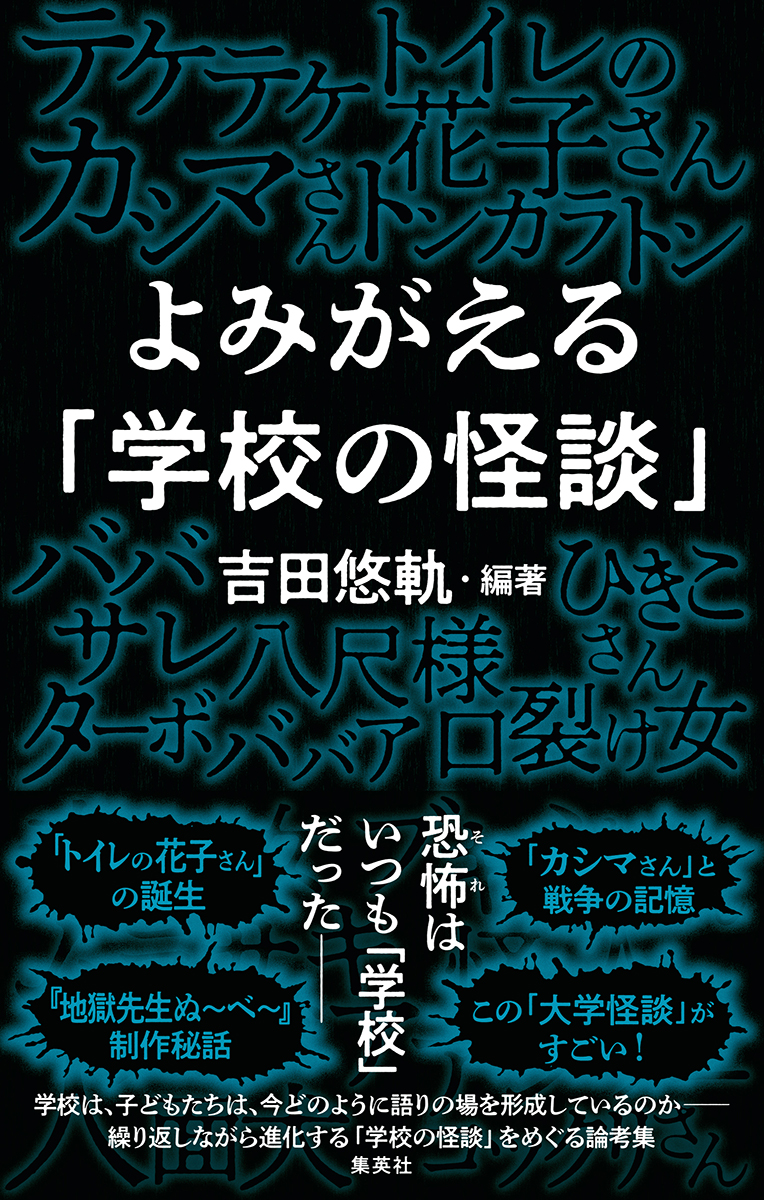
2025/7/4
NEW

2025/5/26
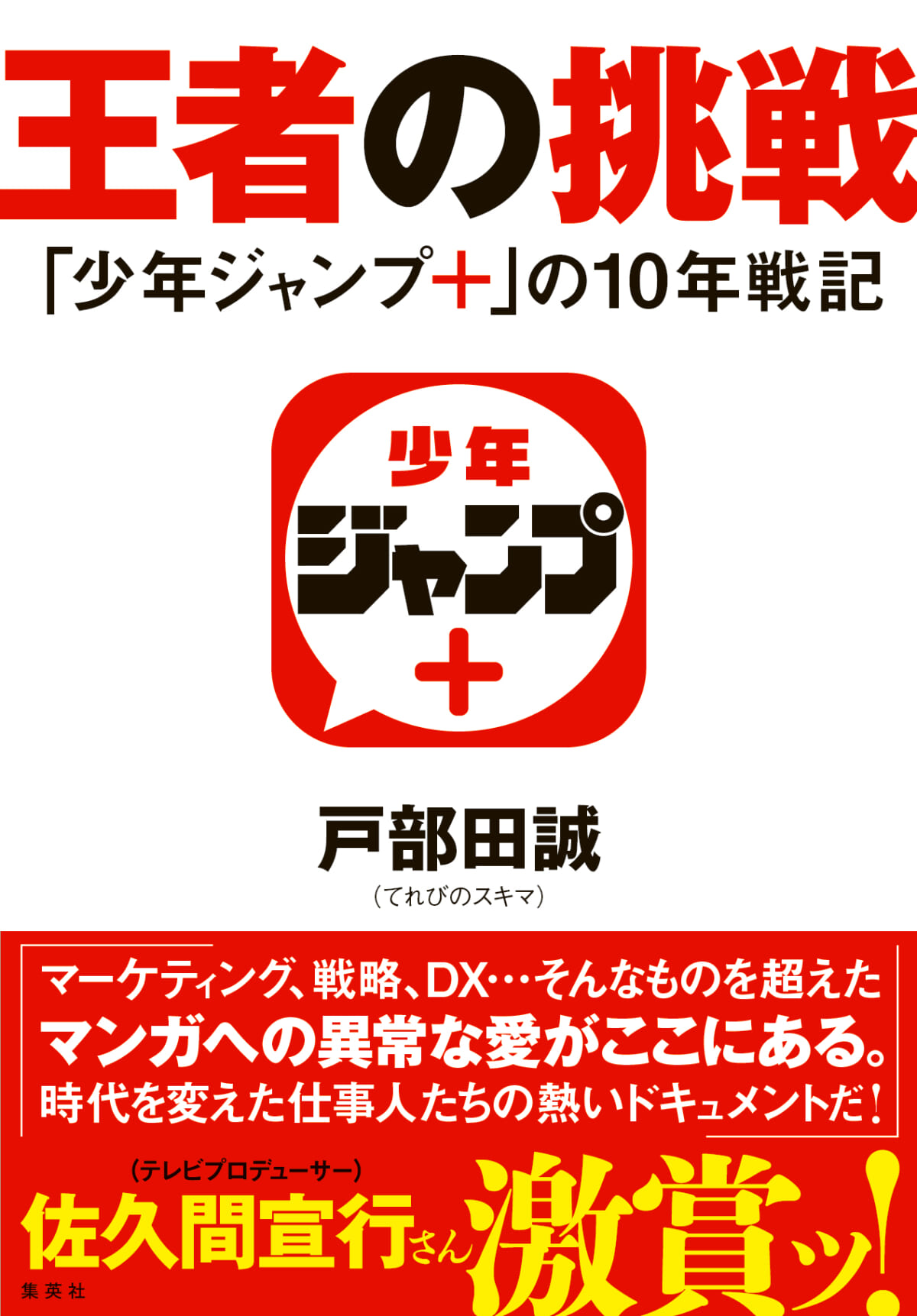
2025/5/9

白兎先生は働かない

西の味、東の味。