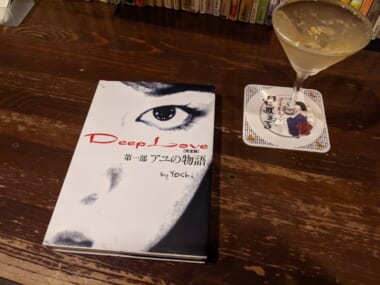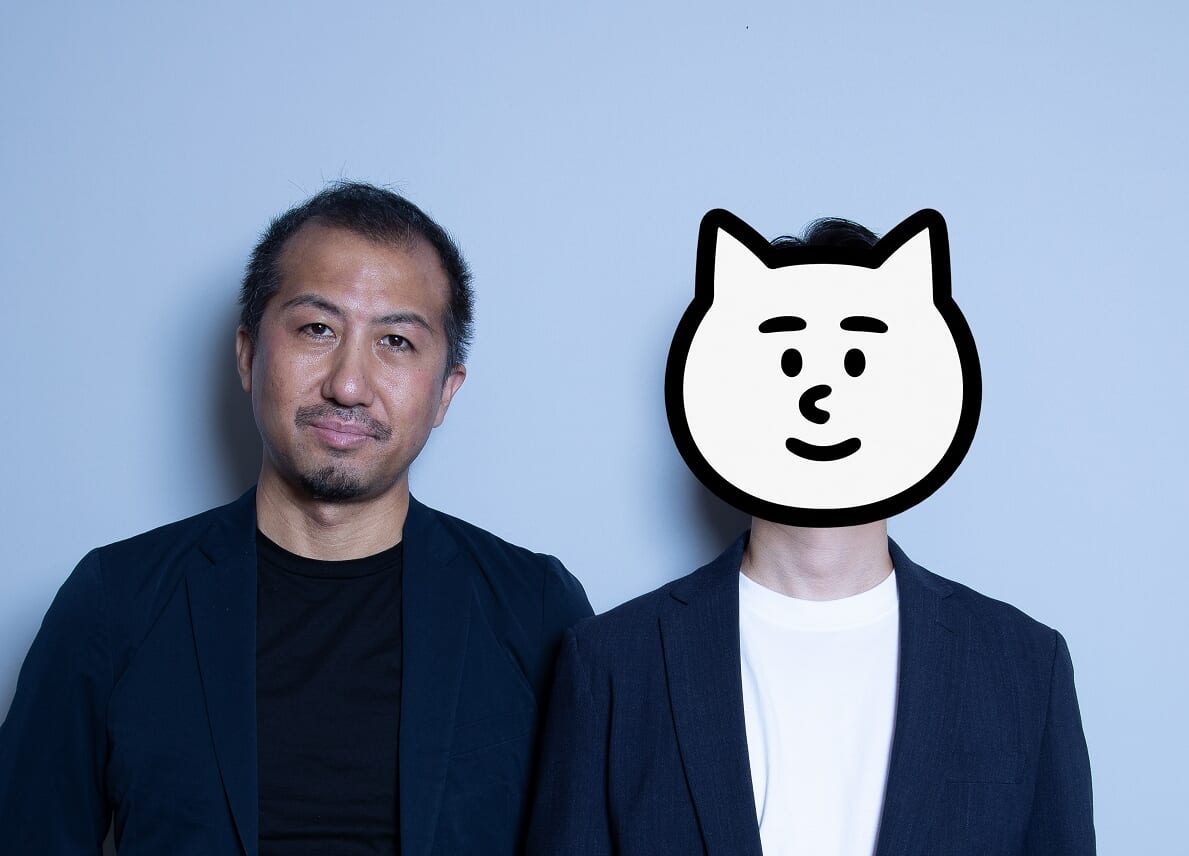2022.10.5
陰キャが勝ち取った幸運?「人見知り克服養成所」店番の米澤成美さん監督作品『ちくび神』を見に大阪へ…
謎の句点のついたLINE
6月。大阪に行くことにした。大阪に行くのは小学生のとき以来だった。観光を兼ねようと思い、『ちくび神』の上映日の前日である6月17日に大阪に到着した。観光が一段落して夕方になったころ、米澤さんに「大阪に来たので、時間あったら飲みましょー」とLINEを送ると、
「なんともはや!嬉しやです。いま十三の商店街でビラ配りしてて、18時30ころおわります、」
と、最後に謎の句点のついたLINEが飛んできた。とりあえず十三に移動すると、19時を過ぎたころに、
「おわりまして、荷物が駅チカコインランドリーにおいててとりゆきます!」
とLINEが来た。たぶんコインロッカーのことだと思ったが、「了解です」とだけ返して次の連絡を待っていると、
「駅のこちら側におります!」
「メガネです」
という連続したメッセージと共に、2枚の写真が送られてきた。大きな一本の木の周りにたくさん草の生い茂った、レンガの石で囲われた植木スペースの写真と、手前に止められたたくさんの自転車の向こう側にミスタードーナッツの看板が辛うじて映っている写真だった。初めて訪れた十三駅でその少ない情報だけでは場所を特定するのは難しいと思ったけれど、グーグルマップでミスタードーナッツを調べたら十三駅の東口の近くに一つしか出てこず、ミスタードーナッツと道を挟んで正面にある何も建物のないスペースがグーグルマップ上で「アーモンドの木」と名指されていたので、そのアーモンドの木の下に米澤さんがいるのだろうということが意外にも明確にわかった。
「了解です」
と返信をして、グーグルマップに従ってアーモンドの木を目指して歩いていると、
「植木に座ってました」
とLINEが届いた。なぜ過去形なのだろう。自分が向かっている先に米澤さんはもういなくなってしまったのではないかと不安に思いながらも、アーモンドの木の場所を目指し歩くと、植木スペースを囲うレンガの石のところにスマホをいじっている米澤さんが座っておられた。米澤さんは荷物のたくさん入った手提げ鞄を2つ持っていて、1つは自分の隣に置き、もう1つは自らの膝の上に置いていた。
「お久しぶりです」
「おぉっ。今日はわざわざありがとうございます。ちょっとメッセージを返しているので、少々お待ちください」
それからしばらく米澤さんはスマホで文字を打ち込み、膝の上に置いてあった手提げかばんの中からロジクールの黄色のBluetoothマウスを取り出すと、膝の上でカチッと一度だけクリックした。
「すいません、お待たせしました」
やはり、小説に出てくる世界を一変させてしまう一節のような、美しい動きだと思った。
行きたい居酒屋が十三駅の西口の商店街にあったので歩いて向かうと、店が満員になっていて入れなかった。特に二軒目のことは考えていなかったので「すいません、困りましたね。どこか目についたとこ入りますか」と言うと、
「いえいえ、私は、もう本当どこでも、そこら辺の大衆居酒屋で大丈夫ですよ」
と言った米澤さんが、道の右手に串カツ屋が見えたところで串カツ屋に吸い寄せられるように小走りになり、
「そういえば、大阪に来たのに串カツをまだ一回も食べてないですねぇ」
と腕を組みながら言いはじめたので、その串カツ屋に入ることにした。
テーブル席に着くと、お勧めのセットが書かれたメニュー表がテーブルの上に置かれていた。生ビール一杯と、どんてんと、3つの串カツがついて980円。とりあえずそのセットを頼みましょうということになり、店員のおばちゃんを呼んだ。
「このセット2つお願いします」
「どちらのセットですか?」
メニュー表をよく見ると、串カツの種類によってセットは2種類に分かれていた。Aセットの串カツは豚かつと、うずらの卵と、玉ねぎ。Bセットは豚かつと、ハムカツと、レンコンだった。
「どちらのセットにします?」
米澤さんに尋ねると、少し口元を緩めながらメニュー表を眺め、まるで時間が止まったかのようにそのまま固まってしまった。店員のおばちゃんが「どちらのセットですか?」と改めて聞いてくるので、「どっちにします?」と米澤さんに再び尋ねたが、米澤さんは相変わらず同じ表情で固まったままだった。
「どちらのセットですか?」
大阪のおばちゃんが間髪いれずにこれでもかとプレッシャーをかけてくるので、「何食べるかは頼んでから考えますか」と言って、AセットとBセットを1つずつ頼むと、
「私、こういうとき優柔不断でねぇ。選べなかったです」
米澤さんはやっと呼吸を再開できたような顔をした。
少しすると店員のおばちゃんが、「二度漬け禁止」と印字された小皿と、大きな長方形の銀の皿の上で網に並べられた串カツと、ボトルに入ったソースを持ってきてくれた。
「全部いっぺんにソースかけてもいいですかねぇ?」
ボトルのソースを手にした米澤さんが訊ねてくれた。特にソースの量にこだわりがなかったので、
「お願いします。全部かけちゃってください」
とお願いをすると、
「二度漬け禁止って。これ、どこまでが二度漬けになるんでしょうねぇ。ソースを往復してかけるのは、二度漬けに入るのかなぁ。片道でかけるだけだと味が薄そうだから往復でかけたいのだけど。でも、二度漬けは駄目だしなぁ」
と、米澤さんがまるで人形に話しかけるみたいに串カツを見つめながらしばらく悩んだあと、
「いいや、やっちゃえぇぇっ!」
決死の覚悟で串カツにソースを往復でかけはじめた。
僕は、米澤さんが一体何をしているのかすぐに理解することができた。店員のおばちゃんが持ってきた小皿に「二度漬け禁止」と印字されており、おそらく米澤さんはその文字を見て、ボトルのソースを二度かけてはいけない、と判断しているようだった。しかし、「二度漬け禁止」というのはおそらくコロナ禍の前にアルミケースに入った状態でソースがテーブルの上に置かれていたときのもので、コロナ禍になってからは感染対策でソースはボトルで提供されるように変わったから、そもそも二度漬け自体が発生し得ない状況になっていた。そんな状況であっても以前から使われていたであろう「二度漬け禁止」と印字された小皿が提供されるのは、コロナ禍のせいで発生した串カツ屋の綻びであり、その綻びを通して米澤さんは「ボトルのソースの二度漬け禁止」という新しい世界観を自分の中で作りだしてしまったようだった。
「二度漬け禁止はコロナ禍の前の話だから、ソースはいくらかけても大丈夫だと思いますよ」
もし米澤さんがソースをどのくらいかけようか悩んでいるときに僕の目を一度でも見たら、そんな風に訂正をしていたと思う。けど、米澤さんがひたすらテーブルの上の串カツだけを眼差しながらどこからが二度漬けになるのか真剣に格闘している姿を見ると、米澤さんが今まさに作りあげている世界を壊してしまうのがよくないことのように思え、自分から訂正することはできなかった。
「二度漬けって言われなきゃ助かるんだけどねぇ」
そう言いながら豚カツの串を口にした米澤さんは、
「やっぱり往復でかけても味が薄いねぇ。でも二度漬けはダメだしなぁ」
と悩んだ末に、ソースをかけたときに銀の皿の下に落ちて溜まっていたソースに豚カツを付け、
「これなら二度漬けにならない」
と、満足そうな表情で食べていた。僕も、米澤さんがソースをかけてくれた豚カツを食べてみると、確かに一往復ソースをかけただけの豚カツは味が薄かった。だけど、美味しいと思った。物理的にはソースを適量かけた方が美味しいのかもしれないけれど、この人と一緒にご飯を食べているからこそ生まれた状況というのは、その状況こそがひとつの調味料のようなもので、それは時に適量のソースよりも豚カツを美味しく思わせるのだった。結局は、自分はこうした状況が好きだから、自分のためにソースをいくらかけても二度漬けにならないということを米澤さんに教えなかったのではないか、という罪悪感のような感情も生まれたが、自分ほどの人間が米澤さんのことを訂正できるような人間ではなかったのだと思わされたのが、二軒目の飲み屋での大阪の人と米澤さんの掛け合いだった。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)