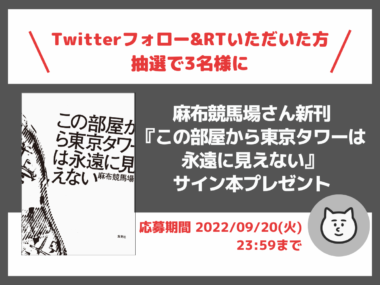2022.9.7
一言目で「抱いていい?」と言われたのは、人生で初めてのことだった──ボブカット美女とのほろ苦いゴールデン街デート
理不尽なゲーム
「はーい、じゃあ、ゲームはじめるよ。グラスをテーブルに置く時に二回トントンッとしなかったらアウト。あと、英語を使ったらアウト。罰ゲームは一気飲みね。いい? 始めるよ? よーい、スタート」
お酒の提供が終わったナカザワ君が、今度はやけに真剣な顔で仕切りだし、なにやらゲームが始まった。その簡単なルール説明を聞いただけで店内の客はみな何一つ疑問のないような顔をしていたから、常連客には馴染みのあるゲームのようだった。自分は絶対に罰ゲームにならないようにしなければ、と思った。イベントの日の常連客ばかりの状況で、新参者が罰ゲームになることほど白けることもないからだ。
「あ、ふえこ普通に置いた!」
ゲームが始まってすぐ、ふえこさんがグラスを普通にカウンターの上に置き、ナカザワ君に即座に指摘された。
「うるせぇなぁ」
それまで聞いたことのない悪声をふえこさんが発した。
「おい、ふえこ、アウトだぞ」
またどこからか男の声がした。僕はその「アウト」という英単語を聞き逃さなかった。
「あっ、お兄さん。今、英語を口にしましたね」
声のした方に向かって指摘すると、三十半ばくらいの男と目が合った。その男もまた一瞬僕の目を見ると、何も言葉を発することなく目を逸らした。一瞬だけ合った目は、お前は一体何を言っているんだ、と訴えかけているように見えた。僕はゲームのルールに忠実に従ったつもりだったが、もしかしたらなにか間違ったことを言ったのかもしれない、と思って周囲を見渡すと、お酒を口にした人はみなグラスを普通にカウンターに置くようになっていた。ゲームが始まって誰か一人がアウトになったら、そこでゲームは終了のようだった。そんなルール、僕は聞かされていなかった。ひどい仕打ちだと思った。心細くなって助けを求めるようにふえこさんの方に目をやった。こんな常連だらけの場に僕を投げ込んだ張本人がふえこさんだったが、この場で僕が頼ることができるのもふえこさんしかいなかった。しかし、いつの間にかふえこさんはグラスを握りしめたまま下を向いて寝てしまっていた。そのまま朝まで、ふえこさんは眠ったままだった。唯一の知り合いがいなくなってしまった僕は、カウンターに並べられている文庫本をなんとなく眺めた。永沢光雄の『声をなくして』という本が目についた。イベントの日に常連客に囲まれて全く馴染めずに喋れない今の自分の境遇にお似合いのタイトルだと思った。本を開いて文字を追っても、酔っぱらってるから何も意味が頭に入ってこなかったが、その本を読んでる振りをしながら、朝まで静かにお酒を飲むことができた。
「始発の時間になったから帰るわ」
店の中の誰かが呟くように言った。開けっぱなしのドアの外を見ると、路地が朝日に照らされていた。
「えっ、もう始発?」
「そんな時間か」
店内にいた十人近くの人がみな帰り支度をし始めた。その喧騒に起こされるようにふえこさんもやっと頭を上げ、「帰る」と一言だけ口にすると席を立った。ふえこさんのことを追いかけるようにお店を出ると、
「あれ、俺が来たらみんな帰っちゃったよ」
ちょうど店内にいた全員が店を出るタイミングで入店してきた50歳くらいのおじさんが、まるで自分のせいで皆が帰ってしまったと言わんばかりの切ない表情で店の入り口のところで嘆いていた。そのおじさんの声に耳を傾ける人は誰ひとりおらず、駅の方に向かってみな散り散りに帰っていった。
ふえこさんのことを駅まで送っていこうかと思ったが、何かしようとする度に「いいっ」と断られてきたからその必要もないのかもしれない、と迷いながら、石畳の四季の路を駅の方に向かって歩くふえこさんの少し後ろを歩いた。しばらく歩くと、ふえこさんが後をついてくる野良犬をシッシッとやるように、斜め後ろに伸ばした手を僕の方に振りながら「ありがと。またね」と言ってきた。こちらが返事をするよりも早くふえこさんの顔は前を向き、そのまま早歩きで駅の方へ去っていった。重たい荷物を背負って丸くなったふえこさんの背中が小さくなってゆくのをしばらく眺め、別の道で家に帰ることにした。
この続きは、書籍でお楽しみください☟

どうしたら正しいセックスができるのだろう――
風俗通いが趣味だったシステムエンジニアの著者が、ふとしたきっかけで通い始めた新宿ゴールデン街。
老若男女がつどう歴史ある飲み屋街での多様な出会いが、彼の人生を変えてしまう。
ユーモアと思索で心揺さぶる、新世代の私小説。
書籍の詳細はこちらから。
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)