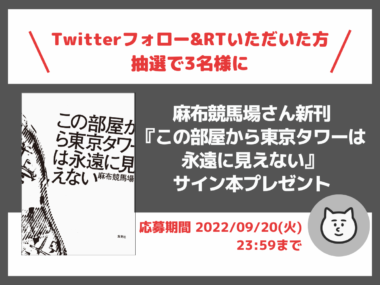2022.9.7
一言目で「抱いていい?」と言われたのは、人生で初めてのことだった──ボブカット美女とのほろ苦いゴールデン街デート
「今まで読んだ中でそれが一番おもしろかったよ」
「ゴールデン街に戻る」
結局、おつまみを追加で頼むことはしないまま一時間くらい飲んだところで、重くなってきた瞼をパチパチしながらふえこさんが言った。この日は初めて会った『月に吠える』というプチ文壇バーで店番のナカザワ君という男の子がイベントをやってるらしく、そこに行きたいとのことだった。お店を出て、ゴールデン街の方に向かった。
「本が好きなんだっけ?『Deep Love 第一部 アユの物語』っていうの小学生のときに読んだけど、今まで読んだ中でそれが一番おもしろかったよ」
ゴールデン街に向かって歩いてる途中、何の前触れもなく本の紹介をされた。全くこっちの話なんて聞いていないようにも見えるのに、初めて会った日に交わした少しの会話のことを不思議なリズムで思い出す人だ。こんな風に、他人から好きな本を教えてもらえるのはありがたい。どうしてこの人はその本が好きなのだろう、どうしてこの人の中にその本が長く記憶に残っているのだろう、と想像しながら読書をすると、この本は読まなくてよかったな、と思うことなんて一切なくなってしまう。ゴールデン街に向かって歩きながらスマホでAmazonのアプリを開き、『Deep Love 第一部 アユの物語』を購入した。
*
『月に吠える』に到着すると、八席あるカウンター席がすべて埋まっていた。
「おう、ふえこ。二人? 席空けるよ」
カウンターの真ん中あたりに座っていた男性二人が席を空けてくれた。カウンター席に座っている人たちの背中と後ろの壁の間の狭い道を通って、空けてもらった席に座った。カウンターの中を見ると、お酒の置かれたラックの目立つところに「ナカザワユースケ リストラ記念」というフライヤーが掲示されていた。ナカザワ君という男の子が編集プロダクションをリストラされてフリーランスになったということで、その記念イベントが行われているようだった。カウンターの中に立つナカザワ君は、小太りで、海藻のような髪が肩まで伸び、目深に被った黒いキャップの下から女性器を水平にしたような横長の目を覗かせる、奇妙な男だった。
「今日、私この人とデートしてきたの!」
ふえこさんが席に座るや否や、またカウンターの中に向かって叫ぶように言った。
「へぇ、よかったじゃん」
「ふえこと二人って、何しゃべるんだろう」
ふえこさんの叫びを聞いて、カウンター席に座る男の人たちがポツポツと呟いた。その反応からするに、ふえこさんも含め、みな顔なじみの常連のようだった。ふいに、右隣の席でマルクスの資本論がなんたらと話をしていた男性が僕の肩のところに顔を埋めてきて、「お兄さん、無印良品の匂いがしますね」と言ってきた。この店の常連である自分のような男と、女のデート相手になるような新参者の男は違うんだ、という差別化のニュアンスが「お兄さん、無印良品の匂いがしますね」という言葉に込められているように聞こえたが、幸か不幸か、僕は本当に無印良品の服を着ていたので、
「よくわかりましたね。無印良品の服を着てるんですよ」
と返すと、やはりそういう返答は求められていなかったようで、黙って目線を逸らされてしまった。
絡まれるのが落ち着いたところで、お酒を頼むことにした。ふえこさんはウーロンハイを頼み、僕は「印税生活」というオリジナルカクテルを頼んだ。店番のナカザワ君がシェイカーの中にいくつかの液体を混ぜ、肩まで伸びた髪とむちむちした体全体を揺らしながらシェイカーを振り始めた。シェイクしている間、ナカザワ君がプルプル震える顔をこちらに真っすぐ向けてくるものだから目のやり場に困った。振られているシェイカーの方に視線を合わせると、突然シェイカーがナカザワ君の手から滑って吹っとび、ガシャンッ、と大きな金属音が店内に鳴り響いた。
「ごめんごめん、もう一回作り直すわ」
まるで自分の失敗を寿ぐように満面の笑みでナカザワ君がそう言うと、再びシェイカーの中にいくつかの液体を混ぜ、先と同じように肩まで伸びた髪とむちむちした体全体を揺らしながら、プルプル震える顔をなぜかこちらに向けてシェイカーを振り、黄濁したカクテルを提供してくれた。
「印税がないじゃん。ナカザワ、印税がないぞ」
ふえこさんが僕の前に置かれたカクテルグラスを覗いてなにやら指摘をしてくれると、ナカザワ君が「忘れてた!」とカクテルに金粉を振りかけてくれた。最後に振りかける金粉のことを、「印税」と呼んでいるカクテルのようだった。
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)