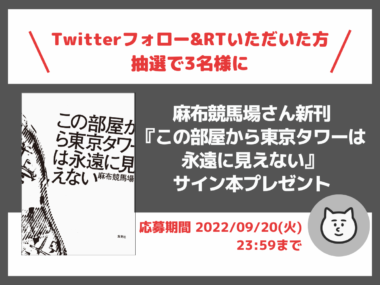2022.9.7
一言目で「抱いていい?」と言われたのは、人生で初めてのことだった──ボブカット美女とのほろ苦いゴールデン街デート
小室圭と眞子様みたいな恋がしたい
コロナ禍の深夜の新宿三丁目は真っ暗で、人通りもほとんどなく静寂に包まれていた。唯一営業していた橙色の明かりを灯した大衆居酒屋がオアシスのように存在していた。ふえこさんと特に示し合わせることもなく、吸い込まれるようにその店に入った。
入り口近くのテーブル席に座って、お酒とおつまみを頼んだ。ふえこさんはレモンサワーを、僕はオリジナルゆずサワーというものを頼んだ。おつまみは全てふえこさんに頼んでもらった。ポテトサラダ、ゲソの唐揚げ、まいたけバター。他人が選んだ食べものを食べることは一人でご飯を食べるときにはできないことだから嬉しい。
「じゃあ、デートに乾杯」
オリジナルゆずサワーを体に流し込むと、驚くほどにゆずの味が薄く、炭酸水と焼酎の味しかしなかった。なんだか騙されたような気持ちになったが、よくよく考えてみれば「オリジナル」には味が強いという意味もなければ、他のサワーより美味しいという意味もない。味が薄くたって、美味しくなくたって、なにも文句を言う権利はないのだ。個性的であるというだけでそれが良いものであるに違いないと信じてしまう、ゆとり教育で体に植えつけられてしまった感性が、もうすぐ三十歳になるというのに一向に治る気配がない。
「ねぇ、テレビとか見るの?」
お酒を一口飲んだあと、おつまみを小皿に取りながらふえこさんが聞いてきた。
「テレビ持ってないです。テレビ見ます?」
「私は、ラヴィットと水曜日のダウンタウンだけ見てる。毎朝、仕事行く前にラヴィット見るのが生きがいなの」
「あ、僕もParaviで水曜日のダウンタウンだけ見てます。芸人に操られたあのちゃんがラヴィットで大喜利するドッキリ、面白かったですよね」
「面白かった。私あれ、ラヴィットでリアルタイムで見てたからね」
ポテトサラダはジャガイモの味が薄かった。大衆居酒屋のポテトサラダは胡椒さえかけてくれればそれだけでよいのに胡椒もかかっておらず、玉ねぎとキュウリに付着したやけに多い水気が味の薄さに拍車をかけていた。味がしないから、言い訳のようにポテトサラダの皿の隅に盛られていたマヨネーズをつけて食べた。
「SNSは何やってるの?」
「Twitterだけです。ふえこさんは?」
「私はね、最近TikTok見るのにハマってる。高校生の男の子とかが投稿してる動画を見ると、すごい可愛いの」
「年下の子が好きなんですか?」
「うん。好き。あっ、でも、小室圭も好き。小室圭と眞子様みたいな恋愛がしたい」
ゲソの唐揚げは驚くほど真っ白だった。下味のされていない真っ白なイカを、申しわけ程度の衣が包んでおり、歯ごたえのある無を食べさせられているようだった。味がしないから、言い訳のようにゲソの唐揚げの皿の隅に盛られていたマヨネーズをつけて食べた。
「ふえこさんTwitterはやってないんですか?」
「やってるよ。Twitterはね、嘘か本当かわからないことを呟いてる」
「へぇ、嘘を書いてもバレないんですか」
「完全な嘘を書くわけじゃないからね。本当のことの中に、スパイスのように少しだけ嘘を混ぜるのがコツなの」
まいたけバターだけは味がした。まいたけ自体の旨味は感じられなかったけど、醤油とバターの味が濃くて助かった。言い訳のようにまいたけバターの皿の隅に盛られていたマヨネーズをつけると味がぶつかりすぎるので、マヨネーズはいらなかった。
「君、Twitterのフォロワー多そうだよね」
ピストルの形に開いた親指と人差し指で顎をはさみながら、まるでTwitterのフォロワーが見えるスカウターでも装着しているみたいにふえこさんが上目遣いで言ってきた。
「Twitterのアカウント教えてくださいよ」
「待って! もっと仲良くなってからね」
この日に聞いたなかで一番力強い声で拒絶されてしまった。
「タバコ吸ってきていい?」
ふえこさんが店の外に設置された灰皿のところにタバコを吸いに行った。一分ほどの短い時間で帰ってきた。
「風俗の文章を書いてるんだっけ? なんでそんな文章を書いてるの?」
一服してきたふえこさんが席に座ると、改まって質問をしてきた。そんなことをちゃんと覚えてくれているのだな、と少し嬉しく思った。初めは何か衝動のようなものがあってインターネットに文章を投下していたが、今となっては自分の文章を読んでくれてる人とばかり会うようになり、文章を通さずに他人と繋がる方法がよくわからなくなっているからだった。
「今となっては、それだけが他人と繋がる手段だからです」
「私も同じ。お酒を飲まないと、他人と繋がれないから」
子どものように頬を丸くして顔いっぱいに笑顔を浮かべたふえこさんと、改めて「かんぱーいっ!」とグラスを突き合わせた。
「鶏の唐揚げ頼もうかな」
おつまみの皿がすべて空いたところで、ふえこさんが呟くように言った。
「味しないものが多かったから、今度はちゃんと味がするものがいいね。今のところ、まいたけバターしか味がしてないから」
「後ろ見て。鶏の唐揚げ食べてる」
ふえこさんが目線で差した方向を振り返って見ると、黒のライダースジャケットに紺色のジーンズ姿の細身のおじさんが、白い丸皿に置かれた鶏の唐揚げにちょうど箸をかけたところだった。箸で半分に切った唐揚げを口元に運ぼうとしたとき、皿に残されたもう半分の唐揚げがコロンッとひっくり返り、衣のついていない断面の部分がこちらを向いた。衣の中は、お皿と同じくらいに真っ白い鶏肉だった。思わずふえこさんの方に目をやると、
「やばい、やばい。あれ、ぜったい味しない」
グラスに口を付けながら笑っていた。
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)