2021.10.22
仕事、生活費、災害対策……移住の前に考えなければならないこと ——経済アナリスト・森永卓郎さんに聞く
当記事は公開終了しました。
2021.10.22
当記事は公開終了しました。
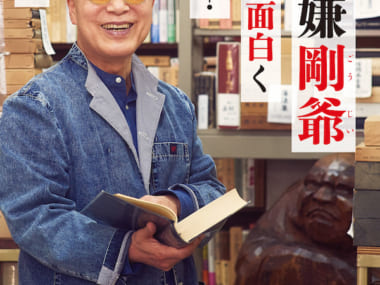

スタイリスト栗原登志恵のイタリア時間

犬と本とごはんがあれば 湖畔の読書時間


まめの推しごと
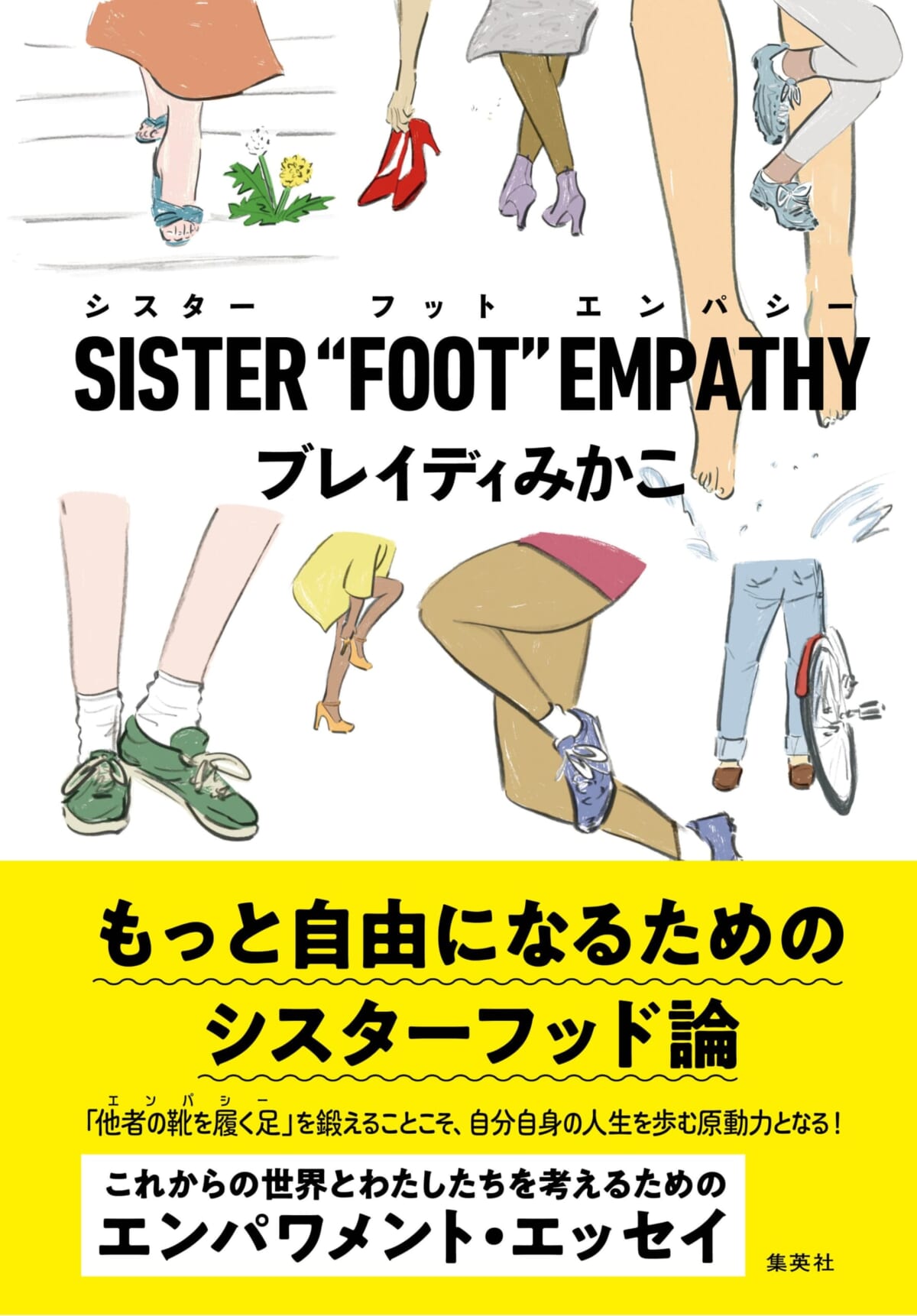
2025/6/26
NEW
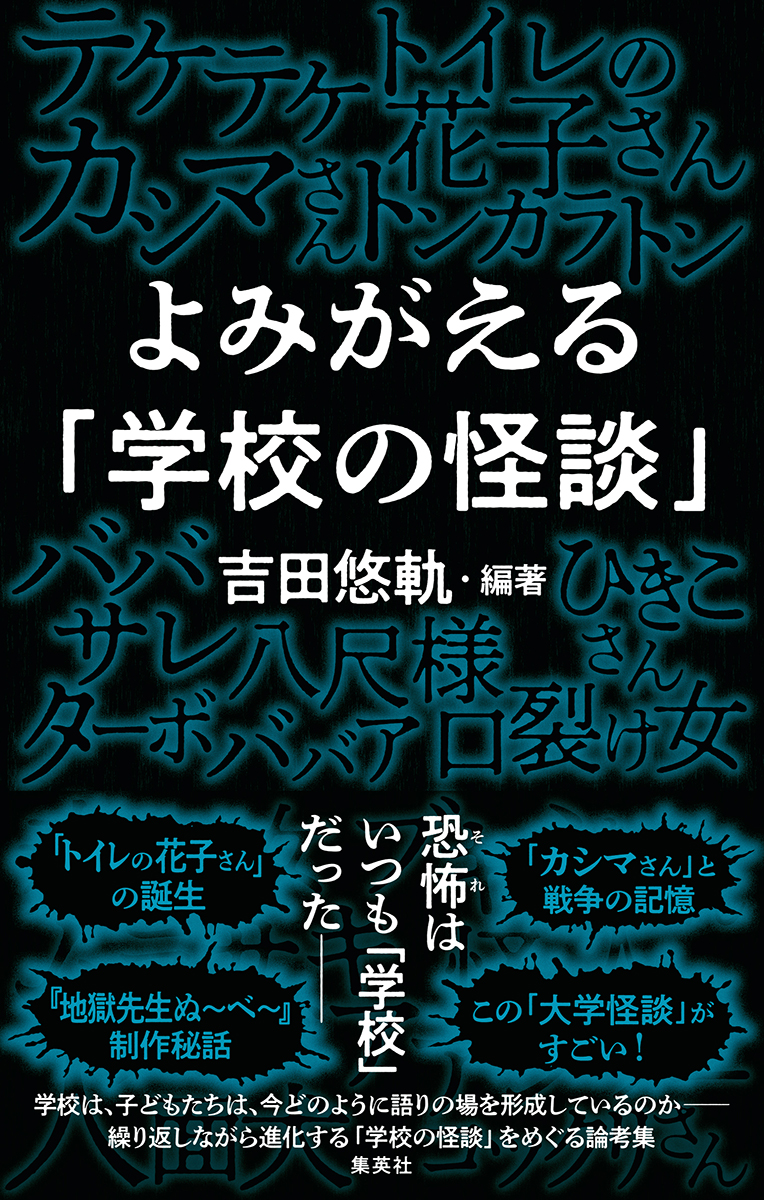
2025/7/4
NEW

2025/5/26
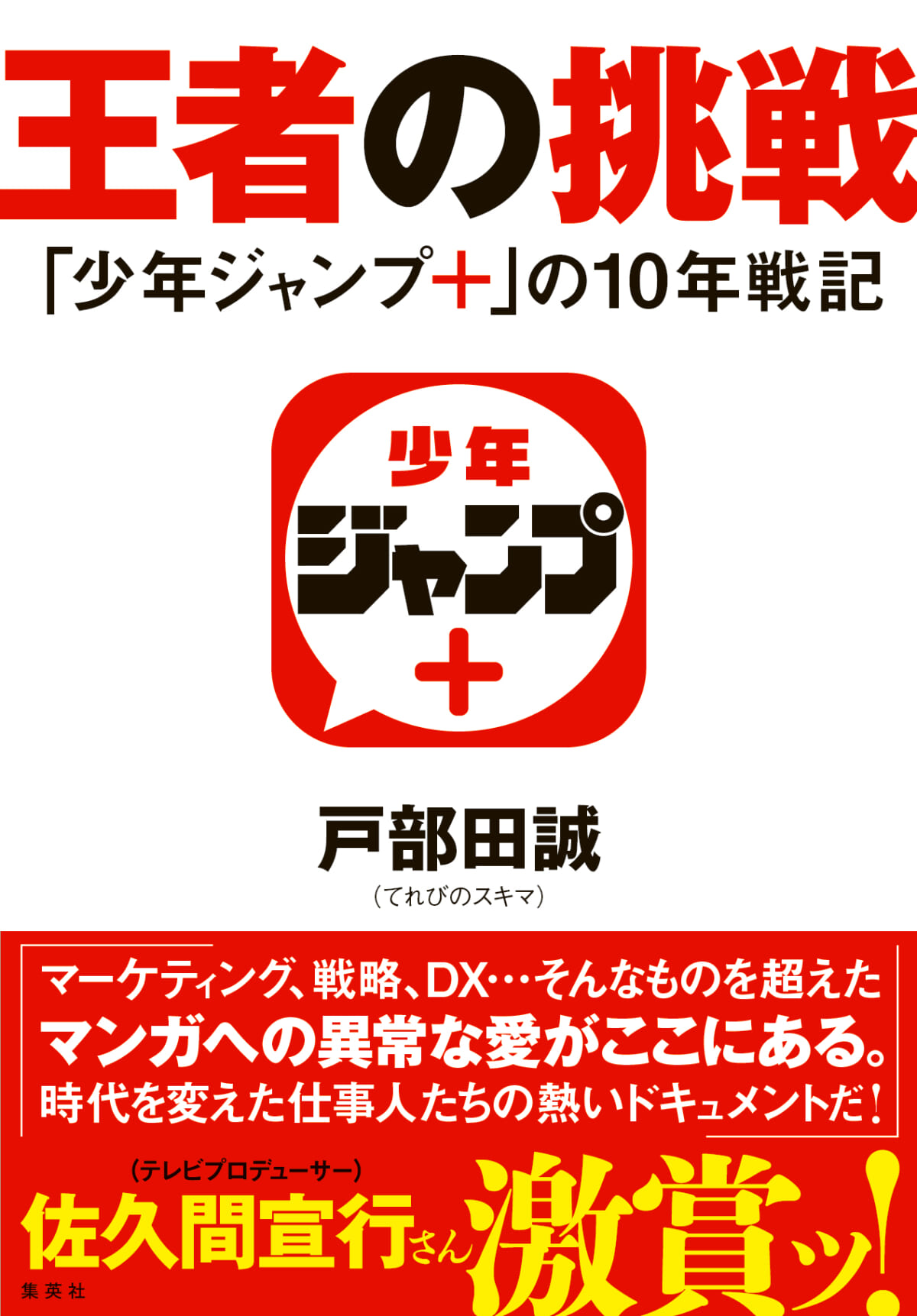
2025/5/9