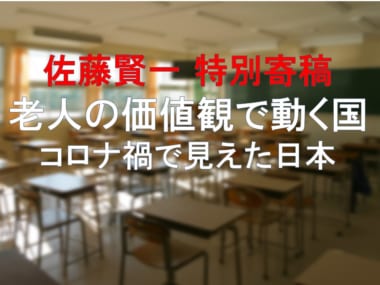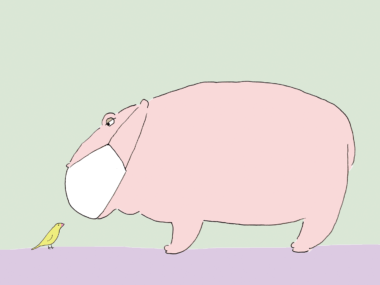2020.7.13
父の死と、「さみしさという遺産」―今年、私は父の年齢を超える
私が帰国してわずか一か月で、父は吐血して倒れ、入院した。すでに末期の胃癌で、余命幾ばくもない状態だった。当時、病院では癌患者に対して告知をしていなかったから、私たち家族はその事実をひた隠しにした。日に日に痩せていく父を見ながら、それをなかったかのように振る舞い続けた。もうすぐよくなるってよ、退院も近いんだって。そう言い続ける私たちと、そんな口先だけの誤魔化しに疑問を抱く父との間で、神経をすり減らすようなやりとりが増えた。俺の病気は一体なんなのだと怒りをこめて聞く父に対して、母は口ごもって何もはっきりとは答えなかった。そんな曖昧な態度を貫く母に私は苛立ちを募らせた。なぜきっぱりと否定しないのか。なぜ、うつろな表情で下を向くのか。私の母に対する嫌悪にも似た感情は、どんどん膨らんで、そのうち母を避けるようになり、父のいる病院には母のいない時間を見計らって行くようになった。
父は、詰問の矛先をそんな私へと変えた。ある日、窓際のベッドに座った父が、細くなってしまった足をあぐらに組み、そこに枯れ枝のような両手を置いて、私を睨み付けた。
「お前は俺に嘘は言わないよな? 正直に言え。嘘をついたら、この窓から飛び降りてやる。お前だけは本当のことを言ってくれ。パパは癌なんだろ?」
「そんなわけないじゃない。癌のわけがないよ。パパは胃潰瘍で、もうすぐ退院だよ」
父は、落ちくぼんだ目でさみしそうに私をしばらく見つめたあと、少しだけ笑い、そして私に「もう遅いから家に帰れ」と言った。父が亡くなったのは、それから二週間後のことだ。その日を境に、私の心の奥底に、父のその日の強い悲しみが横たわっているような気がする。
漫画家の松田洋子は『父のなくしもの』のなかで、さみしがりやの父の姿とその死を描き、さみしさが父の生命力であり、彼女自身が、その「さみしさという遺産」を受け継いだと表現した。この言葉に、私は大きな救いを感じた。確かに私も、さみしさという遺産を父から受け継いでいる。私はそれを父から受け取り、何十年も抱え込み、そして父の年齢を超える今になって徐々に吐きだしている。溜め込んだ強い悲しみとさみしさを吐き出すことで、ようやくそれから自分を、そして父を解き放とうとしている。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)