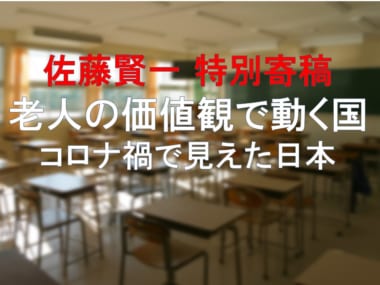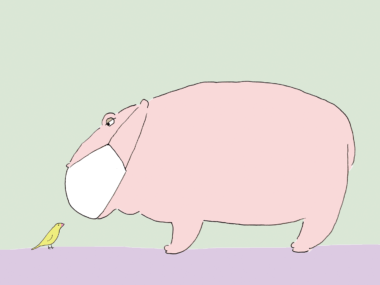2020.7.13
父の死と、「さみしさという遺産」―今年、私は父の年齢を超える

父が四十九歳で亡くなったのは、今から三十年前のことだ。亡くなる前年、親元から離れ海外で暮らしていた私に母が、父の体調が優れないのだと連絡してきた。数か月後に帰国することはすでに決まっていた。はやる気持ちを抑え、異国での最後の日々を過ごして帰国した。当日、空港に迎えに来てくれているはずの父を約束の場所で探したものの、一向に見つからない。私は当時十九歳で、たった一人で飛行機を乗り継ぎ帰国する勇気はあったというのに、そこに父の姿が見えないというだけで、胸が苦しくなるほど悲しく、泣きそうになった。もしかしたら違う国に辿りついてしまったのかもしれないと不安で仕方がなくなったそのとき、とても痩せた男性が、同じ場所で誰かを探していることに気づいた。それが父だとわかるのに、しばらく時間がかかった。父の方はと言えば、私が以前に比べ、あまりにも体重を増やして帰国したために実の娘だとわからず、困惑した様子だった。私と父は、ようやく互いに気づき、驚きの表情で見つめ合いながら、「太ったなあ!」「痩せたねえ!」と言い合った。なんとなく照れくさい気持ちを隠しながら、私たちは父の白いセダンに乗り、故郷まで何時間もかけてゆっくりと戻った。車中、異国での思い出話を披露すると、父は上機嫌で笑顔になった。痩せてシワだらけになってしまったその笑顔を見ながら、病院に行ったのかと聞く私に、父は何も心配するなと言った。
私と父は昔からうまが合った。父は私を溺愛していたし、どこへでも連れて行き、なんでも買ってくれた。家のなかでは、母と兄がなにかにつけて意見が合い、父と私が常に行動を共にしていた。根っからの変わり者だった父は、社会人としては失格だったのだと思う。勤めていた職場では、出勤するよりも、欠勤していることの方が多かった。夕方になるとゴルフの打ちっぱなしに行き、思い切り打ったあとは飲みに行き、へべれけに酔って帰宅するのが日常だった。そんなこんなで、父と母は頻繁にケンカをしていたし、同居していた母方の祖母は、そんな父を毛嫌いしていた。でも私は、そんなダメ男の父が好きだった。父はいつでも私に珍しいものを買って持って帰ってきてくれた。発売されたばかりのステレオ、タイプライター、ワープロ。父が私のために持ち帰るものはすべて、私にとって宝ものになった。
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)