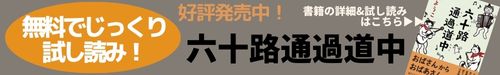
2024.4.10
部活帰りのラーメン
当記事は公開終了しました。
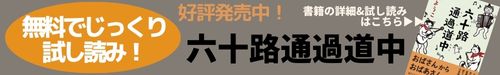
2024.4.10
当記事は公開終了しました。

六十路通過道中

六十路通過道中

わたしとふたりで旅をする 京都・大阪・神戸 西の都のものがたり

ちゃぶ台ぐるぐる
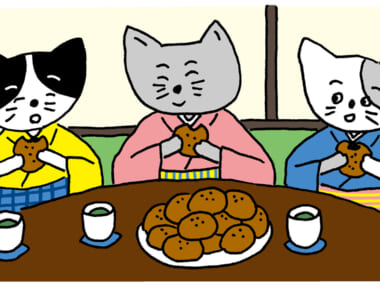
ちゃぶ台ぐるぐる

ちゃぶ台ぐるぐる

2026/4/24
NEW

2026/2/26
NEW

2026/1/26

2025/11/26

人生競馬場

実録・メンズノンノモデル 創刊40年の歴史を彩る男たち

実録・メンズノンノモデル 創刊40年の歴史を彩る男たち

~40代、そろそろ誰かと暮らしたい~ 超実践! アラフォー婚活のかなえ方