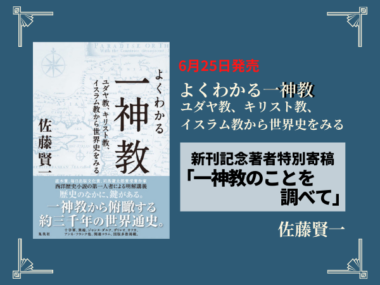2021.9.6
第30回 歌人の月
川の水でむいた里芋を、富山の母が両腕で抱えきれないほど送ってきてくれたことがある。
表面を乾燥させた里芋は、新聞紙でくるんで冷暗所で保管すれば、冬の間じゅうもつ。煮っころがしにするか、揚げるか。または、蒸して潰すか。料理心が刺激されるが、それもこれも、皮をむかれた状態で手にしている幸運ゆえ。最近では、皮むきと独特のぬめりを嫌がって、冷凍の真っ白な里芋のほうが人気だそうだ。手をかけた末に顔を出すあの粘りと、むんと立ちのぼる濃い香りこそが、里芋の持ち味だというのに。
なかでも私が気に入っているのが、里芋のぬめりを生かすスープだ。皮の処理にひと工夫。里芋を買ってきたらすぐに、たわしでよく洗ってざるに並べ、ひと晩乾かしておく。こうすることで皮がむきやすくなり、手が汚れるのも防げる。
厚めに皮をむいた里芋は、水にさらしてぬめりをさっと洗い流してから、鰹節と昆布で引いたたっぷりの出汁で煮る。下茹でをしない、直炊きという調理法だ。煮はじめの里芋は、どこか青白く澄んで、私の好きな色である。里芋が柔らかく煮えたら、白味噌とバターを加えて好みの味にととのえ、仕上げに和辛子を添える。箸で割れば、ほこほこして湯気があふれ出し、クリーミーな汁が里芋にまとわりつく。里芋のようにぬめりのある食材は、どこかにひっかかりを作ったほうがバランスが取れる。そのための和辛子である。今回は蓋付きのお椀に盛ってよそ行きな感じにしたけれど、皮付きのまま蒸した里芋を、皮をつまんでつるんとむき、潰してから器に入れ、汁を張ってもいい。
蒸すといえば、皮付きのまま頭をほんの少し切り落としてから蒸した小ぶりな里芋には、きぬかつぎという特別な呼び名がある。お月見には欠かせない。
お月見の晩に腕まくりをして団子をこしらえたのが、与謝野晶子である。鉄幹との間に十二人の子をもうけた、子だくさんの人。晶子のレシピは、ふかした里芋を潰してから生地に練り込み、両端をちょっととんがらせて里芋の形にととのえられていたという。さらには、皮に見立てたこしあんを巻いたと知って、なんておしゃれなと驚いたが、それもそのはず、晶子は堺の和菓子屋の娘である。
その晶子の、やさしい表情の写真を見たことがないと気がついたのは、最近のこと。いつも唇を一文字に結んでカメラを見据えていた。愛に生きた女性というイメージがあるが、私は、与謝野ブランドをプロデュースした仕事人としての姿に惹かれる。よく詠み、よく食べ、たくさん旅をした。大きなエンジンを積んで、与謝野晶子という役を演りきったひとだった。
平塚らいてうとの母性保護論争では、女性も職業をもって自立すべきと説き、母性は国家によって保護されるべしとの立場を崩さなかったらいてうと、真っ向から対立。両者の溝は埋まることはなかった。百年後の今もなお、女たちはどう生きることができるのか、迷い、不安でいる。そもそも正解などないのだ。
元始、女性は実に太陽であった──らいてうは『青鞜』創刊に寄せてこう書いた。
〈今、女性は月である。他に依って生き、他の光によって輝く、病人のような蒼白い顔の月である〉
だからこそ、女性たちよ立ち上あがれと旗を振った。コピーセンスはさすがだけれど、私には、新雑誌のために思いついたコンセプトをこねくり回しているように思える。
冬の夜の星君なりき一つをば云うにはあらずことごとく皆
夜空を見上げるなら、晶子のようでありたい。生きる喜びを、普遍の命へと結び、世界を肯定する心の強さに打たれる。
悔いのない人生を生きているか。十五夜、月を鏡にして、自分の姿を問うてみる。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)