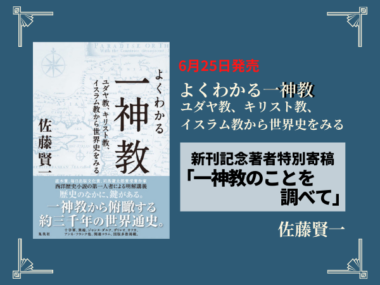2021.9.6
第30回 歌人の月
里芋の葉茎を背負った女性と、同じ車両に乗り合わせたことがある。
場所は新宿、山手線。高尾のほうから戻ってきたのだろうか、そのうらやましい持ち物を見た瞬間、子どもの頃よく食卓にのぼった赤いずいきを思い、口のなかがじゅっと酸っぱくなった。東京で葉茎に出くわしたのは、この一度きりだ。
雨傘にもなりそうな大きな葉を見れば、もともとは熱帯の植物なのだと分かる。耐寒性を身につけながら日本列島を北上したものの、秋田・岩手より北では現在でも栽培が難しいという。秋の初めから年明け二月頃までが旬。根っこに毛むくじゃらの実が連なり、子孫繁栄を象徴する野菜でもある。
私が生まれ育った富山県砺波市は、散居村と呼ばれる風景で知られる。広大な砺波平野に家々が点在し、それぞれの屋敷を取り囲むようにしてカイニョ(防風林)が築かれている。台風や夏の日差しから家を守るその役割に、保守的でよそ者を受け容れにくい土地柄を重ね合わせ、十代の頃は美しいと感じるどころか、未来に立ちはだかる障壁に思えた。
家と家の間を占めるのは、言葉を奪うほど圧倒的な田んぼと、その間を縫って流れる水路である。航空写真で見ると、水田は夕暮れには赤い鏡となって光り、初夏には一面の濃緑が視界を覆う。明確な農地計画などおそらくなかったろうに、水路の配置は行き届いていて、精巧だ。
田んぼに水を引き入れるための水路にかかっていたのが、水車式の里芋洗い装置である。都会のひとはどんなものかご存じないかもしれない。短冊型の木板を連ねて筒を作り、川の流れによって回転するように組み立てたもので、中に里芋を入れて蓋ができるようになっている。
里芋同士がぶつかり合うことで、皮はすっかりむかれ、なめらかな肌が現れる。故郷の田んぼの光景を思い出すとき、そこには必ず、ごろん、ごろん──川底を這う里芋の音が鳴っている。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)