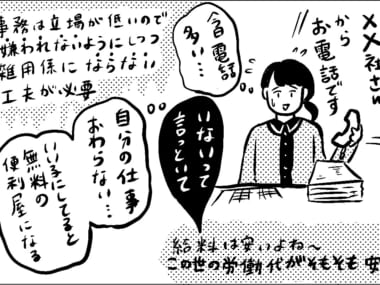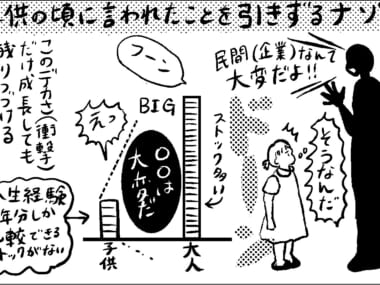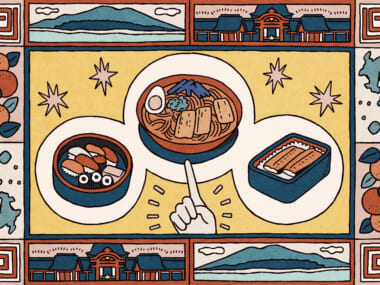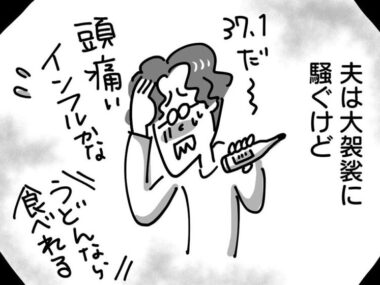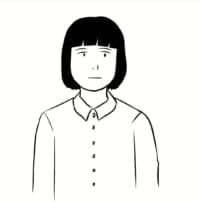2025.1.22
コロナ禍の激鬱会社員生活……それでも実家には帰らない理由とは 第21話 私は帰らない
記事が続きます
そんな気持ちに変化が起きたのは、祖母の介護が始まったあたりからだ。90代半ばで亡くなった祖母は、亡くなる3年ほど前から認知症の症状が始まっていた。既にその何年も前から嫁である母がお風呂の介助などを行い、次第にデイサービスを利用するようになり、認知症になってからは完全に“老老介護の現実”が広がっていたようだ。といっても年に一度帰るだけの私は、壁が便まみれ・徘徊・人格が変わったように暴れ回るなどの、“私の想像する介護の惨状”に遭遇することはないのだが、帰省のたびに祖母のトンデモ行動の数々や、入院に付き添った親戚があまりの大変さに体調を崩した話などを聞くと、自分には無理だ……と恐ろしくなった。高齢出産で生まれた私は、同世代より10年くらい早く介護をする側になる計算だ。このことは大学時代からずっと不安視していて、就活の話題になると「でも、介護が始まったら辞めなきゃいけないのかな? やっぱ実家帰んなきゃなのかな? どうしよう」と会社を受ける前から友人に泣きついていた。
その友人からは、「うちは祖父母も健康で同居もしていないから考えたことない」と申し訳なさそうに言われ、地方出身者同士、介護不安の傷を舐め合う気でいた私は豆鉄砲を喰らったものだ。
ある年の大晦日、食事の席で顔を合わせた祖母は、私のことを覚えておらずお客さんが来ているという認識で、「どうも~」とニコニコしながらよそ行きの声を出していた。私はそれを見て悲しくなるかと思いきや、警戒と恐怖の方が優っていた。私を知らない人と同じ家にいるのが怖い。深夜、祖母の隣の部屋で布団に入る時、突然ドアが開き鬼の形相をした祖母に「誰だ! 出ていけ!」と叫ばれ、包丁を振り下ろされるシーンを思い浮かべて眠る。それは心配するというより、覚悟しておくという感覚だった。私は、祖母に対して悲しむでもなく労わるでもなく、暗闇に抱くような恐怖心を抱いた。
最も気が滅入るのは朝だった。一通り朝食の用意を済ませた母が、祖母の部屋に行くと何か叫んでいる。細かな内容までは入ってこないが、「なんだこれ!」「も~!」「なしてこんな……!」と怒りと悔しさと悲しさ、落胆、疲弊、ネガティブな感情全てが混ざった嘆き声が途切れながら響きわたり、時折、祖母の悪びれないのんびりした声が挟まれる。祖母が悪びれないのは認知症とは関係なくデフォルトだが、耳から入ってくる断片的な情報からオムツ関連の惨事を想像し、味のしない白米を口に運んだ。気が滅入るという率直な感想は、息子は抱いても娘は抱いてはいけない気がして罪悪感を覚え、「まいったなもう」としかめ面で戻ってきた母を見て、同調しながら宥めるように相槌を打つ父の適当さに腹が立った。祖母の長男であるこの男は、私の半分でも罪悪感を感じているだろうか。父はこの家で車の送迎役を担っていることは知っているが、それでも「お前の母親だろ! お前がやれ!」と言いたくなる。
記事が続きます
とはいえ、私の本音も全く介護に関与したくなく、手伝うつもりも更々ないので強く責める立場にはないだろう。「イタタタ」と腰をさすりながら台所に行く母、無言で食事を続ける父、ほぼ寝たきりの祖母。母は笑い話のように「寝たきりになった方が楽になった」と言うが、一体、あと何年続くんだろう。あと何年……ふと「目薬」という言葉が脳裏に浮かんだ。いつだったか、金融機関のパートさんが与太話として言っていたのだ。「目薬を毎日のご飯に混ぜるとバレないとかね」。これはたしか、まさにこういうシチュエーションの話だった気がする。ゆっくりゆっくりと寿命を縮める方法だったような……。目薬が口に入ったからといって人体に害があるとは思えないのだが、それでも、母のこの重労働を終わらせる方法は目薬なんじゃないか。実行には移していないが、そんな発想になる自分にショックを受けることもなく、真剣だった。母のためを思ってというのは建前で、半分は自分のためである。今母が倒れたら、今度は私の番だからだ。祖母の世話を母に任せて当然のような顔をしている団塊世代の父が、介護を自分の仕事だと買って出るとは思えない。きっと父は、自分の仕事は娘を召喚することだと判断し、私は負けるだろう。こういう場合、完全に傍観者を決め込む人間が強い。少しでも罪悪感や責任感を感じた側は折れることになる。父には衛生観念が欠けていることを知っているので、介護される人が気の毒だとわかるし、娘が献身的でないことを母は人に隠すだろうと想像する。その日が来たら、年収300万の一般事務の仕事にしがみつく自信がない。東京を捨てて、でも絶えず後悔に襲われ、ぐちゃぐちゃに引きちぎられた心を引きずりながら地元に帰り、死ぬまで両親を責め、そして……その先は想像がつかないのだった。
記事が続きます
だからある時、親を捨てようと思った。法的には完全に親を捨てることはできないそうなのだが、気持ちの問題だ。酷いと言われても後ろ指を指されても、軽蔑されても100倍楽だろう。現実的には、最大限行政を頼り利用し尽くし、それでも足りなければ外部サービスを利用し、絶対に自分の仕事や生活を優先するよう努める、という割と現代であれば普通の考え方だが、当時は「親を捨てる」くらいの宣言をしないと辿り着けない発想だった。考えてみれば、うちの父だって、また思いつく限りの甥っ子たちだって、仕事を辞めて介護をすることを宿命のように思った瞬間などないだろう。自分事として捉えないという父の姿勢を、私も見習ったのだ。
この決断をしてからというもの、憂鬱だった帰省を楽しめるようになった。無邪気に車窓の景色を撮影し、地元の名産品や郷土料理に興味を持ち、観光地気分で町を眺める。もうここには帰らない。私には侘しい給料の仕事しかないが、それと心中するのだろう。なるほど、前向きに生きるということが死ぬ覚悟を伴うとは難儀なものだ。寂れた町に味わいを感じ、電車やバスの本数が少ない不便さにエモさを見いだし、東京にあるチェーン店が乱立する国道に「つまらないなあ」などと勝手なことを思う。昔は嫌だったシャッター商店街のアートプロジェクトにも、「いろんなことをやっているんだなあ」である。そうやって、地元の良さを“再発見”している私を、数メートル後ろから本来の私が見ている。老いた両親と同居する未来を選ばざるを得なかった本来の自分が、「何を遊んでいるんだ」と、恨みがましい軽蔑した目でこちらを見ている。
結局、真っ当な会社で長く働き続ける自信がなく、1年を待たずに辞めることにした。また仕事を探さなければ。残りの出勤日数を数えながら、神田や人形町、日本橋の町を楽しんだ。整然とした大通り、荘厳な洋風のビルに、古びた日本食の店、東京はすぐ隣の街でも雰囲気がガラッと変わって面白い。日本橋三越に初めて入り、お茶をしながら「信じられない」と思う。これに限らず、東京らしい街並みを見ながら食事をするたびそう思う。こんな人生、続くわけない。私にとって人生とは、地元の、雪に閉ざされた家そのものを指す。どこにも行けず、雪かきで最低限の道路を確保し、天気に左右されながら徒歩圏内で楽しみを見つけて満足する。
無力感が忍耐を育て、逞しく同じ場所に留まる。だから、自分の意思で会社を辞めたり、地下鉄を使って簡単にどこまでも移動できたり、歩を進めると違う景色が広がる東京なんて、そこにいるなんて、そんなのは自分の人生じゃない。
でも、だからこそ、もうしばらく東京で遊ぶのだ。

次回は2月19日(水)公開予定です。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)