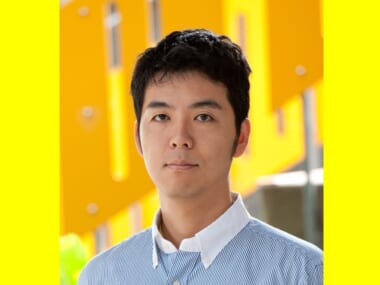2025.4.2
不安や恐れには科学的な「価値」がある? ソニーコンピュータサイエンス研究所・小泉愛氏に聞く
こんな問いを考えたことがある人は多いかもしれません。
そういった「赤い感じ」や「コーヒーの香りのあの感じ」等は、〈クオリア〉と呼ばれています。
重要なテーマであっても、これまで科学的にアプローチしにくかった〈クオリア〉。
そこにいま、様々な分野の最先端の研究者たちによる、新たな研究が進んでいます。
〈クオリア〉を探求する多様な研究者に話を聞く、インタビュー連載です。
脳科学的な手法によって感情を研究している小泉愛氏(ソニーコンピュータサイエンス研究所)は、ネガティブなものだと思われやすい不安や恐怖にも「機能」がある可能性があると述べる。私たちにとって身近なクオリアである感情の役割とは。
(聞き手・構成・文責:佐藤喬、特別協力:藤原真奈)

記事が続きます
感情クオリアの意味
「嬉しい」とか「不安だ」といった感情は主観的な意識内容、つまりクオリアと考えることができます。ただ、感情は、意識をめぐる議論でしばしば話題に上がる「赤の赤さ」といった色のクオリアなどと比べると、少し性質が異なるようです。
クオリアは進化の過程を経て今を生きる私たちに備わっているものですから、そこに何らかの「機能」が潜んでいる可能性があるのではないでしょうか。その点では、色のクオリアは、たとえば果物の熟れ具合を判断するなど、外界のものごとを正確に知るために役立つ可能性があります。
では、感情のクオリアはどうでしょうか。
たしかに、色のクオリアと同じように、外界の特定の対象によって感情のクオリアが引き起こされることはよくあります。鬱蒼とした森でイノシシに襲われて恐怖を覚える、などです。
しかし、感情には「持続する」という特徴があります。上記の例ならば、目の前からイノシシという対象が消え去った後でも、その恐怖の感じがただちには消えず、何日も、あるいは何週間も不安として残ることは珍しくありません。
感情にはもう一つ、別の特徴があります。不安の具体的な原因になったのが特定のイノシシだったとしても、イノシシに限らず動物一般や、あらゆる森に対して不安が広がることがあります。これは抽象化が起こっていると解釈できます。
この「持続」と「抽象化」という二つの特徴によって、感情は行動に影響を及ぼすかもしれません。今の例ならば、なんとなく森に入りたくない気分が続くとか、動物の鳴き声から距離を置くようになることで、結果的に危険から距離をとる行動に繋がる可能性があります。
社会と感情クオリア
言うまでもなく、感情のクオリアも、他のクオリアと同様に、主観的にしか感じることはできません。しかし、感情には表情などを介して社会的に伝播するという特徴もあります。
たとえば、強盗のニュースが大きく報じられたことで社会不安が広がるとか、スポーツの試合に対して社会が熱狂することがあります。人間は社会的な動物ですから、不安の感情を共有することで、たとえば野生動物除けの火を絶やさないように交代しながら見守るなどの協調行動が促される可能性があります。また、熱狂を共有することが集団の結束や士気を高めるといった社会的な機能に結びついている可能性も考えられます。
うつ気分は身を守るため?
現代社会ではネガティブに評価されがちな感情特性にも、適応的な側面がある可能性が考えられます。
犬などの動物を使った、「学習性無力感」についての研究をご存じでしょうか。簡単に説明すると、被験動物に電気ショックなどのストレスを与え続けると、最初は逃げようともがくのですが、やがて諦めて抵抗しなくなる現象のことです。動物をストレスから逃れられる環境に移しても、やはり逃れようとせず諦めたままです。
学習性無力感は、人間のうつ状態とよく関連付けられています。うつ病は、一般的には薬などで治療すべき「病気」だとみなされていますが、学習性無力感の実験を踏まえると、うつ状態に対して異なる視点が生まれるかもしれません。
逃れようのないストレスから無理に逃げようとしても、リソースを無駄に消費するだけです。それならば、リスクの高い状況では、抵抗せずにエネルギーを温存することが合理的とされる場面もあるかもしれません。動物をストレスから逃れられる環境に移してもやはり抵抗しないのは、自然環境下ではいきなり状況が変わることがまずないからでしょう。
このような視点からは、うつ状態にリソースを温存するという機能的意義がある可能性も考えられます。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)