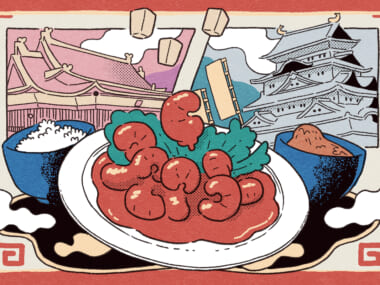2022.10.19
荻上直子『かもめ食堂』が肯定する人間の欲望――それぞれの思い出を抱えて、人々は世界の終わりを生きる
母を早くに亡くしたサチエは、小学生の頃から家事を担当していた。ただ、運動会と遠足の日だけは父親がおにぎりを作ってくれたという。「おにぎりは自分で作るより人に作ってもらった方がずっとうまいんだ」という父親の言葉どおり、それは「とってもおいしかった」のだと。「日本人のソウル・フードだから」というのは建前に過ぎない。サチエは、彼女のごく個人的な思い出を大事にしているからこそ、シンプルなおにぎりにこだわるのである。
劇中にはサチエの父と似たようなことを言うフィンランド人が出てくる。コーヒーメーカーを取り戻そうとして泥棒まがいのことをしていたマッティは、その前に客としてかもめ食堂を訪れている。その際、サチエにおいしいコーヒーのいれ方をレクチャーし、「コーヒーは自分でいれるより人にいれてもらう方がうまいんだ」と言うのである。
サチエはのちに、店に忍び込んだマッティを合気道の技で組み伏せる。彼女は幼い頃から合気道を嗜んでいたと言い、現在でも就寝前に膝行をおこなっている【図6】。それはおそらく「武道家」だった父親の影響だろう。彼女は父と同じようなことを言う男に、父の影響で始めた合気道の技をかけたことになる。サチエがマッティを放免し、あまつさえおにぎりまで振る舞ったのは、そこに父の影を見たからではないだろうか。もちろん、彼女の性格であれば誰であってもそうしたのかもしれないが、いずれにせよ、映画としては細部の設定が響き合う見事なシーンになっている。

「思い出」は、リーサがかもめ食堂を訪れた理由としても使われている。彼女は窓越しに店内のサチエを睨みつけている怖そうな女性として登場する。彼女がサチエを見ていたのは、夫が家を出た直後に死んでしまったという飼い犬のクッカによく似ていたからだった。サチエもまた死んでしまった猫と、それに連なる両親の思い出に導かれるようにして生きている。サチエとリーサは、合わせ鏡のような関係にある。
人はそれぞれの思い出に基づいて欲望を抱く。現実世界でその欲望が解消されることはほとんどない。『かもめ食堂』は、ともすればダークサイドに陥りがちな人々の欲望を軽やかに肯定してみせる。各々の欲望が絶妙な均衡を保って、そこに居心地のいい場所を作り出している。
サチエは理想的な母の姿を求めて、あるいは慕っていた父の影を追ってフィンランドにやってきたと僕は考えている。最初のうちこそ閑古鳥が鳴いていた「かもめ食堂」には、やがて客も含めてサチエが好意を抱けるような人間ばかりが集まってくる。その数はどんどん増えていき、当初は見向きもされなかったおにぎりを注文する客も現れ、最後は満席になる【図7】。それはサチエの密やかな欲望が次第に満たされていく過程であり、観客はその過程を彼女と共有する。

だから僕たちは『かもめ食堂』を見ると癒やされるのである。それは映画が見せてくれる夢の最たるものだろう。

【図版クレジット】
図1~7 『かもめ食堂』荻上直子監督、2006年(DVD、バップ、2006年)
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)