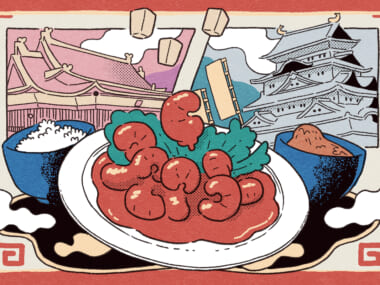2022.10.19
荻上直子『かもめ食堂』が肯定する人間の欲望――それぞれの思い出を抱えて、人々は世界の終わりを生きる
ストーリーを追うだけでなく、その細部に注目すると、意外な仕掛けやメッセージが読み取れたり、作品にこめられたメッセージを受け取ることもできるのです。
せっかく観るなら、おもしろかった!のその先へ――。
『仕事と人生に効く 教養としての映画』の著者・映画研究者の伊藤弘了さんによる、映画の見方がわかる連載エッセイ。
前回は、是枝裕和監督作品『DISTANCE』(2001年)を中心に、是枝作品の中で描かれる「水」の表現を考察しました。
今回は、フィンランドブームの火付け役にもなった荻上直子監督による人気映画『かもめ食堂』(2006年)を取り上げます。
『かもめ食堂』冒頭の違和感
荻上直子監督の新作『川っぺりムコリッタ』の公開に合わせて、久しぶりに代表作の『かもめ食堂』(2006年)を見直してみた。以前は特に気に留めていなかった冒頭のモノローグに、何やら不穏な気配を感じた。
『かもめ食堂』は「かもめ」をめぐるサチエ(小林聡美)のモノローグで幕を開ける。フィンランドの「丸々太った」「でかい」かもめが、サチエが小学生の頃に飼っていた巨漢三毛猫のナナオを思い出させるという内容である。かわいがるあまりにたくさん餌を与えていたところ、ナナオはどんどん太って死んでしまう。その翌年には母親が事故死する。しかし、なぜか猫が死んだときよりも涙の量は少なかったと言う。
サチエは自分は太った生き物にとても弱く、母親は痩せっぽちだったと、その理由らしきものを述べている。しかし、この理由はどことなく「後づけ」感がある。じっさい、彼女は劇中でしばしば後からこじつけた適当な理由を口にする。このモノローグでも本心を隠しているような印象を受けた。
ここには「北欧フィンランドを舞台にしたオシャレな映画」から逸脱する何かがある。「見るものに癒しを与えてくれるようなピースフルでハートフルな映画」というイメージに収まりのつかない過剰さを感じたのである。
映画にとって冒頭は特に重要なパートだ。まだ現実の側に意識が残っている観客の心をつかみ、作品世界のなかに引き込まなければならない。そこに無意味なシーンが置かれることはまずない。もしも冒頭に違和感の萌芽があるとすれば、それは何か重要なことを示唆している可能性が高い。
「猫的なもの」が結ぶ奇縁
『かもめ食堂』にはナナオ以外に少なくとも二匹の猫が登場する。一匹目は、最初の客としてやってくる日本かぶれの青年トンミ・ヒルトネン(ヤルッコ・ニエミ)のTシャツに描かれているニャロメである【図1】。赤塚不二夫の漫画に出てくる、猫をモデルとしたおなじみのキャラクターだ。

もう一匹は、ロストバゲージに見舞われた日本人旅行者のマサコ(もたいまさこ)が現地のおじさんから突然預けられる猫である。行方がわからなかった荷物が出てきて、そろそろ帰国しようと思っていた彼女は、猫を預かってしまったことで帰るに帰れなくなり、滞在を延ばすことにする【図2】。

記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)