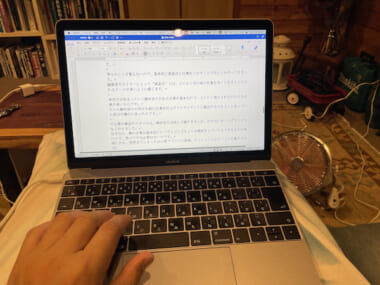2022.7.13
岩井俊二『Love Letter』のヒロインが一人二役である理由 ――あるいは「そっくり」であることの甘美な残酷さ
ストーリーを追うだけでなく、その細部に注目すると、意外な仕掛けやメッセージが読み取れたり、作品にこめられたメッセージを受け取ることもできるのです。
せっかく観るなら、おもしろかった!のその先へ――。
『仕事と人生に効く 教養としての映画』の著者・映画研究者の伊藤弘了さんによる、映画の見方がわかる連載エッセイ。
初回は、岩井俊二監督の長編映画デビュー作『Love Letter』(1995年)を取り上げます。
そっくりであるというのは、愛にとって残酷な制度であり、
しかもそれが、人を裏切る夢の定めなのである。
――ロラン・バルト
『明るい部屋――写真についての覚書』花輪光訳、みすず書房、1997年
久しぶりに岩井俊二監督の『Love Letter』(1995年)を見直して「そういえばもうずいぶんと長いこと手紙を書いていないなあ」と思うなどした。
こんなふうに書くと、あたかも文通文化をリアルタイムで経験した人間であるかのように思われるかもしれないが、1988(昭和63)年生まれの僕が高校生の頃にはすでに携帯電話が一般に普及していた。家族、友人、恋人とのやりとりはもっぱらメールである。焦燥感に駆られて「新着メール問い合わせ」を連打していた世代といえば、伝わる人には伝わるだろうか。
当然、『Love Letter』も公開当時に見たわけではない。いくら世間を賑わせた話題作とはいえ、6歳の小学一年生が見る映画でないことは親もわかっていただろう(97年公開の『もののけ姫』すら見せてもらえなかった)。
僕が『Love Letter』を初めて見たのは大学生のときだった。それからでもすでに15年近くが経過しているのだから、光陰矢のごとしとはよく言ったものである。まだ映画の勉強を始めたばかりの頃で、「おもしろい」と思ったことは覚えているが、その感覚をうまく言語化できないでいた。
それから15年間かけて、映画を見続け、映画について書かれた本を読み漁り、そして曲がりなりにも映画について書く仕事に就いた。右も左もわからない状態でとにかく有名な映画を見まくっていたあの頃よりは、何かを言い当てることができるようになったと思う。
もちろん、「おもしろい」以上の映画の感想など持つ必要がないと考える人もいるだろう。娯楽なのだからそれで何の問題もない。SNSでは気の利いた感想コンテストが展開され、バズを競い合っている昨今だが、そんなものにかかずらうこともない。
とはいえ、人間は欲深い生き物である。自分が感じたあの感動をどうにか言葉にしてみたいと思うこともまた自然な感情だし、それは自分の経験、ひいては自分の人生を大切にすることにつながってくる。誰に誇るためでもなく、自分の感動を自分で理解してあげること。孤独な人生を生き抜くには、それくらいの贅沢が許されてもいいではないか。
作品の核心をつかむことを、英語では「get」を使って表現する。ポケモン以外にも使える汎用性の高い言葉なのである。この連載では、僕が映画を「ゲット」していく過程を綴っていきたいと思う。
言うまでもなく、何を作品の核心と捉えるかは人によって異なる。その意味できわめて個人的な文章にならざるをえないことを最初にお断りしておく(あるいは、単に僕が孤独を紛らしたいだけの文章なのかもしれない)。それでも、読者のみなさんがそこから何かを感じ取ってくれるのではないかという期待も抱いている。
僕が書くもののなかには、きっとみなさんが同意できない感想もあるだろう。そのときは「なぜ同意できないか」「自分はどう感じたのか」を考えるきっかけにしてもらえれば幸いである。
さて、すっかり前置きが長くなってしまった。今回は『Love Letter』である。
「手紙」が鍵を握る作品であることは間違いないが、「一人二役」もまた重要な要素だと思う。中山美穂の一人二役は、単に話題性を狙っただけでなく、この映画のテーマの根幹に関わっている。
ストーリーを辿りながら、そのゆえんを説明していきたい。

記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)