2024.11.21
「非モテ」概念で遊ぶうちに取り返しがつかなくなる男子校出身者の危険性【学歴狂の詩 最終回】
当記事は公開終了しました。
2024.11.21
当記事は公開終了しました。

学歴狂の詩



シン・ゴールデン街物語
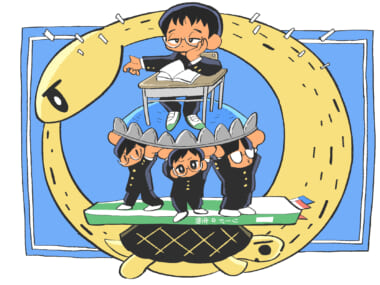
学歴狂の詩

学歴狂の詩

2025/8/26
NEW

2025/6/26
NEW
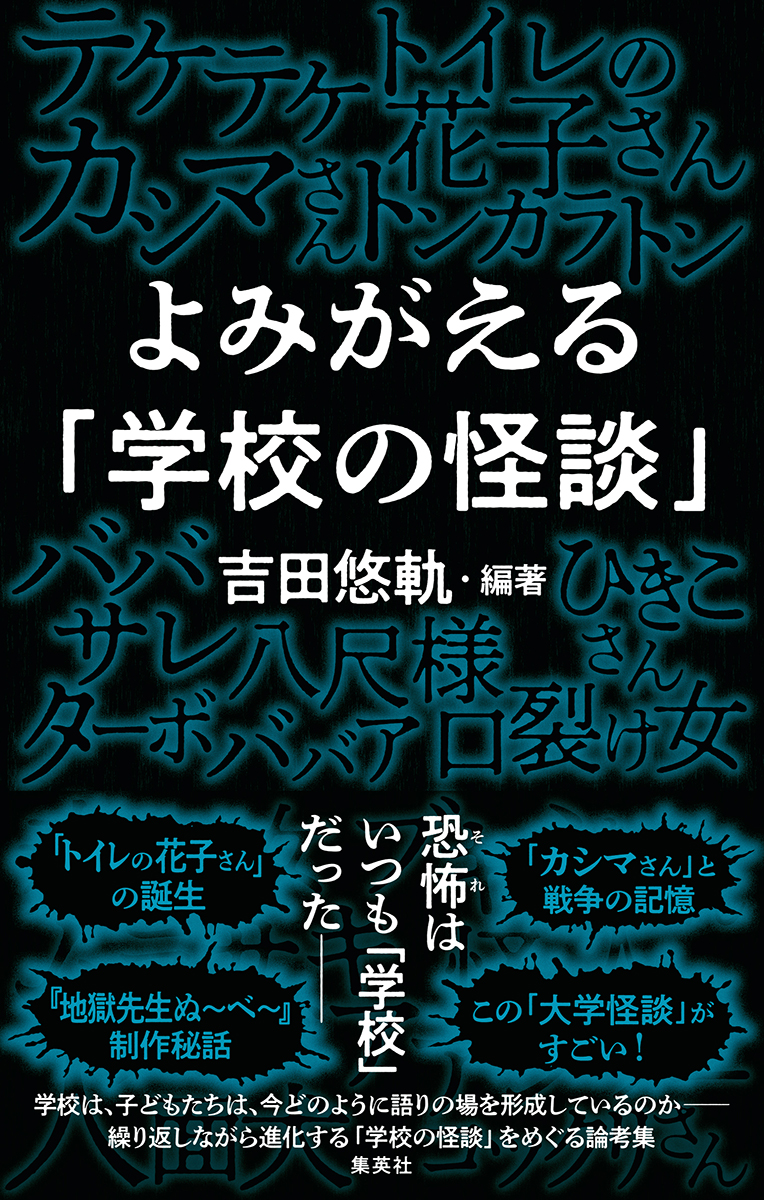
2025/7/4
NEW

2025/5/26

白兎先生は働かない

ケアとアートのダンス ~アクセシビリティのためのプロジェクト・レポート~

もう一度、君の声が聞けたなら

私たちは癒されたい 女風に行ってもいいですか?