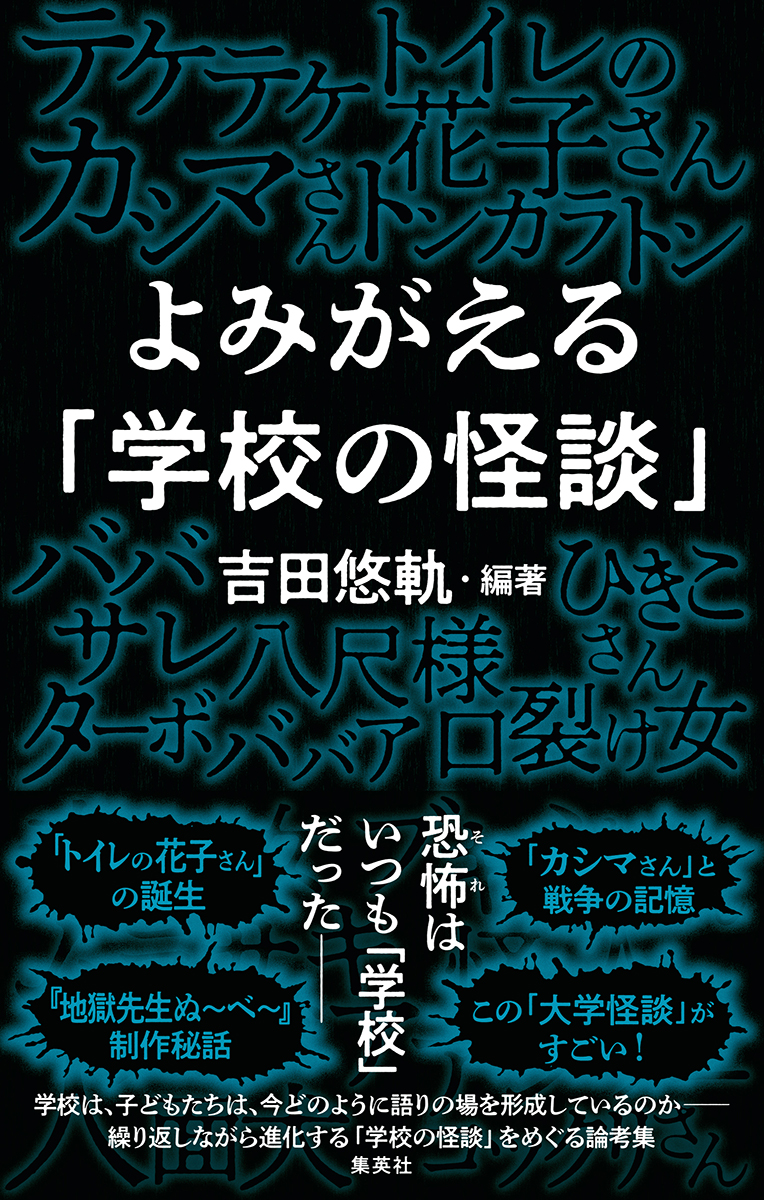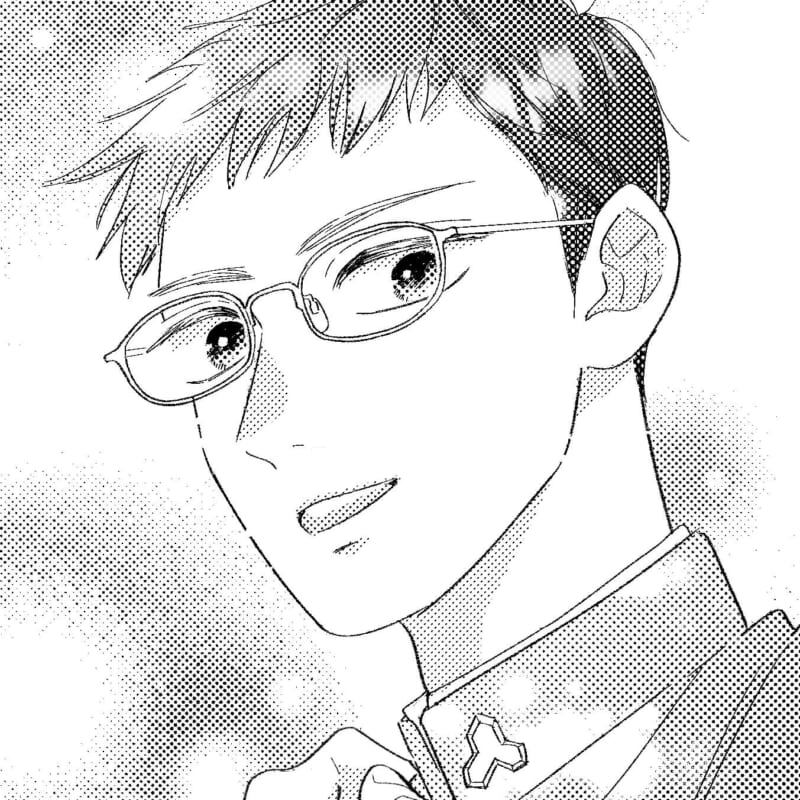2023.7.20
天才・濱慎平がつぶやいた「こんなんもう手の運動やん……」【学歴狂の詩 試し読み】
濱の言葉に受けた衝撃を生涯忘れないだろう
結果として、濱は東大文一を秒殺した。それからは大道芸にハマったりネトゲ廃人になったりと、高校時代の姿からは予想のつかない方向に走ったようだが、さすがの濱でももう就職対策が間に合わないぞ、というところから一気に勉強して今度は公務員の国家一種試験を秒殺、今では官僚として輝かしいエリートコースを歩んでいる。人生の正解など誰にもわからないが、恐らくそれは濱の超頭脳が導いた最適解だったのだろう。
しかし、奇しくも京大文学部に入った私は、もし濱がこっちに来ていたら、と想像することがある。当初の希望通り歴史家になってとんでもない発見をしていたかもしれないし、もしかすると文学に目覚めて偉大な作家になっていたかもしれない。受験の帝王がそのまま文才に恵まれているわけではもちろんないが、濱には間違いなく文才があった。私はある日の高校の休み時間、ルーズリーフにぎっちりと文章を書きつけている濱を見た。「何してるん?」と聞くと「ひまつぶし」と言うので見せてもらうと、そこにはバチクソに難解だが文章の筋は通っており、しかし内容が一切ないような謎の文章があった。当時は「なんこれ」と笑っただけで内容もほぼ忘れてしまったが、強烈なインパクトがあったことだけは覚えている。今の知識でたとえてみると、蓮實重彦や大江健三郎や吉田健一の文体をごちゃまぜにして書かれたベケット、みたいな感じだった。濱はきっと、何にでもなれたのではないかと思う。
「こんなんもう手の運動やん……」
私は濱のこの言葉に受けた衝撃を生涯忘れないだろう。どんな分野に進んだにせよ、濱ならばあらゆる対象を「手の運動」へと収斂させた後、そこを超え出るものの煌めきを見出すことができたのではないか? もちろん、これは私の青春時代のスーパースターに対する勝手な神格化かもしれない。だが、私は濱以上に私の戦意を喪失させる人間にいまだ出会ったことがない。
ついに発売! 話題沸騰中!

あまりの面白さに一気読み!
受験生も、かつて受験生だった人も、
みんな読むべき異形の青春記。
——森見登美彦さん(京大卒小説家)
最高でした。
第15章で〈非リア王〉遠藤が現役で京大を落ちた時、
思わず「ヨッシャ!」ってなりました。
——小川哲さん(小説家・東大卒)
ものすごくキモくて、ありえないほど懐かしい。
——ベテランちさん(東大医学部YouTuber)
なぜ我々は〈学歴〉に囚われるのか?
京大卒エリートから転落した奇才が放つ、笑いと狂気の学歴ノンフィクション!
書籍の詳細はこちらから。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)