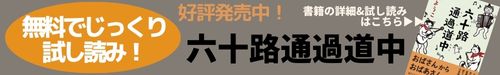
2024.3.13
浅草での味
当記事は公開終了しました。
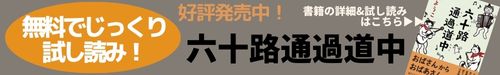
2024.3.13
当記事は公開終了しました。

六十路通過道中

六十路通過道中

わたしとふたりで旅をする 京都・大阪・神戸 西の都のものがたり

ちゃぶ台ぐるぐる


ちゃぶ台ぐるぐる

2026/2/26
NEW

2026/1/26
NEW

2025/11/26

2025/10/24

こんな質問が来る

ヘルシンキ労働者学校——なぜわたしたちは「ボーダー」を越えたのか

孤独の功罪
