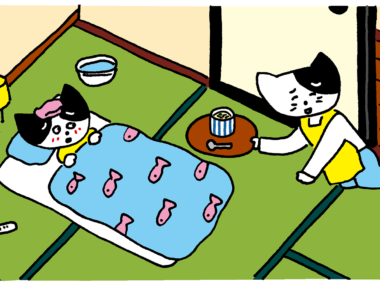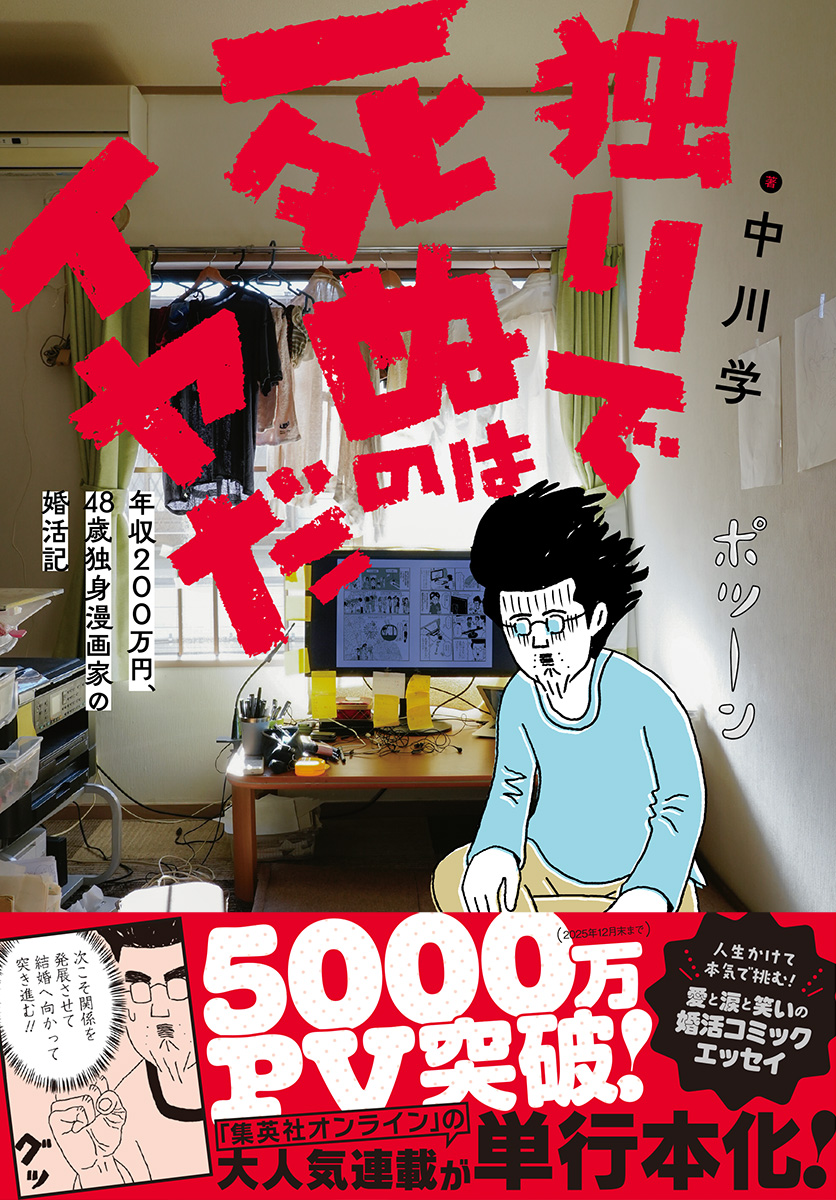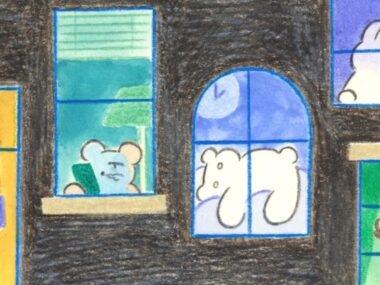2025.3.28
見えること、見えないこと。感覚の違いを超えて生まれる新たな表現とは?【後編】<感覚の点P>展@東京都渋谷公園通りギャラリー
これらには、視覚・聴覚障害のある人とない人がともに楽しむ鑑賞会や、認知症のある高齢者のための鑑賞プログラムなど、さまざまな形があります。
また、現在はアーティストがケアにまつわる社会課題にコミットするアートプロジェクトも増えつつあります。
アートとケアはどんな協働ができるか、アートは人々に何をもたらすのか。
あるいはケアの中で生まれるクリエイティビティについてーー。
高齢の母を自宅介護し、ケアする側としての日々を送る筆者が、多様なプロジェクトの取材や関係者インタビューを通してケアとアートの可能性を考察します。
前編では、東京都渋谷公園通りギャラリーで開催中の「今村遼佑×光島貴之 感覚をめぐるリサーチ・プロジェクト〈感覚の点P〉展」の作品展示について紹介しました。
後編では、〈感覚の点P〉展が私たちにもたらすものを探して、さらにプロジェクト全体を掘り下げます。
記事が続きます
自分のものとして感覚が立ち上がるまでの「触覚時間」
今回の展覧会までに行われた、感覚をめぐるリサーチの過程や成果は、展示室Bのテーブル上にまとめられている。そのなかに、石粉粘土による彫刻が9体、布に覆われた「手でみる彫刻コンペティション」がある。
これは障害のある人が評価されて選ばれるのではなく、審査員として選ぶ側に立つコンペで、2025年1月に実施されたものだ。立体作品を目で見て評価するのではなく、さわるだけで評価してみるという試みで、布の中に手を入れて彫刻にさわる。すべすべで丸いもの、ちょっとギザギザに尖ったもの。
彫刻の後ろ側から手のひらで包むようにさわると全体像がつかめる。なお、布の上からさわると、今度は質感にとらわれず、全体の形や空間をつかむことに集中できる。

また、最後の展示室Cでは、リサーチの記録である《手でみる野外彫刻》シリーズから3つの映像作品が上映されている。
東京都現代美術館が所蔵するアンソニー・カロの野外彫刻《発見の塔》に光島さんがふれている映像は、光島さんが左手で彫刻をさわりながら、右手にiPhoneを持って撮影したものだ。難解な作品に挑むのが好きな光島さんは、4メートルほどある階段も登る。認識が間に合わないからと途中で杖を放り出すシーンもある。
映像は手がさわっている狭い範囲を写しているので、さわっているものの全体は見えない。そのことで光島さんの頭のなかで全体像が把握されていく過程が視覚的に追体験できる。
光島さんは、今村さんとの往復書簡のなかで、この彫刻にふれているときのことを「触覚時間」という言葉で表現した。部分部分をさわっていき、全体の構造がわかるまでにかなり時間を要した。このことは、始まりから終わりまで聴かないと曲全体がわからない音楽にも似ている。
「カラオケで新曲を歌えるようになるまで、何回か繰り返して覚えていくうちに、曲全体の雰囲気がわかってきて歌えるようになりますよね。それと同じように、今村さんの《プリペアド・トイピアノ》のインスタレーションでも、何回か聞いてみると、だいたいどういう音からどういうところから聞こえてくるかわかってきて、空間全体がわかってくるんです」。
単に全体の形を把握するということではなく、対象が自分のものになったという感覚が立ち上がってくるまでが「触覚時間」、なのだ。ちなみに、たとえ目が見えていても、《発見の塔》の複雑な構造をつかむことは容易ではない。
また、光島さんが木にふれる映像もある。連続してさわると木の皮がめくれることもあるため、二本の指で歩くような動作をするさわり方を編み出した。
光島さんは、木には根っこがあって形が面白いし、自分自身を表現するモチーフでもあると思っている。「木をさわってみると、ブロンズや石と異なり木は温かいのがいいですね。でも、上の方は手が届かないし、根っこもさわれることはない。想像で描くしかないけれど、それでいいかなと思うようになりました」。

「触覚時間」には、部分部分をさわって全体をつかむという現在進行形の時間だけでなく、過去の記憶にふれる時間もあるのだろう。
今村さんは以前、光島さんにラインテープで制作した昔のドローイング帳=スケッチブックを見せてもらいながらインタビューをしたことがある。その際、ラインテープの凸面をたどり「このときはこんなことを考えて描いていた」など、想像以上に光島さんが当時のことを覚えていることに驚いたという。
光島さんは「見える人が写真やアルバムを見て思い出すのと同じようなこと」というのだが、手を動かしてつくった時間の回想は、写真に写るという受動的な時間の回想とは記憶の強さが違うのではないだろうか。
時々情報を交換して、それぞれの畑を耕すように
〈感覚の点P〉展では、二人が展覧会に寄せて書いたテキストも掲示されている。今村さんと光島さんの関係性のつくり方は、交わる空間と個々の空間を尊重した、実にちょうどいい距離感だと思う。
今村さんのテキストから一部を紹介する。
(感覚をめぐるリサーチは)コラボレーションの作品を作ることを目指しているわけではないし、作品を作る技術の交換をするわけでもありません。例えていえば、畑を耕すことに似ていると思っています。お互い自分の畑を耕して、時々こんな肥料を使っているとかこんな作物を育てているとかそんな情報交換をして、時には一緒に実験をして、また帰って自分の畑を耕す。それぞれの場所で全然別の作品を作ればいい。それがなぜ僕と光島さんなのかは、たぶん、けっこう離れているのかと思っていたら、どこか奥の方のある場所では畦道を挟んで隣り合っていたというぐらい畑が近かったからです。
それに対し、光島さんはユーモアを交えて返している。
さてぼくは、畦道を歩くのはたぶん苦手で、草に白杖を絡ませてこけてしまうかもしれません。でも転がり込んだ畑が今村さんの耕していた畑だったらラッキーですよね
光島さんは、障害のある人と障害の(少)ない人がコラボレーションするという型どおりのものにはしたくなかったともいう。今村さんもそれには同感で、視覚障害のあるアーティストと何かをするというより、光島さんだったからできると思ったのだった。感覚の交換の仕方にも「理解する」、「伝える」、「共有する」などさまざまな方法がある。
光島さんは「今までは前に前に進むように来たんですけど、自分の感覚の原点になっているものを遡って掘り下げてみたいなと思って。井戸を掘るように自分の感覚をどんどん掘っていったら、その先で今村さんの感覚とまた結びつくんじゃないかとも思いました」と語る。
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)