2022.6.20
山で生きる祖父が体現していた、本当の意味での「稼ぐ力」
当記事は公開終了しました。
2022.6.20
当記事は公開終了しました。

そこそこ起業 異端の経営学者が教える競争せずに気楽に生きる方法
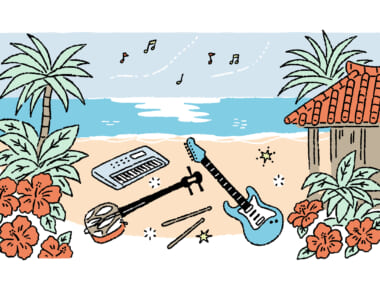
そこそこ起業 異端の経営学者が教える競争せずに気楽に生きる方法
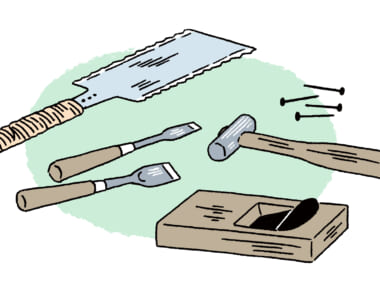
そこそこ起業 異端の経営学者が教える競争せずに気楽に生きる方法
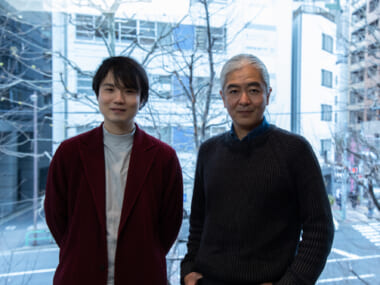
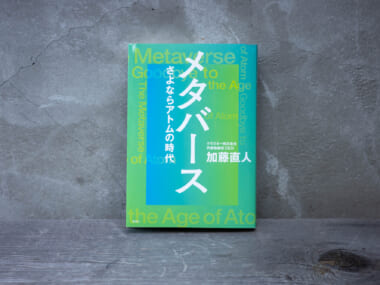
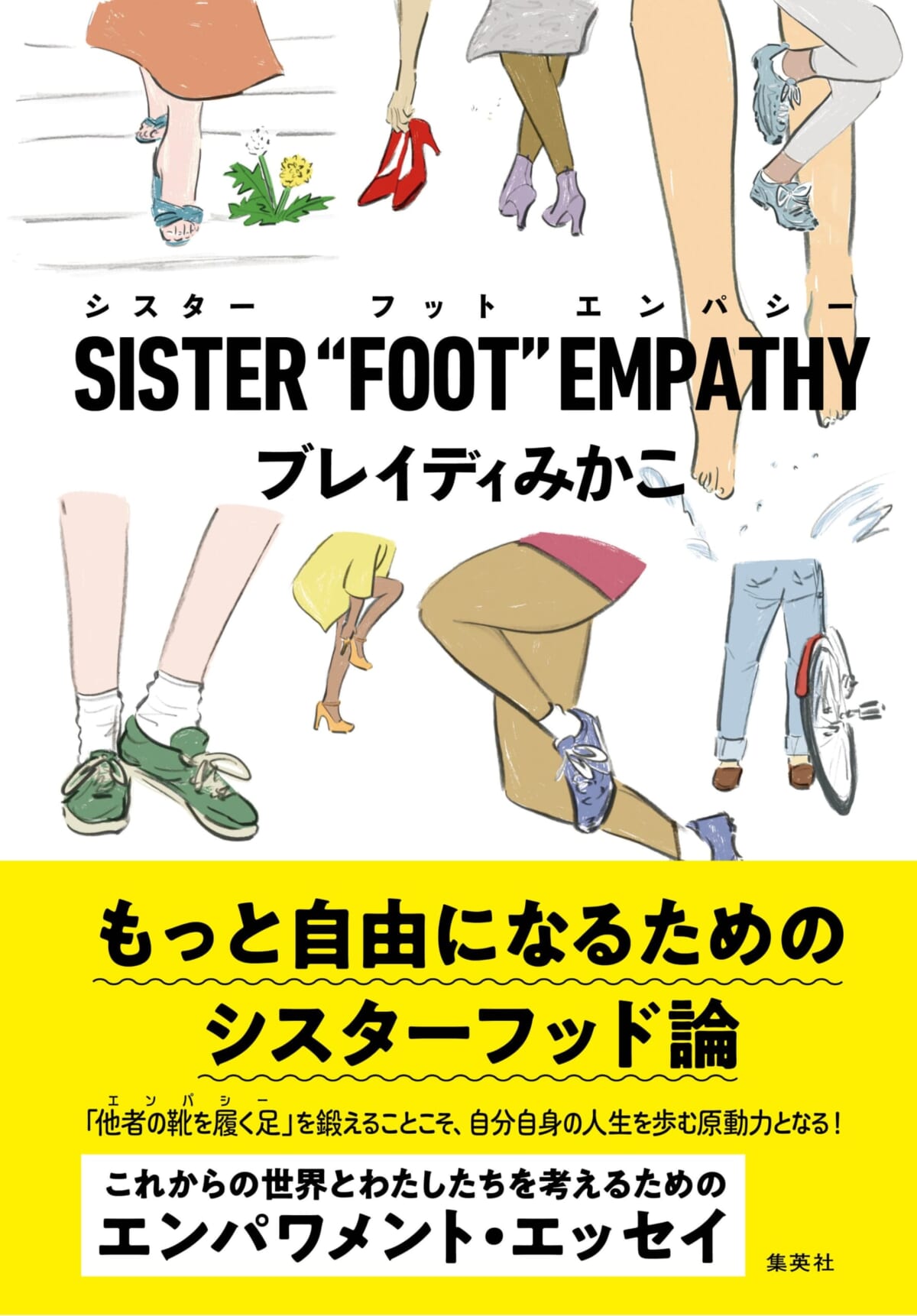
2025/6/26
NEW
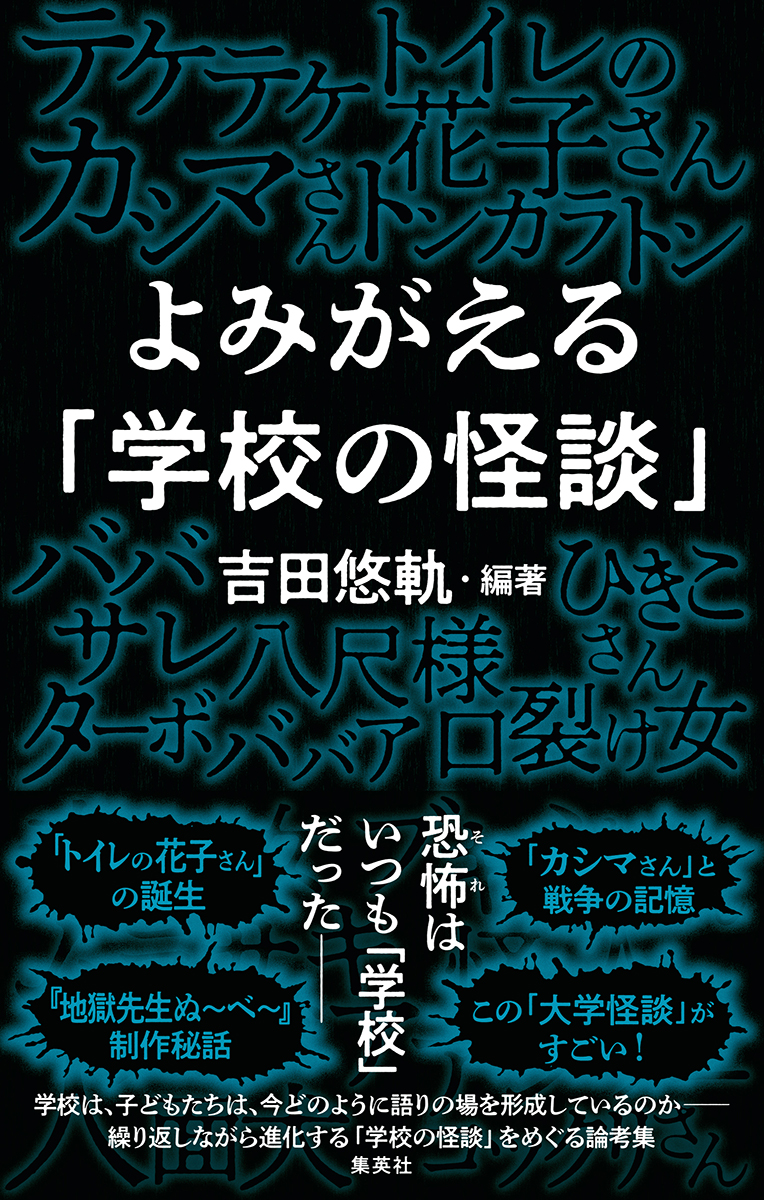
2025/7/4
NEW

2025/5/26
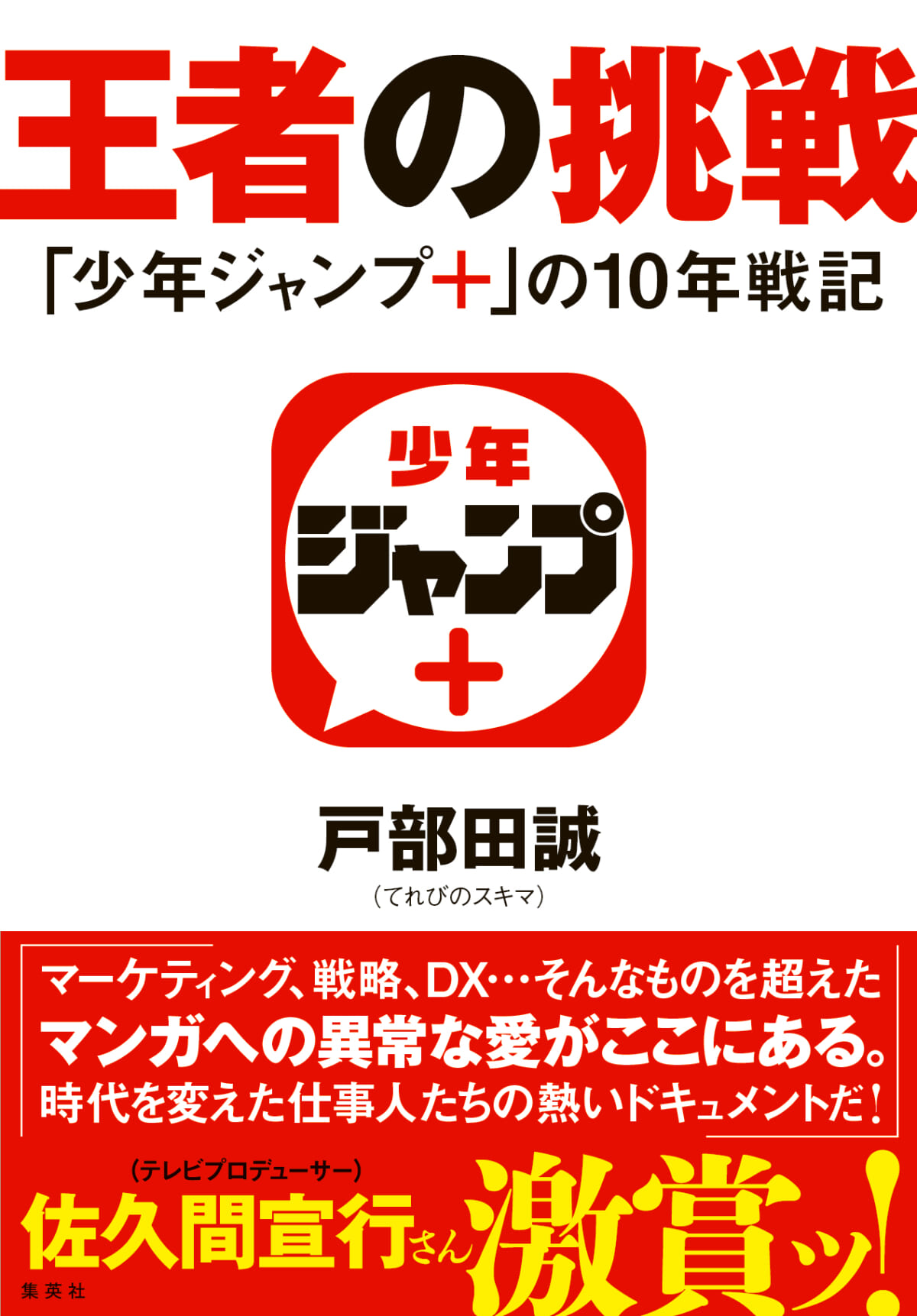
2025/5/9