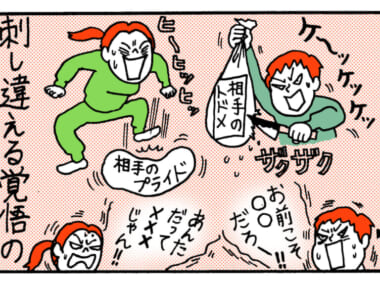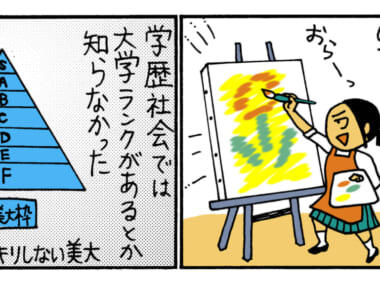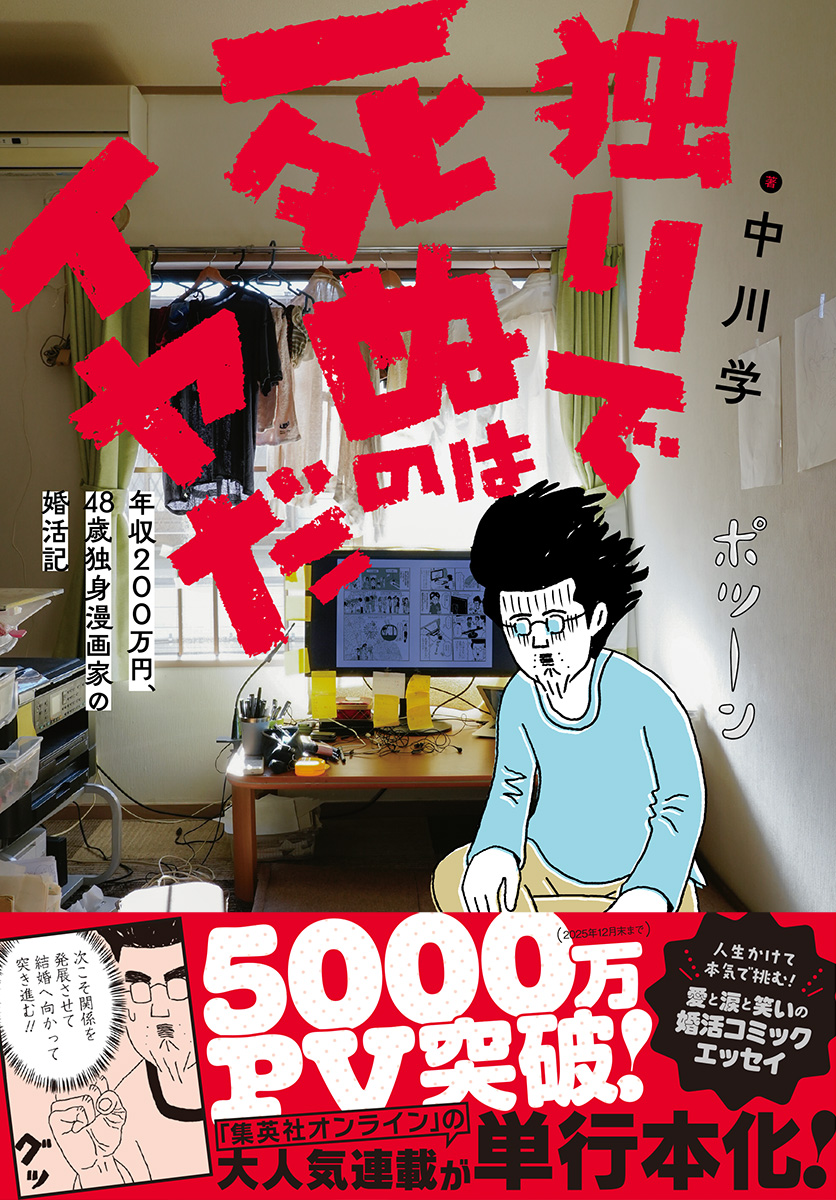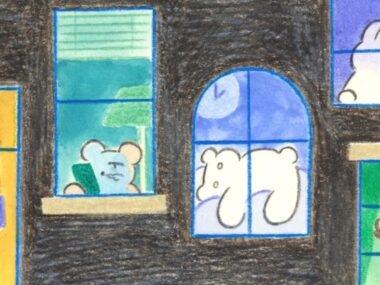2025.10.28
最終回 巧妙な差別──「今の時代、こんなこと言えないけど……」に潜むワナ
田房永子さんの漫画とともにお送りしてきた連載も今回が最終回。毎回、何気ないひと言にも、その奥には、秘められた意図があることをお伝えしてきました。そうして見えてきたのは、私たちが発することばは、想像以上に大きな力を持っているということ。最後にお届けするのは、そのことを最も実感するテーマ、「差別」です。
イラスト・漫画/田房永子
記事が続きます
差別発言をする人は「差別」と思っていない
昨今、国内外でジェンダーや民族、宗教など特定のアイデンティティを有する人々に対する差別発言が、マスメディアやネットで取り沙汰されているのをしばしば目にする。従来から存在したであろうこのような発言が問題視され、「ニュース」として価値を付与されるまでに人々が「差別」に対して意識的になったと歓迎すべきだろうか。
一方で、差別主義団体等による街宣活動や、国民の社会不安を背景とした保守政党の世界的な台頭など、「区別」と称する「差別」が公然と行われているという事実も存在する。彼らは否定的なステレオタイプに基づく差別的な発言をしながらも、「自分が行なっていることは差別である」あるいは「自分は差別主義者である」というレッテルを自分自身に貼ることはない。
私たちの多くは、こういった出来事を自分には関わりのない彼岸の火事と見なし、自分とは切り離して捉えている。「自分が行なっていることは差別である」あるいは「自分は差別主義者である」とは思っていない。しかし、社会にはびこる「差別の根」は、実は私たちの日常の当たり前の会話の中にこそあるのだ。声高に差別発言を行うような明らかなレイシストは、目立ちはするが、「差別」のごく一部しか構成していない。
今回は、60代男性友人同士の喫茶店での会話を例に挙げ、私たちの日常における「何気ないおしゃべり」の中で、差別がどのように実践されうるのかを考えたい。
※以下の会話は、筆者が過去に観察・調査した複数のやりとりの傾向をもとに構成したもので、実在の人物や出来事とは無関係です。
他愛ないおしゃべりに潜む差別
高山:60代男性
吉田:60代男性 友人関係
注:発話内の記号について
・「、」は短い「間」を表す。
・「//」は、次の発話が割り込まれた位置を示す。
・「?」は疑問ではなく、音の上昇を表す。
状況に応じて変わる「暑いね」の意味
会話をスムーズに進めるためには、「今、ここで何が行われているのか」を素早く把握し、そのフレーム(枠組み)の中で適切な振る舞いをする必要がある。
たとえば、「暑いね」という一言も、ことば通りだと気候の描写でしかないが、道端で近所の人とすれ違う時に言われれば「挨拶」になるし、自分の部屋に遊びに来ている友人から言われれば、「窓を開けてほしい」「エアコンを入れてほしい」という間接的な「依頼」になる。このような「今、ここで何が行われているのか」という状況を理解するための背景を、「コンテクスト」という。
コンテクストは多くの場合、明確に言語化されない。「悲しいことがあったから、今からあなたの同情をひく話をするよ」と話に入る前に宣言してくれれば楽なのだが、そういうことはなかなか起こらない。
相手がどのようなフレーム(枠組み)で話をしているのか、それに応じて自分には聞き手としてどのような態度が求められているのかは、相手の表情、声のトーン、ことば選びなど、さまざまな(非)言語的要素から推測しなければならない。このような、コンテクストを伝える要素を「コンテクスト化の合図」(Gumperz, 1982)という。
徐々に差別がつくられていく
高山と吉田の会話を見てみると、会話を主導する高山は、最初、外国人観光客に対してはっきりと否定的な内容を述べているわけではない。しかし「どこも混んでる」(高山1)という話題の導入に続いて用いられる公共交通機関であるバスに乗り込む「集団」(高山7)という語がコンテクスト化の合図となり、「外国人」という語と結びつくことで、「迷惑な外国人観光客」というステレオタイプ的なフレームを吉田に想起させている。
簡単にいえば、「空気を察し」ているわけである。そこで吉田に求められているのは、「同調」や「共感」といった「同じサイドに立ってくれる友人」としての振る舞いである。
吉田はこのフレームにすぐに応じ、「□□人(外国名)か」(吉田8)と、特定の国籍を想定することで、高山の語りに積極的に参加する。その後の高山の発話では、関西方言の卑罵的な助詞(高山11「乗り込んできよって」)により否定的態度が強調され、「カメラ」が観光客のステレオタイプに基づく否定的描写の道具として登場している。
「カメラ」ではなく「カメラみたいなもん」というぼかし表現は、「自分(たち)」と「外国人」との異質性をさらに際立たせる働きをしていると言えるだろう。
カメラを持った観光客の集団がバスに乗ることに対してなぜ高山が「かなわん」(参った)(高山13)のか明確な理由は述べられないが、吉田の調子の良い相づちに支えられ、ここで高山は初めて自分のもつ「外国人の集団」への否定的態度を明示的にことばにする。
続けて語られる浴場の場面では再び「あいつら」(高山15)という卑下表現が用いられ、自己/他者のカテゴリーが明確にされている。高山自身も仲間と連れ立って入浴しているにもかかわらず、外国人観光客だけを「おっさんの集団」と否定的に描いているのである。それに対し、吉田は笑いによってこの侮蔑的態度への支持を表明している。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)