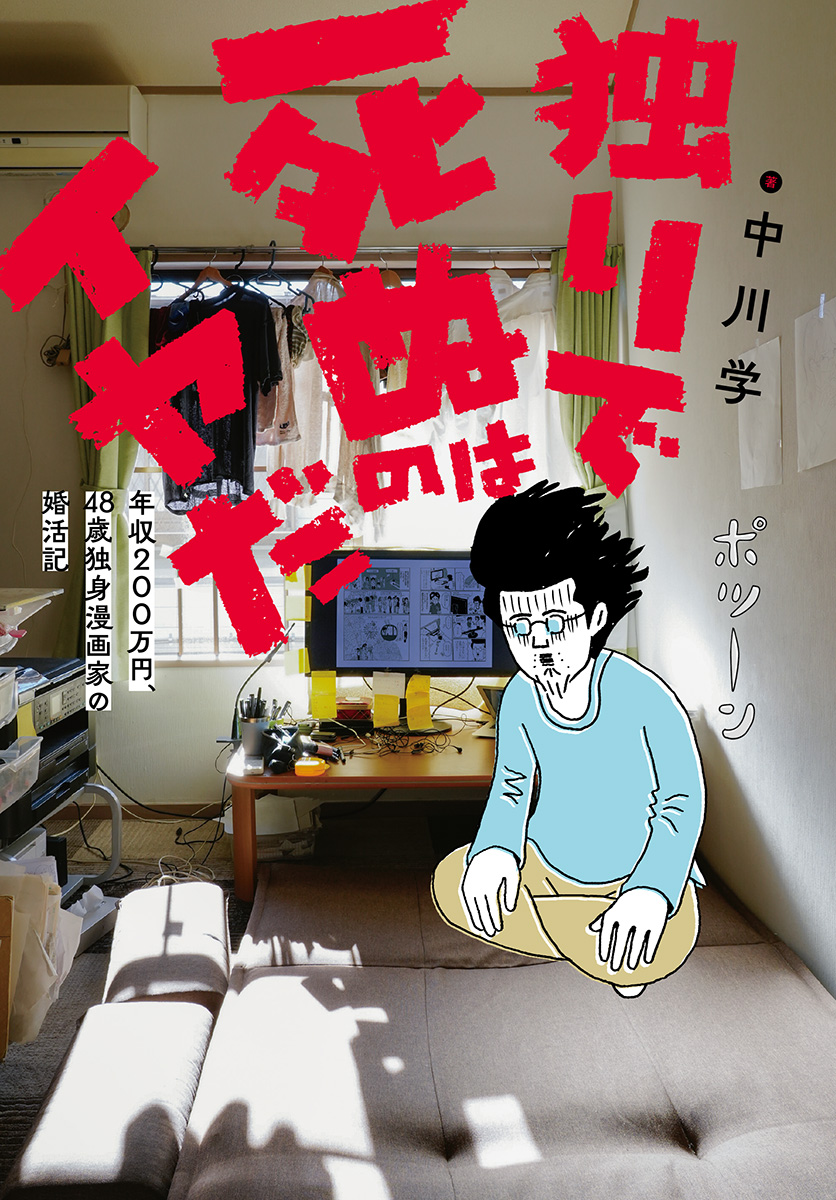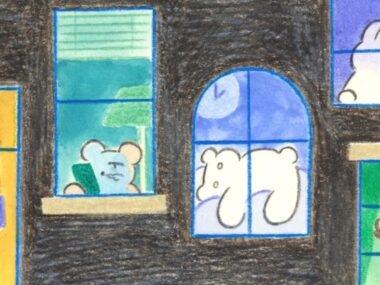2025.7.22
第3回 友人からのマウント。挑発に乗らず、どう切り抜ける?
大塚さんの研究手法は、当事者に実際の会話を録音してもらい、どのような場面で、どんなことばが用いられ、そのことばを通してどのように人間関係がつくられていくかを分析するというもの。リアルな会話を手に入れるのは困難を極めるそうですが、苦労の末に入手しただけあって、その中にはコミュニケーションを円滑にするためのヒントがいっぱい。
今回は、「マウンティング」がテーマ。挑発に乗らずに切り抜けるにはどうしたらいいのか? 田房永子さんの体験に基づいた漫画とともにお楽しみください。
イラスト・漫画/田房永子
記事が続きます
「マウントを取る」とはどういうことか
「マウントを取る・取られる」「マウンティング」という表現を巷で耳にするようになって久しい。これは「話し手が相手よりも自分を優位に位置付ける行為」全般に対して用いることができる表現のようだが、非常に現代的だと私が思うのは、そこにコミュニケーション的視点が含まれている点だ。
「話し手が自分を高く位置付ける行為」を表すだけなら、すでに「自慢」という表現がある。しかし、格闘技における「マウントポジション」をイメージしてもらえればわかるように、マウンティングには力をもって自分の優位性を相手に知らしめようとする強者と、力の差があるためにそれに従わざるをえない弱者が存在する。つまり単なる位置関係の上下を表すだけでなく、二者間の力関係をめぐるやりとりを表すコミュニケーション的視点を含む表現なのである。
しかし、格闘技では行為者の「相手を制圧してやろう」という攻撃的意図が誰の目にも明らかであるのに対し、コミュニケーションでは「他者の真意」などというものは誰にも決してわからない。それにもかかわらず、「マウントを取る」は、受け手が「相手は自分を制圧しようとしている」と相手の「悪意」を勝手に認定して非難する文脈で用いられる。
このように、「自慢」が「自分を高く位置付ける行為」でしかないのに対し、「マウントを取る」では、自他の位置付けに加え、「意図的に相手を圧倒しようとする行為」として話し手の「悪意」が勝手に認定されている。だから、そのラベリングを避けるために、話し手は是が非でも「その位置付けに『悪意』はない」ということを示さなければならない。こうしてマウンティングのストラテジーは巧妙になっていく。
今回はLINEでのやりとりを題材に、マウンティングについて考えていきたい。
※以下の会話は、筆者が過去に観察・調査した複数のやり取りの傾向をもとに構成したもので、実在の人物や出来事とは無関係です。
マウンティングの構造を理解する
山下…23歳男性(東都大学工学部:大学院生)
岡本…23歳男性(西都大学文学部:大学院生)
田村…21歳男性(北都学理学部:学部生)
(人名や大学名は、架空のものである)
以下は高校のバスケットボール部のLINEグループでのやりとりである。ここには現役高校生から最年長は23歳のOBを含む、多数の(元)クラブメンバーが参加している。
山下は難関大学である東都大学の理系の研究室、同期の岡本は、同じく難関大学の西都大学の文系の研究室に所属している。2年後輩の田村は地方の大学の学部生という設定である。
主にグループ内で最年長である山下と、同期の岡本、そして彼ら二人と直接面識のある後輩・田村との間で交わされたやりとりである。高校生の現役メンバーからOBに対してアンケートを依頼するところから始まり、次第に年長のOBによるマウンティングが展開されていく。
高2の◯◯(名前)です。
アンケートにお答え頂いたOBの方々貴重なご意見ありがとうございました!まだ回答されていない方は引き続きよろしくお願いします。.
今年からSNS担当になったのですが、何つぶやいていいかわかりません笑 週末も遠征続きで今年に入って休日は2日のみです
皆さん大学で運動系クラブ入るときはお気をつけて.
現役生へ、文系は比較的まともな生活を送れるはずだよ()*.
*・・・(笑)を表すネットスラング
自分を下に見せかけて上から目線
今回は、(山下9)「まだ東都大の研究室をクビにならずにすがりついてるOBです」と(山下18)「理系院生がひく社畜っぷり。現役生へ、文系は比較的まともな生活を送れるはずだよ()」を「マウンティング」と捉えて分析を行いたい。
現役生によるOBへのアンケートの依頼に対して、山下・岡本がそれぞれ了解の旨をスタンプで返信した後、(岡本4)では続けて、「中国に3ヶ月行くことになったOB」と岡本の自己紹介が行われる。
次に、後輩である田村が登場する。(田村7)で山下と岡本を名指して挨拶(「お久しぶりです」)をするが、山下はこれに挨拶を返した上で、(山下9)では難関の東都大学に所属していることを出し、「まだ東都大をクビにならずにすがりついてるOBです」と自己紹介を行う。
これは、(岡本4)の自己紹介に対応した「単なる自己紹介」に見える。しかし、あえて大学名を挙げて「研究室」を出し、「クビにならず」というわざわざ自己卑下するような表現を用いることには別の意図が含まれているように思われる。
「クビにならず」という表現は、自分が「クビ(除籍)になる」可能性を前提としている。つまり自分に関するネガティブな情報を提示していることになるのだが、その反面、所属する「ブランド」大学がそれほど優秀な学生の集まる組織であることも言外に意味しているのである。
理系vs文系、どっちが上?
その後、話題は所属クラブのSNS担当である田村の多忙さへと移る。「今年に入って休日は2日」しか取れていないという愚痴(田村16)に対し、(山下18)は「理系院生がひく社畜っぷり。現役生へ、文系は比較的まともな生活を送れるはずだよ()」と返す。最初の一文の「理系院生がひく社畜」という表現には、理系院生が「社畜」であるという前提と、その前提が一般に共有されている(はず)という態度が含まれている。そして続けて、「文系は比較的まともな生活を送れる」と、「社畜」である理系院生と「まともな生活」ができる文系という対比構造を作り出す。
「社畜」という表現は、「会社に飼い慣らされ、辛い仕事にも文句を言わずに働く会社員」という否定的な意味を持つ。これは普通勤め人に対して使われる表現だが、理系の大学院修士学生は多くの場合、研究室の階層構造では下層に位置付けられ、上からの指示に従って動かざるを得ないため、このように表現しているものと思われる。
「社畜」と「まともな生活」であれば当然、「まともな生活」のほうが一般的には肯定的に評価されるだろう。しかし、ここでは実は、2つの異なる価値基準のすりかえが行われている。一方には、私生活を犠牲にして忙しく一生懸命に働く(研究する)ことを肯定的に捉える価値観があり、他方には、仕事(研究)はしつつも私生活を充実させることを是とする価値観がある。山下は、自分の所属する難関大の名前を出し、「院生」という高校生や学部生にとっては何となく「すごそう」と感じられる一人称を用いて自分を「忙しい人間」=「研究室や社会に必要とされる能力の高い人間」として提示しており、実際には前者に価値を置いているらしいにもかかわらず、あたかも「まともな生活」の方を称賛するかのような書き方をしているのである。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)