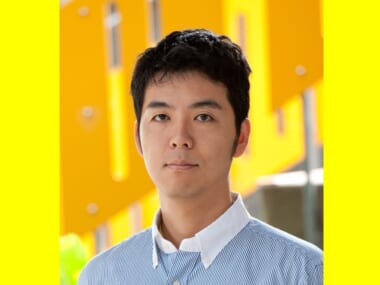2025.5.7
「特定の和音からアイスクリームのような味がする」共感覚の研究でわかったクオリアとの関係とは──東京大学准教授・浅野倫子インタビュー
なぜ共感覚が生じるのか
記事が続きます
人口の数%程度とはいえ、一部の人はなぜ共感覚を持つのか。このような問いにはっきりした答えを得ることは難しいですが、学習や記憶と関係があるかもしれないと議論されています。たとえば、文字から色を連想する共感覚なら、色が、「『あ』という発音=赤のラベル」などというふうに、文字の特徴をラベリングするような 役割を果たして、学習や思考の補助をしているかもしれません。
話したように共感覚にはいろいろあって、中には水泳のフォームに色を感じるような面白い共感覚もあるのですが、報告例が多いのは文字―色、あと音―色が結びつくタイプです。冒頭でお話しした、月日に空間配置を感じる共感覚も多いですね。
よく見られるこういった共感覚には、「抽象的な情報で、かつ順序などの構造を持つもの 同士が結びつく」という共通点があります。あと、文字―色タイプの共感覚者でも、未知の外国語など読めない文字には色を感じないのですが、勉強して字の意味がわかるようになると色が生じるなど、共感覚が意味や概念といった高次な情報処理に関わっていることを示す研究もあります。こういった事実も、共感覚と学習や思考、記憶などとの関係を示唆しているかもしれませんね。
共感覚のクオリア構造どうしを結び付ける
さて、ここからがクオリアとも関係がある話です。また文字―色タイプの共感覚を例に挙げると、今述べたように、文字にも色にも、あいうえお順とか、明度や彩度による順列などの抽象的な構造 がありますよね。
共感覚を持つ人の調査をしていると、似た形の文字ほど近い色を感じるとか、使用頻度が高い文字ほど鮮やかになる……といった傾向が見られます。つまり、共感覚者は、いわば、特定のクオリア(例:文字)の構造と、別のクオリア(例:色)の構造とを結び付けている印象を受けるのです。
ここで面白いのは、クオリアが「似ている」とか「近い」ということは、その元となる情報が物理的に似ているかどうかとは必ずしも一致しないということです。たとえば、色は物理的には「特定の波長の可視光線」ですが、一番波長が長いのが赤で、もっとも短いのが紫です。つまり波長を基準にすると赤と紫は一番かけ離れているのですが、クオリアとしてはどうですか? むしろ近い印象を受ける方が多いのではないでしょうか。
また、赤や紫のような色相ではなく、明度や彩度を「物差し」にして「似ている」と考えることもできます。「似ている」とか「違う」と言っても、類似度を測る物差しには色々あって、どれを使うかによってクオリア構造の形が変わる可能性があるんですね。共感覚が異なるクオリア同士の構造の結びつけであるかを調べるためには、文字や色の物理的な類似度ではなく、その人の頭の中でのクオリアの類似度に迫る必要があります。
それは簡単な話ではありません。共感覚を持つ方の話を聞いていると、かれらが感じるクオリアが非常に繊細で複雑であることを痛感するんですね。色についての実験だと、どうしてもディスプレイの色を見せることになるのですが、「私はたしかに『あ』という文字に赤色を感じるけれど、その赤はこんなツルツルではなく、水彩絵の具のような質感の赤なんです」などと言われることがよくあります。「似ている」と言っても、その実際はもっと複雑なようなのです。
いずれにしても、共感覚からのアプローチでも、クオリアの構造はかなり複雑であるらしいことはわかります。私がクオリア構造学に参加しているのは、今までの共感覚の研究でクオリアの構造に興味をもったからです。
言葉の研究から共感覚研究へ
実は、私ははじめから共感覚を研究していたのではありません。もともとは単語や文章の認知を研究していました。
文章の認知って、面白いんですよ。文の読み方は、一般に思われているよりずっと多様なんです。
たとえば、「共感覚」と書くべきところに「共感楽」とか「共感格」などと書いてあったら誤字ですよね。でもこの場合、後者のほうが誤字を見つけるのが難しいのです。なぜなら、読みが同じだからです。黙読で校正(文章のチェック)をする場合でも、どうやら人は脳内で音としての情報も処理しているようなのです。
プロの校正者の方の話を伺ったことがあるのですが、かれらは複数の読み方を使い分けていると言っていました。通常は文字や文章の意味を思い浮かべながら読み進めますが、あえて意味を読まないようにして、文字の形だけに注意を集中する読み方をする場合もあるというのです。その方が誤字を発見しやすいというんですね。
これは、文や文字の意味だけに注意を向けてしまうと、「ふんふん、こういう意味だな」というトップダウンによる意味の処理が優先されてしまい、細かい漢字の誤りなどを見落としやすくなるためです。脳は文章を読むときに、文脈や意味からのトップダウンの処理もやっているんです。
当時は、脳がいかにして一つ一つの単語を認知して文章として理解するか、というボトムアップの研究が主流でした。それはもちろん大事なのですが、たとえば「斜め読み」をするときには、そんな読み方はしていませんよね。字面をさっと眺めるだけなのに、なぜか大まかな意味は把握できる。これは、一文字一文字を順次、認識していくボトムアップの精読とは別に、文脈を重視したトップダウンの読み方もあることを意味しています。
博士課程での私は四苦八苦しながらそういった研究をしていたのですが、そのころたまたま、私がいた研究室と隣の研究室にそれぞれ一人ずつ、「文字に色が見える」という共感覚を持つ学生さんが入ってきたんですね。それで興味をもってかれらと話していると、どうも文字から感じられるという色には、その字の音や意味が関係しているような気がする。当時の私が取り組んでいた文字の認知研究とも無関係ではないように思えたのです。
コミュニケーションの神秘
こうして私は共感覚の研究をはじめたのですが、文字の認知にせよ共感覚にせよ、根底にあるのは、ヒトの認知の奥深さや多様さへの興味と、それほど異なる認知を持つ人々がコミュニケーションをとり、同じ社会を築き上げていることの驚きです。
同じ文字ひとつとっても、意味に加えて色を感じている人もいますし、その色も人によって違う。もちろん、共感覚を持たない人の文字の認知も一様ではないし、さらには頭の中にある色や意味の構造、クオリアの構造もどうやら異なるらしい。
つまり、私たちは皆、お互いに分かり合っていると信じて日常を営んでいるのですが、実はそれぞれがちょっとずつズレた世界に住んでいるんです。それは誤解やすれ違いの原因にもなるけれど、豊かさでもあると言っていいのではないでしょうか。
浅野倫子(あさの・みちこ)プロフィール
東京大学大学院人文社会系研究科 准教授。専門は認知心理学、特に言語の認知処理や、共感覚、感覚間協応等の多感覚情報処理のメカニズムの解明。著書に『共感覚 - 統合の多様性』(横澤一彦氏との共著、勁草書房 2020年)など。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)